 マンサク マンサク
 2月から3月にかけて、各地の山地に黄色い花を、枝いっぱいにつけた、高さ3〜5mの落葉樹を見ることができます。マンサク科のマンサクです。 2月から3月にかけて、各地の山地に黄色い花を、枝いっぱいにつけた、高さ3〜5mの落葉樹を見ることができます。マンサク科のマンサクです。
早春、葉に先だって数個の花が、かたまって咲きます。1個の花には、幅のせまいちぢれたリボンのような黄色の花弁が4枚ついています。花弁の外側には、がく片が4個あり、卵形で内面
が紫紅色をしています。それが花弁の黄色をいっそう引き立てています。
葉は、ややゆがんだ幅の広い菱形で、長さ5〜10cm、幅3〜7cmで、やや厚いしっかりした葉です。若葉には毛がありますが、後に無毛となります。冬には葉が落ちますが、写
真では風あたりの少ない庭に植えられているため、花の時期になっても、枯れ葉が落ちないで残っています。
マンサクという名前は、早春に他の花にさきがけて先ず咲くというところからついたという説と、この花が枝いっぱい咲くところから、穀物が豊かにみのる様子にたとえて、この花がたくさん咲くと、その年は豊年満作になる前ぶれであるとしてつけられたという説とがあります。
早春、花の少ない時期に、美しい花を咲かせるので、庭園にもよく植えられています。
|
 フクジュソウ フクジュソウ
 フクジュソウを漢字では福寿草と書きます。幸福で長寿の草という意味で、正月の床飾りに用いられ、年の暮れともなると、園芸店や植木市などで立派な鉢に植えられ、高値で売られています。これは温床などに入れて、正月に花が咲くように発育をうながしたものです。 フクジュソウを漢字では福寿草と書きます。幸福で長寿の草という意味で、正月の床飾りに用いられ、年の暮れともなると、園芸店や植木市などで立派な鉢に植えられ、高値で売られています。これは温床などに入れて、正月に花が咲くように発育をうながしたものです。
フクジュソウは、キンポウゲ科の多年草で、北海道から四国、九州まで広く分布していますが、どちらかというと北の方に多く、南にいくにつれて少なくなります。とくに北海道には多く生育しています。落葉樹林に生え、茎は高さ15〜30cmになります。
葉は細かく羽状に分裂し、花は黄金色で径3〜4cmになり、数個のがく片と20〜30個の花弁があります。自然の状態では、花は3〜4月に咲き、開花後に茎がのびて葉が広がります。まわりの樹木の葉が茂りだす5月下旬には結実して、活動をを終えます。
園芸的に栽培されるようになったのは、元禄時代の頃からで、ことに文化から天保にかけて、その培養がさかんとなり、多くの品種が生まれています。
|
 ヤブツバキ ヤブツバキ
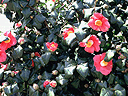 ヤブツバキは、野生のツバキのことです。早春から開花し、花は赤色で大きく、とても立派です。花弁(花びら)は5枚で、花弁の基部は合着しています。 ヤブツバキは、野生のツバキのことです。早春から開花し、花は赤色で大きく、とても立派です。花弁(花びら)は5枚で、花弁の基部は合着しています。
雄しべはたくさんあり、先端のやく(花粉の入っている袋)は黄色です。雄しべの下半部は合着して筒状になっています。そのため、花が終わっても形がくずれないまま、雄しべをともなって落ちます。雌しべ先は、3つに裂けています。花の底から蜜が出るため、メジロなどの小鳥が蜜を吸いにきて、花粉を雌しべの先につけるはたらきをしてくれます。
ヤブツバキは、日本の南部から九州・四国・中国・近畿地方の、主として太平洋側に厚く分布しています。中部地方や関東地方では海岸寄りに多く、内陸に入るにしたがって少なくなります。福島県以北では、分布がとぎれとぎれになり、ごく一部に、わずかしか見ることができなくなります。
これは、シイやカシなどの常緑広葉樹の分布と同じで、森林の高木の生える層(高木層)にシイ、カシ、タブノキが生え、その下の亜高木層にヤブツバキ、シロダモ、モチノキが生えます。東北から北陸の日本海側の豪雪地帯には、葉が濃く、枝が雪のために下に垂れ、地表に接した枝から根が出る性質をもったユキツバキが分布します。
ヤブツバキは、花が美しく、また種子から椿油がとれ、材も器具材となるので、昔からよく植えられ、多くの園芸品種もつくられています。
サザンカは、ツバキに似ていますが、花弁や雄しべが基部まで離れています。そのため、花が落ちるときは、花弁がばらばらになってしまいます。
チャノキ、サカキ、ヒサカキ、ヒメシャラ、モッコクなどもツバキ科です。
|
 ナズナ ナズナ
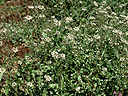 ナズナは、春の七草の代表です。正月七日は、七草といって、七草がゆを食べる習慣があり、ナズナが代表として用いられます。ナズナはアブラナ科の越年草で、道ばた、畑、校庭など、日あたりのよい場所ならばどこでも生える雑草です。 ナズナは、春の七草の代表です。正月七日は、七草といって、七草がゆを食べる習慣があり、ナズナが代表として用いられます。ナズナはアブラナ科の越年草で、道ばた、畑、校庭など、日あたりのよい場所ならばどこでも生える雑草です。
よく見れば薺 (なずな)花咲く垣根かな
(芭蕉)
とあるように、古くから人々に親しまれ、また果
実の形が三味線のばちに似ているところから、ペンペン草という名で、子どもたちの遊びにもよく登場します。
秋に芽生えた苗は、やがて切れ込みの深い葉を放射状に地表に広げ、ロゼットで冬を越します。春になると花茎をのばし、径5mmほどの白い十字形花を総状につけ、下から上へと順次に花を咲かせます。花は3月から6月頃まで咲き続け、その後枯れて一生を終えます。
写真では、ナズナのほかに、白い小さな花がコハコベ、左下に見えるピンクの花はホトケノザです。
|
 コハコベ コハコベ
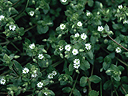 ハコベは、セリやナズナとともに春の七草に数えられ、「はこべら」という名で、昔から若菜つみとして親しまれた野草です。 ハコベは、セリやナズナとともに春の七草に数えられ、「はこべら」という名で、昔から若菜つみとして親しまれた野草です。
一般にハコベとよんでいる植物には、コハコベとミドリハコベがあります。コハコベに比べてミドリハコベのほうが大きいのですが、生えている量
は、コハコベのほうが圧倒的に多く、道ばたや畑などに見られるハコベは、多くはコハコベです。ミドリハコベは、林の縁や立木の下など、やや陰になる所に多いようです。
区別点は、コハコベの茎は紫褐色ですが、ミドリハコベの茎は緑色です。葉の色はコハコベのほうが、ミドリハコベより緑が濃く、葉の大きさは、ミドリハコベがコハコベの数倍にもなります。花は、コハコベの花弁は深く裂け、左右の裂片が重ならないので、5枚の花弁が10枚に見えます。ミドリハコベの花弁も深く裂けますが、左右の裂片が重なるので、10枚のようには見えません。さらにルーペで雄しべの数を調べますと、ミドリハコベでは10本が基本ですが、コハコベでは5本が基本です。以上の点で、両種を区別
することができますが、このほかに、すべてが超大形のウシハコベというのもあります。
ハコベは春の七草として摘み草の対象ですが、食べるには、ミドリハコベのほうが適しています。若い部分を摘んで一度ゆでこぼし、ひたし物、あえ物、汁の実、油いため、天ぷらなどにして食べます。また、カナリヤなどの小鳥の餌としても利用されます。
|