 オギ オギ
 「十五夜のお月見に,ススキを採ってきました。」と言う隣家の奥さんが手にした植物を見ると,それはススキにあらず,オギでした。オギは漢字で荻,東京には荻窪(おぎくぼ)という地名がありますが,昔はオギがたくさん生えていた窪地があったのかもしれません。 「十五夜のお月見に,ススキを採ってきました。」と言う隣家の奥さんが手にした植物を見ると,それはススキにあらず,オギでした。オギは漢字で荻,東京には荻窪(おぎくぼ)という地名がありますが,昔はオギがたくさん生えていた窪地があったのかもしれません。
オギはイネ科の多年草で,ススキによく似ています。ススキは,乾いた草原に生えますが,オギは河岸や水辺など,湿った所に生えます。ススキは,大きな株を作りますが,オギは地下茎を長くのばし,地下茎から茎が1本ずつ間隔をとって生えるので,株を作らず大きな群落を作ります。草の大きさも,ススキより大きく,高さは2mを超し,葉の幅は3cmにもなります。花穂が出る頃になると,茎の下部の葉は葉鞘(ようしょう)とともに脱落するので,竹のように節のある茎が露出します。
花穂も大きく,長さ20〜40cmになります。ススキの小穂には長い芒(のぎ)がありますが,オギの小穂には芒がありません。
ススキの小穂の基部の毛は,白色または,わずかに淡紫色を帯びますが,オギでは銀白色で長く,花穂が風になびくと,銀白色の花穂の波ができて壮観です。河原では,オギの群落ができますが,水のある所にはオギの群落は発達しません。水のある所では,いちばん先端の深いところにガマ,次にマコモ,水位
が浅くなるにしたがってヨシの群落となり,岸から離れ,水のない所にオギの群落が発達し,さらに乾いた所になるにしたがって,ススキの群落に移行します。
野口雨情作詞になる『船頭小唄』の「俺(おれ)は河原の枯れすすき,おなじお前も枯れすすき…」は,どうもススキではなく,オギをススキと見間違えたのではないでしょうか。
荻の花 揺れて折々むき変わり 加賀谷風秋
|
 ノブドウ ノブドウ
 名前のとおり,山野の林縁や垣根などに絡み付く野生のブドウですが,食べられません。 名前のとおり,山野の林縁や垣根などに絡み付く野生のブドウですが,食べられません。
茎の基部は木質となり,太いものは直径4cmくらいになり,つるはジグザグに曲がり長くのびます。葉は,ほぼ円形で基部心形,3〜5裂し,ときに深く裂けます。葉の裏は無毛か僅(わず)かに有毛。巻鬚(まきひげ)は葉と対生し,先が二股に分かれます。夏に柄のある集散花序を葉に対生して出し,緑色の小さな花をつけます。
果実は,6〜8mmの球形の液果で,ブドウタマバエや,ブドウトガリバエなどの幼虫が寄生して虫こぶとなり,不規則にゆがんだ球形となります。白,紫,青色と,色とりどりで,ときに径1.5cmにもなります。
よく似たエビズルは,葉の裏に綿毛が密生するので区別できます。エビズルの果
実は黒紫色に熟し,甘酸っぱく食べられます。
|
 シオン シオン
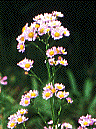 シオンは,キク科の多年草で,茎は直立して,高さ1〜2mにもなります。根生葉は大形の長楕円(だえん)形で,長さ約30cmにも達しますが,開花時には枯れます。茎の葉は幅が狭く,茎の上部に移るにしたがって線形になります。秋に,上部で枝を分けて,径3cmほどの青紫色の美しい花をたくさんつけます。
漢字では紫苑と書き,俳句では秋の季語になっています。 シオンは,キク科の多年草で,茎は直立して,高さ1〜2mにもなります。根生葉は大形の長楕円(だえん)形で,長さ約30cmにも達しますが,開花時には枯れます。茎の葉は幅が狭く,茎の上部に移るにしたがって線形になります。秋に,上部で枝を分けて,径3cmほどの青紫色の美しい花をたくさんつけます。
漢字では紫苑と書き,俳句では秋の季語になっています。
淋しさを猶(なお)も紫苑ののびるなり
正岡子規
平安時代から,観賞用として庭園に植えられてきましたが,もとは,根を鎮咳(ちんがい)剤,去痰(きょたん)剤とするために,朝鮮か中国から持ち込まれたようです。朝鮮半島,中国北部,東北部,モンゴル,シベリアなどでは,野生状態で普通
に見られます。日本では,野生化したものは中国地方と九州の高原にまれに見られる程度です。
|
 ヤナギタデ ヤナギタデ
 ヤナギタデは,川べり,湖沼のほとりなどの湿地に生えるタデ科の1年草です。茎は直立し,枝を分け,高さ30〜80cm。葉は長さ3〜10cm,幅1〜2cm,披針形〜長卵形で,両端は細まり,両面
に透明な小腺(せん)点があります。葉の基部の托葉鞘(たくようしょう)は筒状で膜質,短い緑毛があります。 ヤナギタデは,川べり,湖沼のほとりなどの湿地に生えるタデ科の1年草です。茎は直立し,枝を分け,高さ30〜80cm。葉は長さ3〜10cm,幅1〜2cm,披針形〜長卵形で,両端は細まり,両面
に透明な小腺(せん)点があります。葉の基部の托葉鞘(たくようしょう)は筒状で膜質,短い緑毛があります。
花は,夏から秋に,長さ4〜10cmの細長い総状花序に,まばらにつきます。花弁がなく,萼(がく)だけの花で,萼は4〜5裂して黄緑色で,先が赤みを帯び,透明な腺点が密にあって,長さ2.5〜4mmです。雄しべは6本,果
実はレンズ形です。イヌタデのような,はなやかな花色はないのですが,落ち着いた地味な花色です。
葉に辛味があり,葉を噛(か)んでみれば辛いので,他のタデと区別
することができます。
刺身のつまにつく赤い小さな芽は,このヤナギタデの栽培種の芽生えで,その辛味を賞味します。この栽培種は,ホンタデとか,アザブタデ(エドタデ)という名前で栽培されています。「蓼(たで)食う虫も好き好き」という諺(ことわざ)がありますが,夫婦の取り合わせの様子を,こんな辛い葉を食う虫もいるのだと,揶揄(やゆ)してできた諺なのです。
|
 セキヤノアキチョウジ セキヤノアキチョウジ
 関東地方および中部地方の山地の木陰に生えるシソ科の多年草です。茎は四角形で,高さ1mくらいになります。葉は対生し,長楕円(だえん)形で,長さ5〜15cm,幅2〜5cm,両端は長く尖(とが)り,葉縁には低い鋸歯(きょし)があります。 関東地方および中部地方の山地の木陰に生えるシソ科の多年草です。茎は四角形で,高さ1mくらいになります。葉は対生し,長楕円(だえん)形で,長さ5〜15cm,幅2〜5cm,両端は長く尖(とが)り,葉縁には低い鋸歯(きょし)があります。
秋に,枝先や葉腋(ようえき)から花枝を出し,長さ1〜2.5cmの細長い花柄の先に,美しい青紫色の唇形花を多数つけます。花冠は細長く,長さ2cmくらい,上唇は,反り返って浅く4裂します。萼(がく)の上唇の歯は,披針形でやや尖っています。
同じ属で,よく似たアキチョウジは,花柄が1cm以下で,萼の上唇の歯が短く鈍頭です。分布は岐阜県以西で,両種の分布は重なりません。
|
 ホトトギス ホトトギス
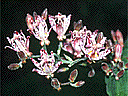 ホトトギスは,山地の木陰に生えるユリ科の多年草です。茎は直立するか,または崖(がけ)から垂れ下がり,茎の長さは40〜80cmで,粗毛があります。葉は互生して左右に並び,長楕円(だえん)状披針形で軟毛があり,表面
にはしばしば油をたらしたような斑紋(はんもん)があります。葉の先はしだいに尖(とが)り,葉の基部は茎を抱きます。 ホトトギスは,山地の木陰に生えるユリ科の多年草です。茎は直立するか,または崖(がけ)から垂れ下がり,茎の長さは40〜80cmで,粗毛があります。葉は互生して左右に並び,長楕円(だえん)状披針形で軟毛があり,表面
にはしばしば油をたらしたような斑紋(はんもん)があります。葉の先はしだいに尖(とが)り,葉の基部は茎を抱きます。
9月から11月頃にかけて葉腋(ようえき)に2〜3個の花を上向きにつけます。花被片の内部には紫紅色の斑紋があり,この斑紋を鳥のホトトギスの胸にある斑紋に見立てて,ホトトギスという名がつきました。
花被片は6個で,互いに離生して,花が終わると1枚ずつ離れて落ちます。外花被片の基部は,ふくれて小さな距(けづめ)となって,中に蜜(みつ)を出します。雌しべの花柱は3裂して外側に曲がり,それぞれの先は,さらに2つに裂けて柱頭になります。
雄しべも外側に曲がり,ハチが蜜を吸うときに,ハチの背中に葯(やく)や柱頭が触れる仕組みになっているのです。
ホトトギスの仲間には,花が上向きに咲くホトトギス,ヤマホトトギス,ヤマジノホトトギスのグループと,花が下向きに咲くジョウロウホトトギスの仲間があります。
また,このグループとは関係なく,タマガワホトトギス,キイジョウロウホトトギス,サガミジョウロウホトトギスなどがあって,花は黄色です。ホトトギスの仲間はいずれも花の形が面
白く,色も美しいため,観賞用として珍重されます。ホトトギスの仲間は,日本に約10種,東アジア〜インドに20種内外あります。
|
 ヤクシソウ ヤクシソウ
 山地の道ばた,林の縁などに生えるキク科の越年草で,高さ30〜80cm,よく分枝して黄色の花をたくさんつけて,秋の野山を彩
ります。根生葉は,さじ形で長い柄があり,茎に生える葉は,葉柄がなく,基部で茎を抱きます。葉は薄く柔らかで,切ると白色の乳液が出ます。頭花は径約1.5cmで,すべて黄色の舌状花よりなり,総包は黒っぽい緑色です。花後に葉柄が曲がって,総包は下を向きます。そう果
は黒褐色で,冠毛は白色。 山地の道ばた,林の縁などに生えるキク科の越年草で,高さ30〜80cm,よく分枝して黄色の花をたくさんつけて,秋の野山を彩
ります。根生葉は,さじ形で長い柄があり,茎に生える葉は,葉柄がなく,基部で茎を抱きます。葉は薄く柔らかで,切ると白色の乳液が出ます。頭花は径約1.5cmで,すべて黄色の舌状花よりなり,総包は黒っぽい緑色です。花後に葉柄が曲がって,総包は下を向きます。そう果
は黒褐色で,冠毛は白色。
北海道から九州,朝鮮,中国,ベトナムにも分布。和名を薬師草といいますが,語源はわかりません。
|
 センブリ センブリ
 日当たりのよい山野に生えるリンドウ科の越年草です。茎は直立して,高さ20〜25cmほどになり,紫色を帯びます。茎の葉は対生し,線形で,長さ1.5〜3.5cm。 日当たりのよい山野に生えるリンドウ科の越年草です。茎は直立して,高さ20〜25cmほどになり,紫色を帯びます。茎の葉は対生し,線形で,長さ1.5〜3.5cm。
8〜11月に,円錐状に多くの花をつけます。花冠は白色で,5つに深く裂け,裂片は広被針形で紫色の脈があります。全草に強い苦みがあり,千度振り出しても苦いので千振と言います。昔から健胃剤として有名で,当薬(とうやく)の名もあります。分布は北海道南西部〜九州,朝鮮,中国で,すべて野生のものが利用されてきましたが,最近は栽培も始まり,品質の研究もされています。
よく似ているムラサキセンブリは,薬効はないといわれています。
|

 オギ
オギ
 セキヤノアキチョウジ
セキヤノアキチョウジ
