 ピラカンサ ピラカンサ
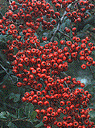 ピラカンサは,赤い実が枝いっぱいにつくバラ科の常緑低木です。中国雲南省の原産で,明治中期にフランスから新宿御苑に輸入されました。Pyracanthaという学名は,ギリシャ語で「火+棘(とげ)」を意味する造語です。寒さに強く,赤い実が美しく,棘が痛いので,泥棒やイヌ・ネコもくぐらないということから生け垣材料としてさかんに植えられました。 ピラカンサは,赤い実が枝いっぱいにつくバラ科の常緑低木です。中国雲南省の原産で,明治中期にフランスから新宿御苑に輸入されました。Pyracanthaという学名は,ギリシャ語で「火+棘(とげ)」を意味する造語です。寒さに強く,赤い実が美しく,棘が痛いので,泥棒やイヌ・ネコもくぐらないということから生け垣材料としてさかんに植えられました。
果実は偏球形で径5〜6mm,12月から2月頃まで色美しく枝についています。果
実の色が橙(だいだい)色のものをタチバナの実にたとえて,タチバナモドキという名前で呼ぶことがあります。私の家の隣家に植えてあるピラカンサの赤い実にはときどきヒヨドリが来ますが,なかなかなくならず,3月になると黒褐色になって落ちてしまいます。
|
 セイタカアワダチソウの繁殖 セイタカアワダチソウの繁殖
 今年(平成11年)の秋は,例年になくセイタカアワダチソウの黄色の穂波に圧倒された感があります。 今年(平成11年)の秋は,例年になくセイタカアワダチソウの黄色の穂波に圧倒された感があります。
各地の造成地がバブル崩壊の影響を受け,利用されないまま放置されて,雑草の茂るにまかせたため,勢力の強いセイタカアワダチソウの天下になってしまったのでしょう。
セイタカアワダチソウが日本に入ってきたのは明治30年頃と言われていますが,急速にふえだしたのは戦後のことで,今では日本全国どこでも雑草の親分になっています。
秋も深まり花が終わると,“泡立つ”という言葉があてはまるように,冠毛をつけたたくさんの種子ができて白い穂に変わります。やがて,種子は風にのって広がっていきます。
日本の自然の景観は,このような外来雑草の繁殖によって大きく変貌(へんぼう)しているのです。
|
 ガマの穂綿 ガマの穂綿
 ソーセージのような花穂も,冬になると無数の果
実が熟し,穂の端からほどけ,果実の基部にある糸状体が綿のようになって,風にのって飛び散ります。これを「蒲(がま)の穂綿」といって「因幡(いなば)の白兎(しろうさぎ)」の伝説で知られています。 ソーセージのような花穂も,冬になると無数の果
実が熟し,穂の端からほどけ,果実の基部にある糸状体が綿のようになって,風にのって飛び散ります。これを「蒲(がま)の穂綿」といって「因幡(いなば)の白兎(しろうさぎ)」の伝説で知られています。
明治38年に作られた尋常小学唱歌『だいこくさま』の歌詞の2番には,
だいこくさまは あわれがり
「きれいなみずに みをあらい
がまのほわたに くるまれ」と
よくよくおしえて やりました
とあり,さらに3番では,
がまのほわたに くるまれば
うさぎはもとの しろうさぎ
となっています。
このガマの穂綿は,綿のように詰め物に使ったほか,火打ち石による発火の火口(ほぐち)として用いられました。また,花の頃には黄色の花粉がたくさんできます。漢方では,この花粉を集めて蒲黄(ほおう)と称して止血,消炎,利尿の薬として用います。
飛び立ちし 蒲の穂わたの しづまらず
池内たけし
|
 ハンノキ ハンノキ
 ハンノキは,カバノキ科の落葉高木で,水湿地に生えます。幹は高さ15〜20mにもなります。日本では,ハンノキが生えるような水湿地がほとんど水田となっています。そのため,自然のハンノキ林の姿を見ることは少ないのですが,最近は減反のために放棄された水田にハンノキが侵入し,小規模なハンノキ林が形成されている場面
に遭うことがあります。 ハンノキは,カバノキ科の落葉高木で,水湿地に生えます。幹は高さ15〜20mにもなります。日本では,ハンノキが生えるような水湿地がほとんど水田となっています。そのため,自然のハンノキ林の姿を見ることは少ないのですが,最近は減反のために放棄された水田にハンノキが侵入し,小規模なハンノキ林が形成されている場面
に遭うことがあります。
日本の水田は,放棄されるとヨシやカサスゲの群落から,やがてハンノキ林に移行していくのです。
ハンノキの花は2月頃咲きます。花弁や萼(がく)は無く,雄花序は長さ5〜7cmで尾状に垂れ下がり,たくさんの黄色い花粉を飛散します。
雌花序は,雄花序のすぐ下の葉腋(ようえき)につきます。果実はマツカサのような球果
で楕円(だえん)形,長さ1.5〜2.0cmになります。この果実は樹皮とともに煮て,煮汁を染料として用います。
|
 カラスウリの果実 カラスウリの果実
白き蔓(つる) 白き枯れ葉の 烏瓜(からすうり)
後藤夜半
 カラスウリは雌雄異株の植物で,夏の夜に白い花を咲かせます。虫媒花で,花粉の媒介は蛾(が)によって行われます。果
実は熟すと赤く色づきますが,熟しても裂開することはありません。冬が来て蔓も葉も枯れ,葉緑素を失って白っぽくなっても,赤い果
実は,色がすこしあせながらも,短い柄でしっかりと蔓にくっついています。種子は偏平で左右に翼があり,大黒天に似ているところから,財布に入れておくとお金が殖えると言われています。また,結び文に見たてて「玉
梓(たまずさ)」という古名もあります。カラスウリは,昔から根・種子とも漢方薬として用いられ,また果
肉は,「ひび」「あかぎれ」に効用があります。 カラスウリは雌雄異株の植物で,夏の夜に白い花を咲かせます。虫媒花で,花粉の媒介は蛾(が)によって行われます。果
実は熟すと赤く色づきますが,熟しても裂開することはありません。冬が来て蔓も葉も枯れ,葉緑素を失って白っぽくなっても,赤い果
実は,色がすこしあせながらも,短い柄でしっかりと蔓にくっついています。種子は偏平で左右に翼があり,大黒天に似ているところから,財布に入れておくとお金が殖えると言われています。また,結び文に見たてて「玉
梓(たまずさ)」という古名もあります。カラスウリは,昔から根・種子とも漢方薬として用いられ,また果
肉は,「ひび」「あかぎれ」に効用があります。
|

 ピラカンサ
ピラカンサ
 ハンノキ
ハンノキ
