〔1〕 環境教育の教材として
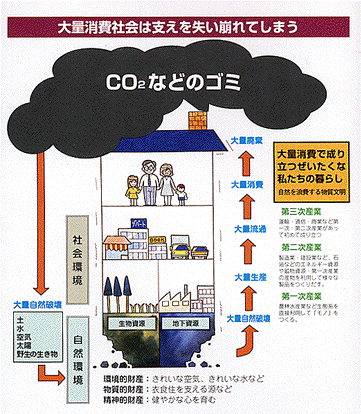
持続不可能な現代社会
環境問題は、個別に取りざたされるケースが多いが、環境教育を進める上ではそれぞれの環境問題に共通
する原因を把握することが求められる。現在起きている環境問題の原因は主として大きく2つに集約される。
●直接自然を破壊することで起こる「野生生物が絶滅する問題」。 ●現代社会が大量に排出したさまざまな物質が原因となって引き起こされる この2つに大別された問題は、直接的、間接的の違いはあるが、最終的には水、大気、土、太陽光、そして多様な種類の野生生物から構成される自然生態系を破壊しているのである。
私たちは、現代のさまざまな環境問題を引き起こす持続不可能な社会を改めるために、まず生存基盤ともいうべき自然生態系を正しく認識することが求められる。その効果
的な教材のひとつが学校ビオトープと言える。
1980年代から、ドイツでは環境教育を効果的に進める教材として、学校ビオトープが急激に導入されてきた。これは、1970年代に、世界各国が自然生態系を守ることを環境問題解決のための最優先目標に掲げたことを受けている。
例えば…
◯住宅地や農地をつくるための森林伐採。
◯セイタカアワダチソウ(北米原産)など外国の動植物が国内に移入したことで
引き起こされる、地域の野生の生きものの絶滅。
(⇒求められる行動:自然を守り育てること)
「ゴミの問題」。
例えば…
◯大量にものを生産することで排出されるCO2というゴミが引き起こす地球温暖
化問題。
◯大量の廃棄物を処理する過程で排出されたダイオキシンが引き起こす環境ホル
モンの問題。
(⇒求められる行動:質素な生活への転換)
| コラム
野生の生きものがくらしていくには、餌(えさ)や住みか、産卵場など、さまざまな条件が整っている必要がある。その条件のどれかひとつが欠けても、野生の生きものは生きてはいけない。例えば、ミドリシジミというチョウの幼虫は、ハンノキの葉だけを食べる。つまり、そこにハンノキがなければ、それ以外のみどりがいくらあっても、ミドリシジミはくらしていけない。 ↑写真左上 メキシコ原産であるコスモスを植えても…。
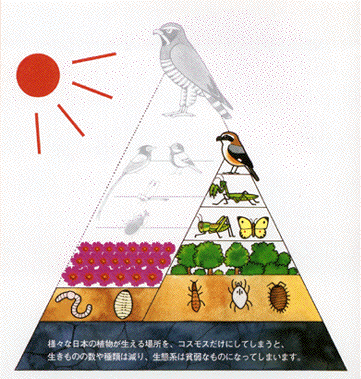 壊されてしまう自然生態系ピラミッド |
次へ
Copyright(C)2000 KYOIKU SHUPPAN CO.,LTD. All Rights Reserved.
 学校などでこれまで行われてきた緑化活動は、見た目の美しさを重視し、外国の植物や園芸種を使用してきた。しかし、これらは日本の草食性昆虫にとっては、ほとんど利用することのできない植物である。草食性昆虫がいなければ、トンボやクモ、さらに野鳥など肉食性の生きものもそこではくらしていけない。
学校などでこれまで行われてきた緑化活動は、見た目の美しさを重視し、外国の植物や園芸種を使用してきた。しかし、これらは日本の草食性昆虫にとっては、ほとんど利用することのできない植物である。草食性昆虫がいなければ、トンボやクモ、さらに野鳥など肉食性の生きものもそこではくらしていけない。