
上野動物園
菅谷 博 園長 インタビュー
上野動物園は,日本初の動物園として1882年に開園しました。1972年には中国からジャイアントパンダが来園し全国的に話題となったことでもよく知られています。 多くの人が訪れる人気の動物園について,菅谷 園長にお話を伺いました。
(聞き手:編集部 岡本)
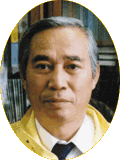

開園120年目
──初めに,日本初の動物園として上野動物園が果たしてきた役割について,お考えをお聞かせください。
菅谷園長 (以下,菅谷)「明治15年3月20日に開園しまして,今年で120回目の誕生日を迎えるわけですけれども,江戸の香りが色濃く残る時代に,動物園をつくったという意義は大きいと思います。江戸時代においてもクジャクを見せたり珍奇な動物を集めた茶屋制度というものはありましたけど,それが発展して動物園ができたのではなく,欧米を視察して,動物園を文化としてとらえて,貴族から庶民まで楽しめるものとして位
置づけられたのがよかったのではないでしょうか。戦前は動物園が数えるほどしかなかったんですが,苦しい状況の中で海外からいろいろな動物を集める努力をして,動物園文化を広く一般
に見せてきたということの役割は大きいと思います。」
──戦前は動物園の数が限られていたということですが,いつ頃から全国に動物園が広まったのですか?
菅谷 「昭和26年頃から日本各地に動物園ができてきました。動物園の黄金期というものです。“ZOO
IS PEACE”といわれるように,動物園には平和のシンボルとしての役割もあります。過酷な第2次世界大戦が終わって国民がほっとして,そこで自治体が何をしようかと考えたときに,“動物園=平和のシンボル”という発想で,苦しい状況の中にもかかわらず,動物園が増えてきたんだと思います。」
現在の動物園
──現在における動物園の意義という点についてはどのようにお考えですか?
菅谷 「動物園には,実際に生きた動物をご覧になって楽しんでいただくというレジャー的な要素がありますね。それとともに,まさに21世紀は環境の時代といわれ,野生下の動物がどんどん減っていく現状に対して,種の保存という大きな柱があります。それと調査・研究,これはフィールドを取り込んだ中でやっていかなければなりません。あとは環境教育,この4つの柱があります。
絶滅の危機にある動物の多い中,種の保存は絶対に取り組んでいかなければなりません。環境教育については,まだまだ微力ですが,展示を通
して,自然と調和のとれた社会づくり,日常生活における自然への配慮,そしてグローバルな地球環境の保全を啓発していきたいと思っています。
学校では『総合的な学習の時間』など新しい授業が行われますが,動物園の中でできることのほかに,外にはたらきかけることを考えていきたいですね。例えば,多摩動物園では,国語の教科書に出てくる動物について,
学校の先生方に対してお話しする機会をもっ ています。これまでも学校などの教育機関を
中心に対してはいろいろな取り組みを行って きましたが,これからも研究を続けていかな
ければならないと思っています。」
ズーストック計画
──東京都で取り組まれているズーストック計画についてお聞かせください。
菅谷 「ズーストック計画は,いまから11
年前に東京都の長期計画で立ち上げられまして,“動物園や水族園で展示する動物は,野生から捕ってくるのではなく,自分たちで繁殖させ,それを皆に見せる”という趣旨のもとに行われている取り組みです。これは,近交係数が高くならないように,日本中の動物園や,さらには世界の動物園と連携していくことが大切になります。」
──近交係数というのは何ですか?
菅谷 「近交係数が高くなるというのは,血が
濃くなるということです。基本的には近交係数が高くなるのはよくないことで,1つの動
物園内だけで交配を続けるとどんどん血が濃 くなってしまいますから,ほかの動物園の動物と交配させるんです。ユキヒョウなどはも
う日本国内だけではだめで,モンゴルなどの 動物園とお互いに交換しています。動物園は,まさに国際化の中にあって,海外と友好関係
を結んで動物の交換や貸し借りを頻繁にして いるんです。」
動物園と教育
──『総合的な学習の時間』が本格的に導入されるのは今年の4月からですが,
動物園が教育に果たす役割というものについ てはどうお考えですか?
菅谷 「その点に関しては,学校の先生方にお願いがございまして,例えば生命尊重について教えたい場合,動物園に来る前に学校で飼っている動物をもっと活用してもらいたいんです。学校では子どもの情操教育や理科の教
材としてウサギやニワトリを飼っていると聞きます。まずは身近な飼育動物を通
して生命 の大切さを感じとることから始めてもらいたいですね。」
──おっしゃるように,身近なところにも教育のヒントはたくさんありますね。
菅谷 「現代は,豊かな食生活が享受できる一
方,『いただきます』や『ごちそうさま』の言えない子どもも育っています。明治から少なくとも戦前まであった家族を中心にした倫理
観も,いまは自由の名のもとに崩れ去り,人 間関係が希薄になっています。そういう時代だからこそ,動物園で動物を
見て,原点を見てほしいと思います。」
──たしかに,現代では人間関係を面倒だと感じてしまう人が多くなっているのかも
しれませんね。
菅谷 「子ども動物園は,非常に人気があるんですよ。モルモットやウサギを抱っこするのに長い行列をつくっています。小さい頃から
動物に接することは,命を実感できますし,人間社会で親兄弟や友達を大切にする心にも
つながるのでしょう。
ときどき乳房の形が悪くなるから母乳を与えない母親や,子どもを抱かない父親がいるとの声を耳にします。稀な例かもしれませんが,大変気になります。幼児期はスキンシップが大切です。1
日に1回でいいから子どもを強く抱いてほしいですね。動物は1日じゅう子どもを抱いていて,絶対に放しません。
動物園で動物を見たときに,ただ単に可愛いと思うだけではなく,自分の生活なり親子関係なりを見つめる余裕をもってほしいんです。動物園としては,解説の中でそのことを気づかせていきたいと考えています。」
──先生のお話を伺って,動物園は,世界の動物を見て楽しむだけでなく,人間と自然とのかかわりや人間本来の在り方を見つめ直す
場にもなるんだと感じました。今回は,どうも有り難うございました。■
Copyright(C)2002
KYOIKU SHUPPAN CO.,LTD. All Rights Reserved.