
よこはま動物園
ズーラシア
増井 光子 園長 インタビュー
よこはま動物園ズーラシアは,野生動物がすむ環境を再現しているのが特徴の動物園で,日本最大級の規模で1999年に開園しました。今回は,園長の 増井 光子 先生に,この21世紀型の新しい動物園について,いろいろとお話を伺いました。
(聞き手:編集部 岡本)


──初めに,動物園がどう変わってきて,どういう役割をもってズーラシアができたのかという点でお話をお願いします。
増井園長(以下,増井)「近代動物園というスタイルをとるようになってから,今年で250年になります。その間に,動物園は,日本でいえば上野動物園に代表されるような都市型の方式から,サファリパークのような方式や多摩動物公園やズーラシアのような生態学的な展示方式へと変わってきたんですね。これはすべて,その時代の一般
の人の考え方に沿って変わってきたんです。
まわりに自然がいっぱいある頃は,動物より人間が大事で,たくさんの人が珍しい動物を見て知的好奇心を満足させていたんです。それが,だんだん人間の暮らしが便利になる一方で自然は減り,動物行動学などの研究が一般
の人にも知られるようになると,動物園で動物があまりいい状況におかれていないことへの批判が高まってきました。
動物園は,地球環境を守ることの重要性を理解してもらうための,非常によい情報発信の場になります。動物園に来た人たちに,きちんとした情報を提供できれば,環境教育の効果
が非常に上がると考えられるわけです。
動物園というのは,地球上に人間以外にもたくさんの動物や植物がいて,それらが密接にかかわり合っているということを体験してもらう場所だと思います。」
──動物を見て楽しんでいたものが,時代とともに,動物の背景にある地球環境のほうに人間の目が向いてきたんですか。
増井「そうですね。最初,自然は無限にあって,いくら利用してもなくならないと錯覚していたと思います。ところが,実際は自然には限りがあるんだということがわかってきて,その上,自分たちが便利になるために作り出した様々な物が環境に悪影響を及ぼすことがわかってくると,さすがにこれはいけないと気づく人が増えてきました。それに生態学的な知識が入ってくると,人間だけのことを考えていたのではうまくいかないとみんなが思うようになってきたわけですね。」
──ズーラシアができてきたのも,そういった時代背景があったんですね。
 増井「そうです。狭いおりの中に動物がいるだけじゃ,見てもあまり楽しくないわけですね,なんか可哀想な気持ちが起こったり。そうなると,動物園側としても,動物福祉や展示法の改善に努力することになります。
増井「そうです。狭いおりの中に動物がいるだけじゃ,見てもあまり楽しくないわけですね,なんか可哀想な気持ちが起こったり。そうなると,動物園側としても,動物福祉や展示法の改善に努力することになります。
しかし,どうも私の見るところ,動物は,あまり広い狭いは関係ないようです。要するに,彼らにとってみれば,毎日食べ物が確保できるところがいちばん望ましいんです。例えば,食べ物が乏しいところのクマは,広い範囲を歩きまわらなければ生きていけません。ところが,食べ物がたくさんあるところのクマは,行動範囲が狭くてもいいんですよ。動物園にいる動物は,どこに食べ物があるかを知っていて,広い場所を提供しても,食べ物のそばを動かないんです。どうやって楽して食べ物を手に入れるかを考えるという点では,人間と同じですね。」
──ズーラシアのような方式は,日本では初めてと伺いましたが。
増井「動物舎の中まで植物を一緒に植え込んでいるというのは初めてです。園路に装飾的に花壇をつくったり緑化したりするのは以前からやられていますが,そうではなくて,東南アジアの動物のコーナーには動物舎に東南アジアを原産とする植物を植えよう,亜寒帯の森には寒い地方の植物をメインにしよう,とエリアごとに全部植物をかえています。植物も順化(=適応)しないと枯れてしまいます。暑いところの植物は寒さに弱いし,寒いところの植物は暑さに弱いので,ズーラシアがオープンする十数年前から植物を植えて定着させてきました。」
──ズーラシアでは,生息環境を再現しているのが大きな特徴ということですね。
 増井「動物園は,もう飼育係と獣医師がいればいいという時代ではないんですね。植物の専門家や,ギフトショップの商品やディスプレイのコーディネートをする人,それからいろんな教育プログラムをつくる人,デザイン関係・美術関係の人などが,ますます必要になってくると思います。いままでは何となく動物に餌をやって,排泄したものを掃除して,病気になれば獣医師が治療して,それで動物園だという感じだったんですが,これからはそれではとても運営できないと思います。
増井「動物園は,もう飼育係と獣医師がいればいいという時代ではないんですね。植物の専門家や,ギフトショップの商品やディスプレイのコーディネートをする人,それからいろんな教育プログラムをつくる人,デザイン関係・美術関係の人などが,ますます必要になってくると思います。いままでは何となく動物に餌をやって,排泄したものを掃除して,病気になれば獣医師が治療して,それで動物園だという感じだったんですが,これからはそれではとても運営できないと思います。
ゲストあっての動物園ですから,動物がなるべくゲストの前に来るようにいろいろ工夫するんですよ。例えば,トラのところは34ミリの強化ガラスがあって,そのガラスを隔てて向こうにトラがいるんです。ゲストが顔を近づけると,トラと人間との距離はわずか十数センチ,すごい迫力でしょ。で,なんでそこにトラがいるかっていうと,ガラスの前に人工の岩が置いてあって,中にヒーターが入っていてあったかいんです。だから冬はその上にいつも乗っかっている。」
──来園者が満足するために,いろいろ工夫されているんですね。
増井「実は,うちの動物園は繁殖率がいいんですよ。ほかの動物園ではなかなか産まれない動物が毎年のように産まれるので,飼い方がそんなに違わないのに何が違うのだろうかと考えたところ,やはり植物の効果
があるんじゃないかと思うんです。
森林浴すると健康にいいとか気持ちがやわらぐとか,いまアロマテラピーがブームとなっています。植物がもっている精油には,妊娠中は使ってはいけないとか,ホルモンのバランスを整えるのに効果
があるとか,いくつも種類があります。それらが自然界の動物に影響を与えてないわけがないと思うんですよ。
ここにくらす動物たちは,まわりに植物が多いから,においを嗅いだり,ときには遊んで枝などを噛んだりするときに,精油を取り入れることになり,その結果
,繁殖率がよくなっているのではないかと考えています。」
──教育に関する取り組みについて,少しお聞かせください。
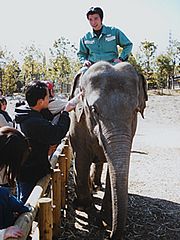 増井「世界中から本物の動物が来ている“動物園”という施設を校外授業でもっと活用してもらいたいですね。私たちは,動物園に来た学校の先生向けのテキストをいろいろ作っています。また,解説員によるツアーや飼育担当によるスポットガイド,講演会など様々な取り組みを行っています。こういうことをしてほしいという要望を動物園側に言っていただければ双方が話し合って,さらに教育に効果
的なものを探っていけると思います。」
増井「世界中から本物の動物が来ている“動物園”という施設を校外授業でもっと活用してもらいたいですね。私たちは,動物園に来た学校の先生向けのテキストをいろいろ作っています。また,解説員によるツアーや飼育担当によるスポットガイド,講演会など様々な取り組みを行っています。こういうことをしてほしいという要望を動物園側に言っていただければ双方が話し合って,さらに教育に効果
的なものを探っていけると思います。」
──今回は,いろいろと楽しい話を有り難うございました。■
Copyright(C)2002
KYOIKU SHUPPAN CO.,LTD. All Rights Reserved.