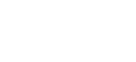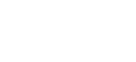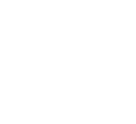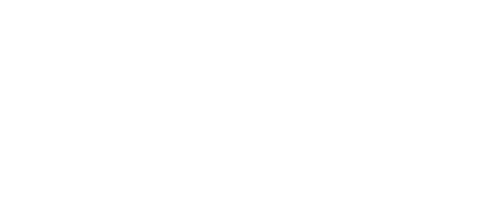

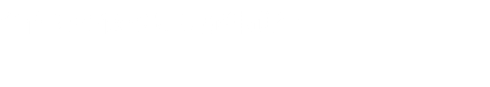
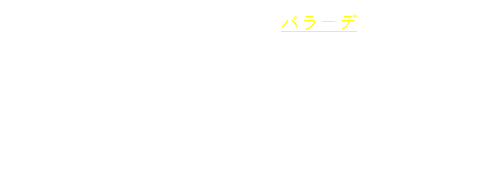
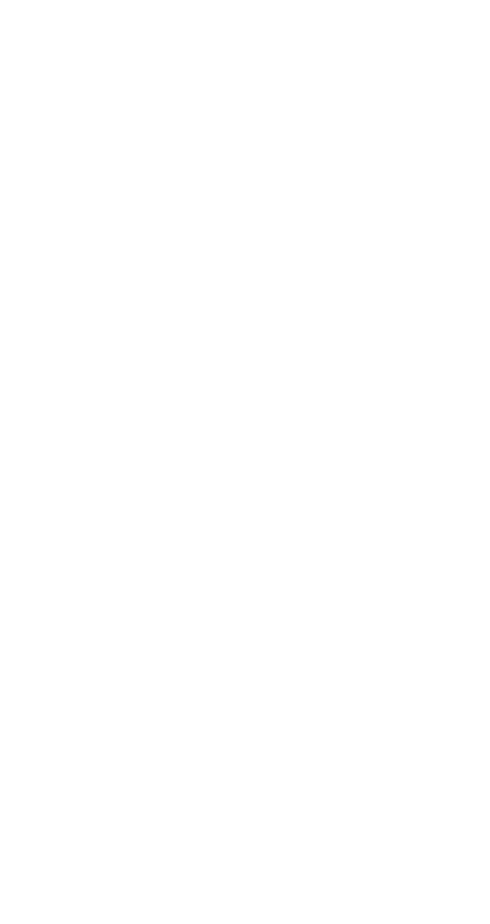
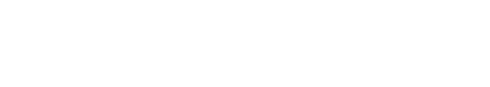
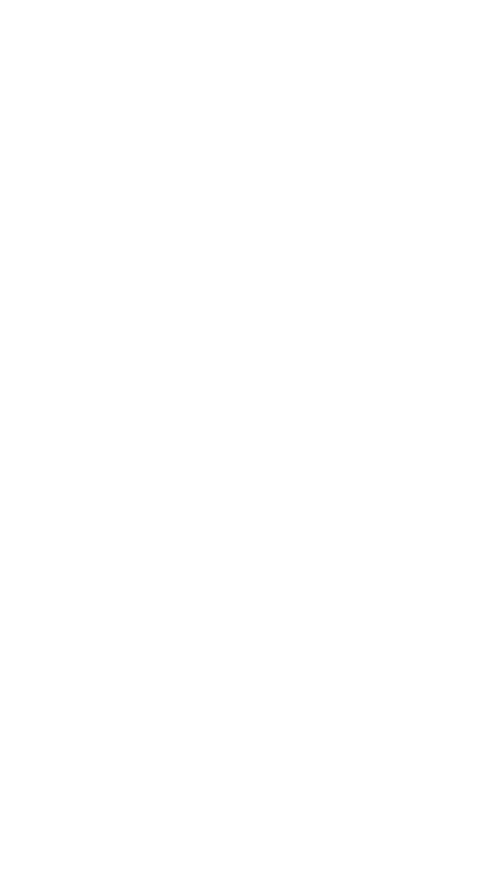
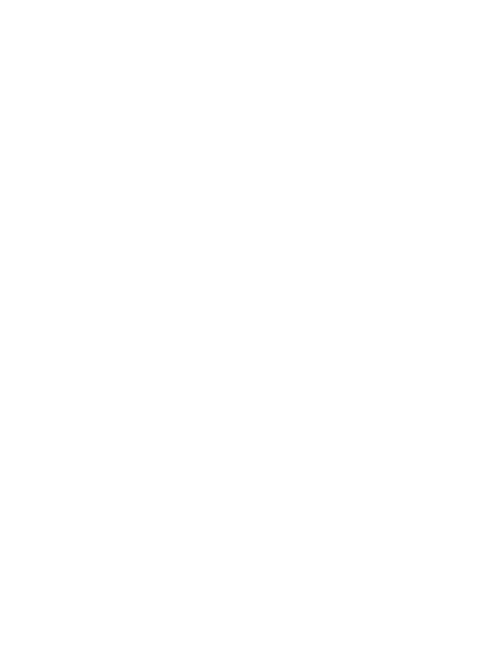
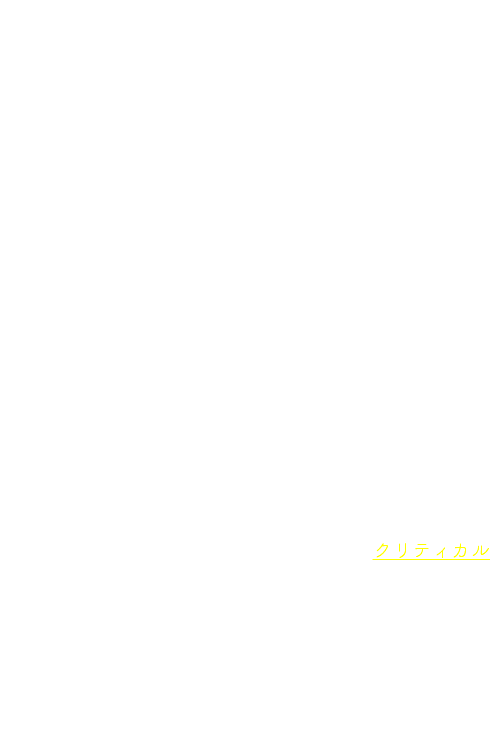
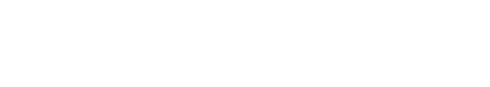
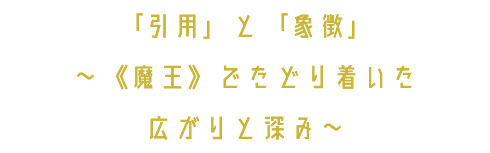
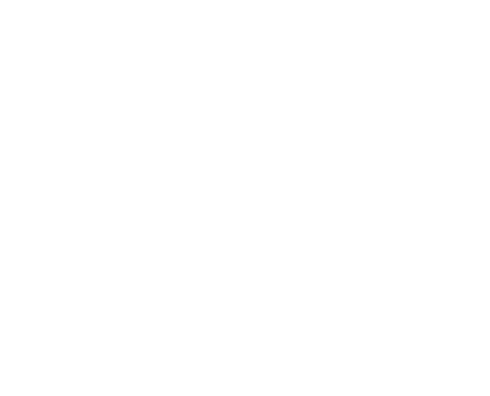
譜例2 J.ライヒャルト作曲
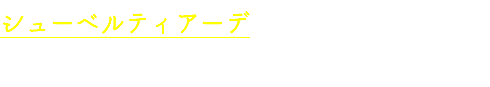
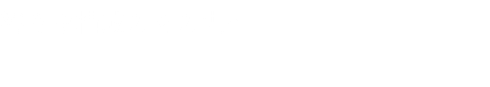
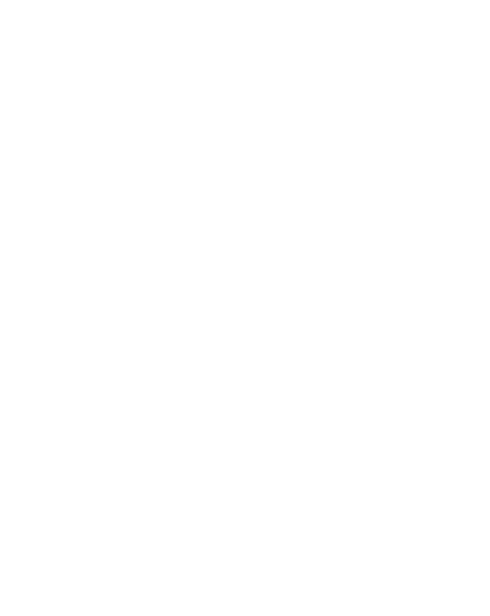
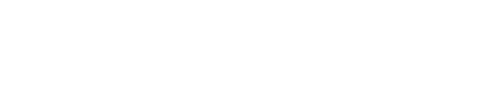
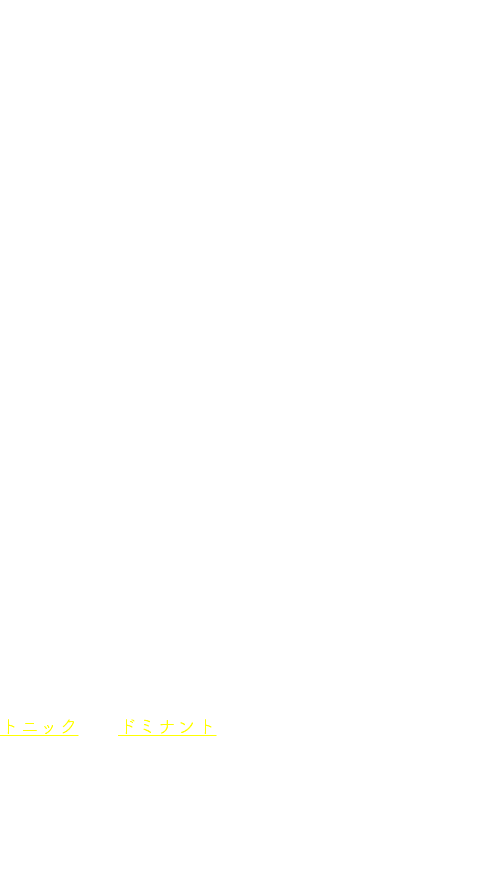
譜例4 魔王の旋律の各出だし ※比較のため同一の調号で記譜しています。
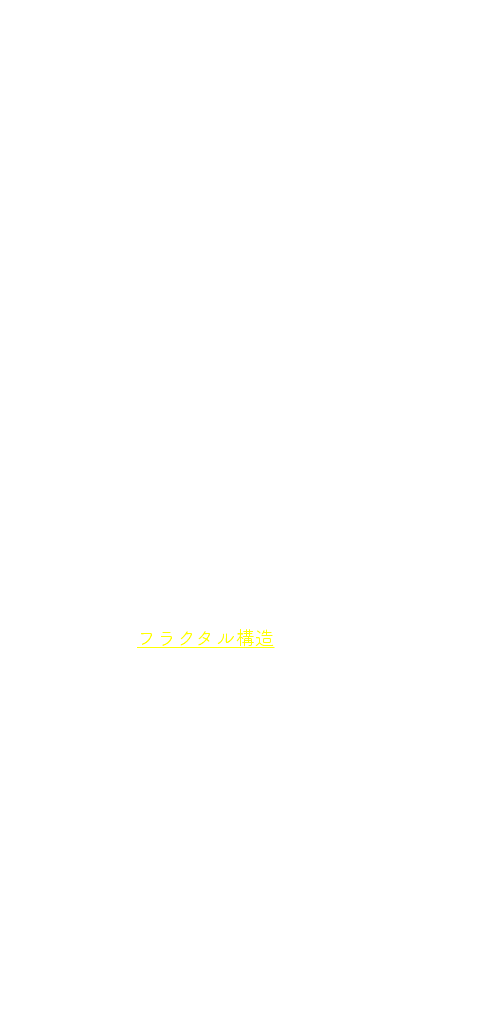
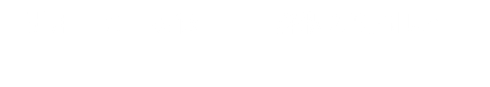
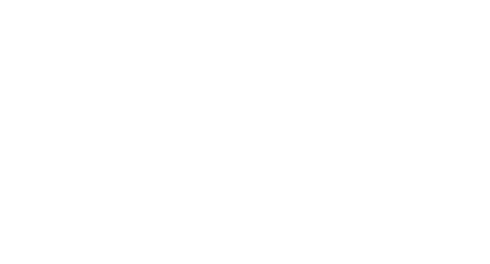
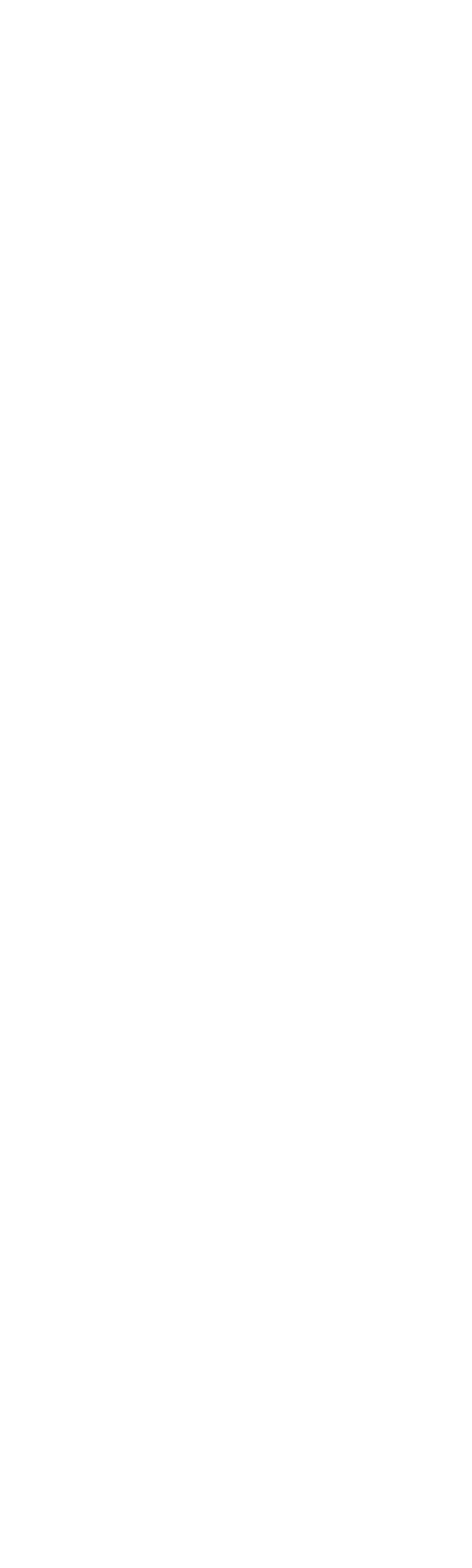
譜例3 C.レーヴェ作曲
変ロ長調
変ホ長調
ハ長調
譜例5
譜例6 曲頭の左手の音型
譜例1


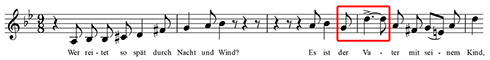
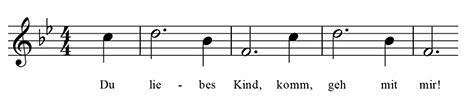
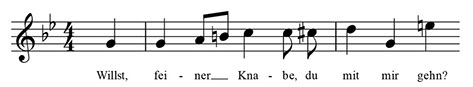

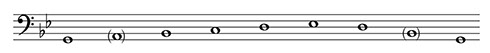

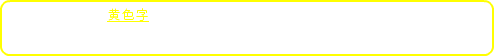
《 目次 》
クリティカル
危機的で深刻に感じられる,という意味。
ドミナント
属音。
フラクタル構造
自己相似形。自然界で見出せる形(図形)で,大きさは違っても同じ形をしている場合があり,それ自体の中に相似の図形が含まれているもののこと。ここでは《魔王》全体での主音を結んでできる形と,その部分としてのこの左手音型を指す。
バラーデ
バラード。物語歌。
トニック
主音。
シューベルティアーデ
シューベルトが友人たちとウィーン各所のサロンなどで開催した集い。