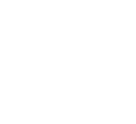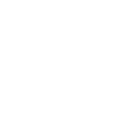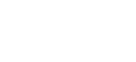注
1)譜例の第3小節冒頭の和音。その響きが何調の響きなのかわからなくなる、独特の不思議な印象の和音。その調の構成音でない音(非和声音)を多く用いることで、その調の性格がぼかされることによる。
2)『[決定版]ベートーヴェン〈不滅の恋人〉の探求』青木やよひ著、平凡社、2007。
及び『シューマン 愛と苦悩の生涯』若林健吉著、ふみくら書房、2013(復刻版)。
3)『饗宴』プラトーン著、森進一訳、新潮社、1968、p125。
4)『星の王子さま』サン=テグジュペリ著、河野万里子訳、新潮社、2006、p108。