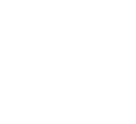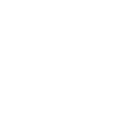注
1)『ファウスト』第一部、ゲーテ著、相良守峯訳、岩波書店、1958年、p303f.
2)CDやwebなどでアンブロシウス聖歌を視聴することができます。
例えば、下記はナクソス・ミュージック・ライブラリーに公開されている音源です。
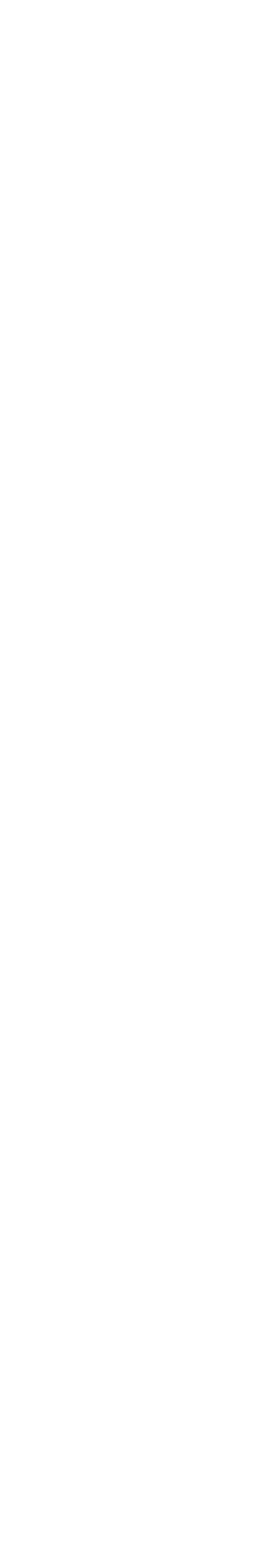
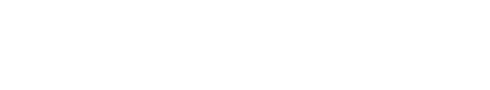
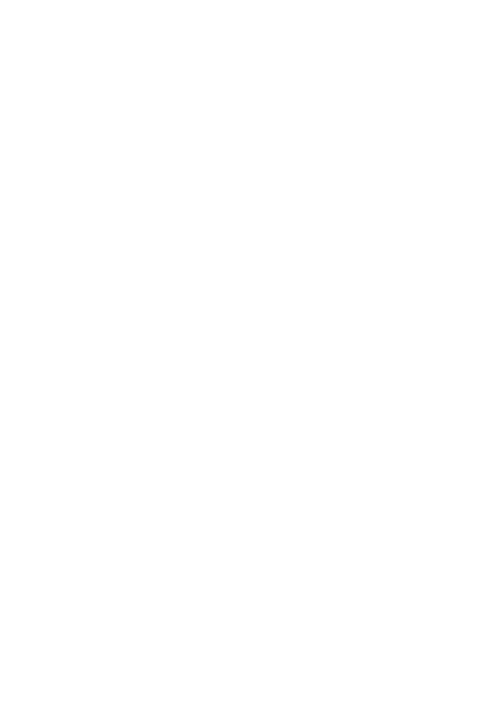
![宗教曲からの引用として最も有名なものと言えば、ベルリオーズ(1803~1869)の『幻想交響曲』作品14でのグレゴリオ聖歌からの引用でしょうか。『幻想交響曲』は作曲者自身の恋愛体験に基づいて書かれました。イギリスからパリにやってきた劇団の女優に恋をするという、かなり苦しい体験でした(最終的には結ばれるのですが)。曲は5楽章から成り、各楽章に標題が付けられています。ストーリーとしては、主人公が恋に落ち、やがて悪夢を見る。その中で彼は彼女を殺し、断頭台で処刑され、自分の葬儀が魔女たちの狂宴の中で行なわれる、というもの。「固定楽想」と呼ばれる、恋人を表わす旋律が、変形されつつ全曲中の随所に現れるのが特徴です。 さてこの曲の第5楽章は「魔女の饗宴の夜の夢」と題され、悪夢の中で主人公の葬儀が行なわれています。ただし饗宴といっても、前回も触れたプラトンの『饗宴』での、酒宴もそっちのけで美と愛に向かった格調高い議論などでは全くなく、その正反対の不気味でグロテスクな宴です。この楽章は「ワルプルギスの夜の夢」としても知られています。 ところでこの魔女たちの醜悪な集会の模様が、ゲーテの戯曲『ファウスト』第1部でも、同じ「ワルプルギスの夜の夢」という名の部分で描かれています。悪魔のメフィストフェレスが、戯曲の主人公たるファウストを堕落させるため、彼を誘惑して、ドイツ中央部にあるブロッケン山で行なわれている魔女たちの不気味な夜会に連れて行きます。この夜会は現在も「ワルプルギスの夜」という名で実際に行事として行なわれています。さて、ゲーテ『ファウスト』中の、この夜会で行われていた素人芝居のセリフの一箇所を記せばこんな具合。 [若い魔女] 髪粉つけて着物をきるのは、 白髪の婆さんだけの話よ、 わたしゃ裸の牡山羊に乗って、 このいいからだを見せるのさ。 [老貴婦人] 私たちはたしなみがいいから、 あんた方と啀み合いはせぬが、 あんた方、その若くてすんなりとした からだのまま腐ってしまえばいい。 [楽長] 蠅のくちはし、蚊の鼻の先、 裸の女にたかっちゃだめだよ。 葉末の蛙に草葉のこおろぎ、 歌の拍子をはずすなよ。 [風信旗(一方に向いて)] 願ってもない粒ぞろいですな。 ほんとに立派な花嫁ばかりだ。 また青年諸君もそれぞれに、 末頼もしい方ですな。 [風信旗(他方に向いて)] もしこれで大地が口をあけて、 あいつらをみな呑んでしまわなけりゃ、 この私がさっさと駆けだして、 まっすぐ地獄へ飛び込みまさあ。*1](images/u7562-70.png?crc=3796011464)
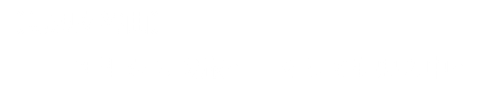


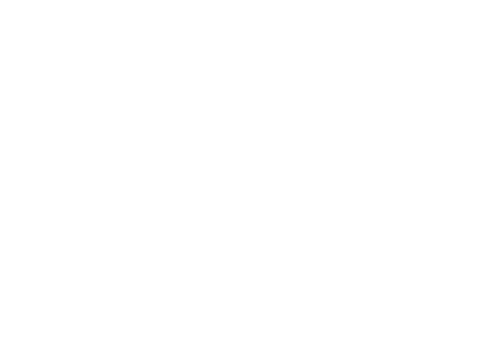
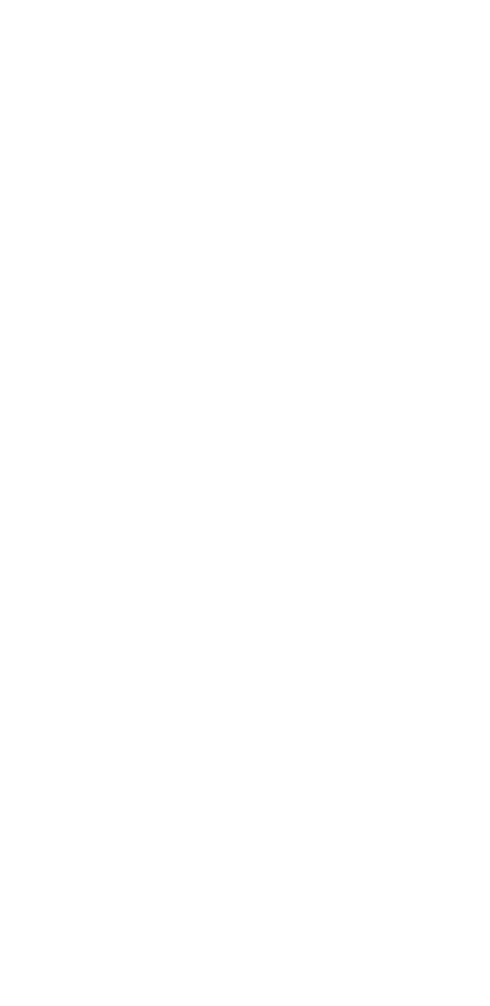

譜例1

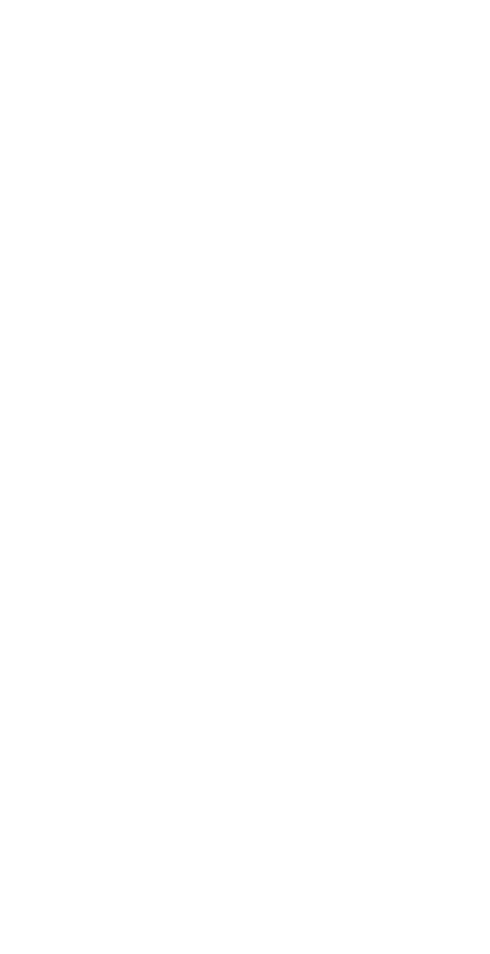
譜例2

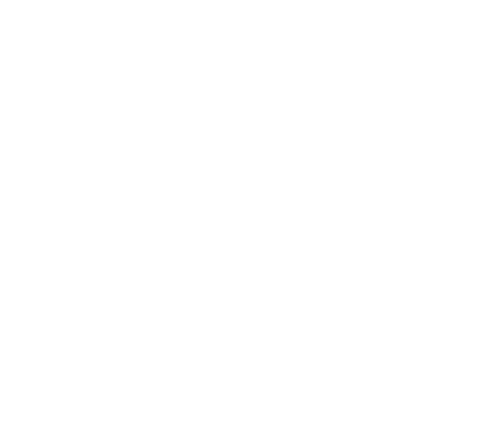
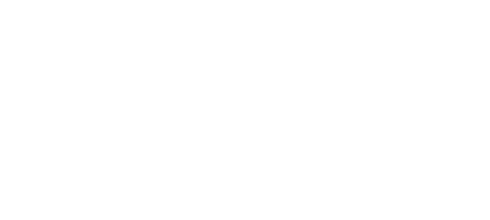
譜例3



注
1)『ファウスト』第一部、ゲーテ著、相良守峯訳、岩波書店、1958年、p303f.
2)CDやwebなどでアンブロシウス聖歌を視聴することができます。
例えば、下記はナクソス・ミュージック・ライブラリーに公開されている音源です。
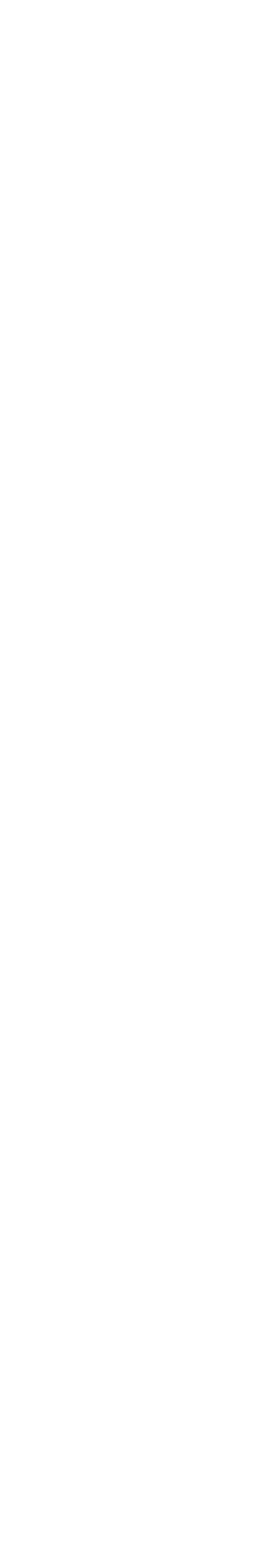
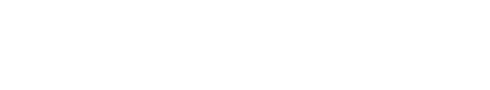
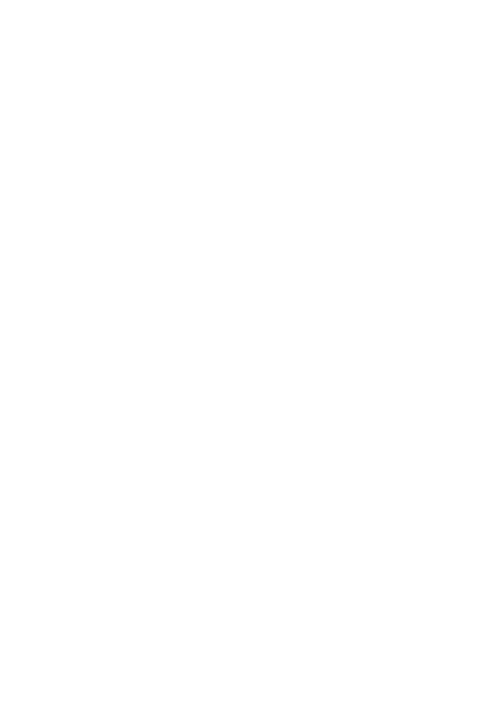
![宗教曲からの引用として最も有名なものと言えば、ベルリオーズ(1803~1869)の『幻想交響曲』作品14でのグレゴリオ聖歌からの引用でしょうか。『幻想交響曲』は作曲者自身の恋愛体験に基づいて書かれました。イギリスからパリにやってきた劇団の女優に恋をするという、かなり苦しい体験でした(最終的には結ばれるのですが)。曲は5楽章から成り、各楽章に標題が付けられています。ストーリーとしては、主人公が恋に落ち、やがて悪夢を見る。その中で彼は彼女を殺し、断頭台で処刑され、自分の葬儀が魔女たちの狂宴の中で行なわれる、というもの。「固定楽想」と呼ばれる、恋人を表わす旋律が、変形されつつ全曲中の随所に現れるのが特徴です。 さてこの曲の第5楽章は「魔女の饗宴の夜の夢」と題され、悪夢の中で主人公の葬儀が行なわれています。ただし饗宴といっても、前回も触れたプラトンの『饗宴』での、酒宴もそっちのけで美と愛に向かった格調高い議論などでは全くなく、その正反対の不気味でグロテスクな宴です。この楽章は「ワルプルギスの夜の夢」としても知られています。 ところでこの魔女たちの醜悪な集会の模様が、ゲーテの戯曲『ファウスト』第1部でも、同じ「ワルプルギスの夜の夢」という名の部分で描かれています。悪魔のメフィストフェレスが、戯曲の主人公たるファウストを堕落させるため、彼を誘惑して、ドイツ中央部にあるブロッケン山で行なわれている魔女たちの不気味な夜会に連れて行きます。この夜会は現在も「ワルプルギスの夜」という名で実際に行事として行なわれています。さて、ゲーテ『ファウスト』中の、この夜会で行われていた素人芝居のセリフの一箇所を記せばこんな具合。 [若い魔女] 髪粉つけて着物をきるのは、 白髪の婆さんだけの話よ、 わたしゃ裸の牡山羊に乗って、 このいいからだを見せるのさ。 [老貴婦人] 私たちはたしなみがいいから、 あんた方と啀み合いはせぬが、 あんた方、その若くてすんなりとした からだのまま腐ってしまえばいい。 [楽長] 蠅のくちはし、蚊の鼻の先、 裸の女にたかっちゃだめだよ。 葉末の蛙に草葉のこおろぎ、 歌の拍子をはずすなよ。 [風信旗(一方に向いて)] 願ってもない粒ぞろいですな。 ほんとに立派な花嫁ばかりだ。 また青年諸君もそれぞれに、 末頼もしい方ですな。 [風信旗(他方に向いて)] もしこれで大地が口をあけて、 あいつらをみな呑んでしまわなけりゃ、 この私がさっさと駆けだして、 まっすぐ地獄へ飛び込みまさあ。*1](images/u7562-70.png?crc=3796011464)
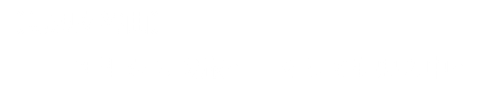


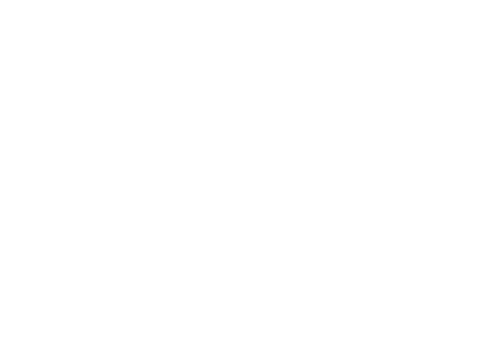
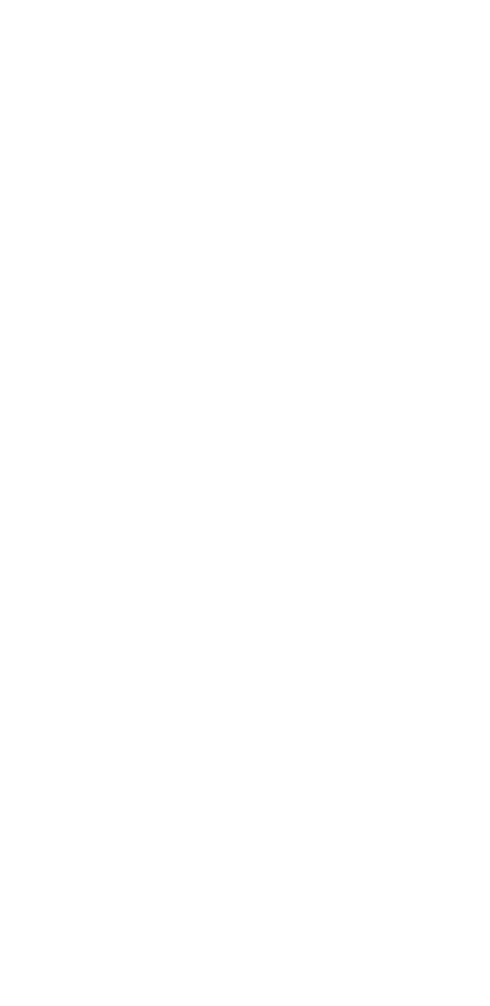

譜例1

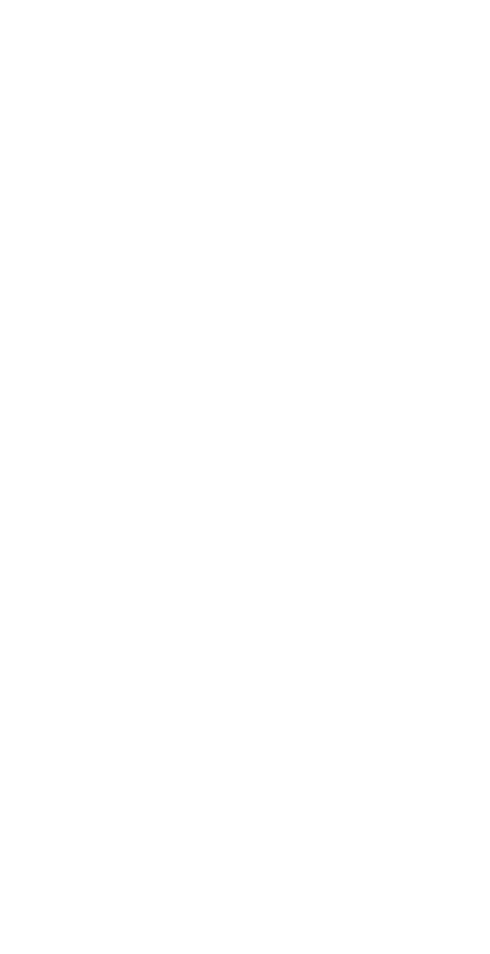
譜例2

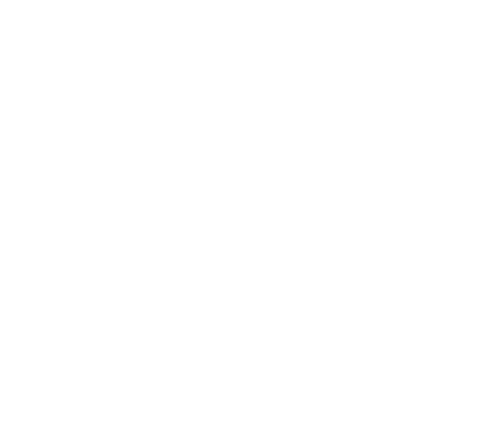
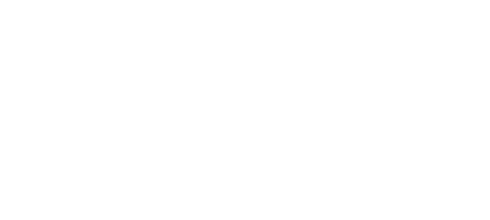
譜例3