
立命館小学校
教頭 荒木 貴之 先生
インタビュー(3)
立命館小学校は,2006年に京都市北区に開校した新しい小学校で,国際社会で活躍する次世代のリーダーを育成することを念頭において,京都市伏見区にある立命館中学校・高等学校と12年間一貫教育に取り組んでいます。
今回は,立命館小学校で新しく「ロボティクス科」を立ち上げ,ロボット教育で「サイエンスを重視したものづくり体験学習」を追究されている,教頭の荒木貴之先生にお話を伺いました。
(聞き手:編集部 岡本)

■大人全体で将来の人材育成を■
── これまで,具体的な内容にふれながら,ロボットを通
して子どもをどのように育てていくかというお話を伺ってきましたが,CSKホールディングスやレゴジャパンやなど,ロボティクス科は,企業との連携で成り立っている部分が大きいと思います。そこで,いまの学校教育が抱えている課題とも関連してくるかもしれませんが,企業と連携した教育の価値について,お考えをお聞かせください。
荒木貴之先生  (以下,荒木)「学校の学びが実際の社会に出てからの生活に結びついてないという指摘を受けた時期があり,それが少しずつ改善され,学校を開く流れができました。学校では,外部評価を取り入れたり,ゲスト・ティーチャーを招いたり,いろいろしてきましたが,それでも十分でないように感じるのは,教員が“知識の一方的な伝達者”という殻をなかなか破れなかったことに一因があると思います。教員は,授業の専門性は必要になりますが,所詮,専門家ではありません。ただし,学習の道筋をつけたり,子どもたちをよい方向に支援したり,学びのコーディネートをすることは教師の力としてできるわけです。一方,動機づけの場面
や最先端の科学的な内容を説明する場面では,子どもたちが専門家の方々と直接ふれて直に学んでいくほうが,より教育効果
が高い場面も多いのです。そこで,大学の研究者の方をお招きしたり,企業の方を派遣していただいたり,カリキュラムづくりの段階で企業の方々の助言をいただいたりすることにしました。授業をつくるうえで,人やモノをプロデュースして,最大の教育効果
を上げればよいのです。ロボティクス科は,教員一人で行うことはできません。教師と子どもの関係を考えると,教師は子どもにとって身近な大人のモデルなんです。教師が様々なかたちで課題解決をしていく,多様な人と連携してよりよいものをつくっていく,そういった授業を展開していく教師の姿を見せることは,おそらく子どもたちにとってプラスになるだろうと思います。ですから,教師が積極的に外に出ていって,そこで得られたものを子どもたちに還元することは,今後ますます推進されるべきだと考えています。」
(以下,荒木)「学校の学びが実際の社会に出てからの生活に結びついてないという指摘を受けた時期があり,それが少しずつ改善され,学校を開く流れができました。学校では,外部評価を取り入れたり,ゲスト・ティーチャーを招いたり,いろいろしてきましたが,それでも十分でないように感じるのは,教員が“知識の一方的な伝達者”という殻をなかなか破れなかったことに一因があると思います。教員は,授業の専門性は必要になりますが,所詮,専門家ではありません。ただし,学習の道筋をつけたり,子どもたちをよい方向に支援したり,学びのコーディネートをすることは教師の力としてできるわけです。一方,動機づけの場面
や最先端の科学的な内容を説明する場面では,子どもたちが専門家の方々と直接ふれて直に学んでいくほうが,より教育効果
が高い場面も多いのです。そこで,大学の研究者の方をお招きしたり,企業の方を派遣していただいたり,カリキュラムづくりの段階で企業の方々の助言をいただいたりすることにしました。授業をつくるうえで,人やモノをプロデュースして,最大の教育効果
を上げればよいのです。ロボティクス科は,教員一人で行うことはできません。教師と子どもの関係を考えると,教師は子どもにとって身近な大人のモデルなんです。教師が様々なかたちで課題解決をしていく,多様な人と連携してよりよいものをつくっていく,そういった授業を展開していく教師の姿を見せることは,おそらく子どもたちにとってプラスになるだろうと思います。ですから,教師が積極的に外に出ていって,そこで得られたものを子どもたちに還元することは,今後ますます推進されるべきだと考えています。」
── 教師は,子どもが接する数少ない大人の一人でしょうから,そこで,一般
社会の大人が行っているいろいろな立場の人たちと接する活動を教師が自ら行い,子どもたちに見せていくのはとても価値のあることだと思います。
いまのお話は,学校側にとっての企業と連携する価値ですが,企業側にとってのメリットについては,どのようにお考えですか。
荒木「ここで,私たちが認識しなければならないのは,しっかりした人材を育成していかなければ,将来日本は経済をはじめ様々なことが立ち行かなくなってしまい,国が成り立つかどうかわからない危機的な状況に陥ってしまうということです。企業にとって,学校と組んで教育CSRを進めることは,こうした長期的展望に立てば,未来への投資といえます。いまの若者を見ていると,機器がどんどんブラックボックス化して本質がわからない,構造がわからないという問題が出てきていると思います。対応能力がどんどん弱くなり,急激な変化が起こったときに対応できなくなってしまうのではないかと心配です。しっかりした人材を育成していかなければ,企業自身も経営がなりたたなくなってしまうし,国の存亡も危なくなってしまう,そうした危機感を,大人全体がもたなければいけない時代になっていると思います。」
── 欧米資本の企業は,比較的に利益を社会に還元する指向があるように感じます。また,日本では,中小企業が地元に利益を還元していく取り組みが見受けられる一方,大企業では,規模が大きいだけに,やりたい気持ちはあるが具体的なやり方がわからないという話も聞きます。
荒木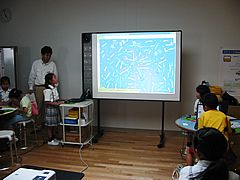 「例えば,CSKさんからは,毎週,ゲスト・ティーチャーを派遣していただいて,クリケットの授業を展開していただいています。また,HP(日本ヒューレット・パッカード)さんは,社内に『HPスクイーカーズ』というボランティアの組織ができていて,ボランティアで休暇を取って社会貢献することを推進する企業文化があります。CSKさんやHPさんのような取り組みをしている企業は,社会的に評価され,企業価値を高めることにつながっていると思います。日本では,企業が利潤追求のために設備投資と拡大生産を繰り返すことに重点をおいてきた傾向があると思いますが,欧米では,企業が利潤を一定の割合で社会に還元し,その活動を社会が認めてきた歴史文化があるのでしょう。日本の企業にも,利潤を社会に還元し人材づくりをしていく,という発想の転換が必要だと思います。そういう文化を築いてこなかったからやり方がわからないという側面
はあると思います。しかし,別にロボットでなくても,企業の得意分野を活かしたり地域の特色と結びつけたりして様々にかかわれると思います。また,個人としてゲスト・ティーチャーやボランティアでかかわることもできます。やり方はいくらでもあるんです。」
「例えば,CSKさんからは,毎週,ゲスト・ティーチャーを派遣していただいて,クリケットの授業を展開していただいています。また,HP(日本ヒューレット・パッカード)さんは,社内に『HPスクイーカーズ』というボランティアの組織ができていて,ボランティアで休暇を取って社会貢献することを推進する企業文化があります。CSKさんやHPさんのような取り組みをしている企業は,社会的に評価され,企業価値を高めることにつながっていると思います。日本では,企業が利潤追求のために設備投資と拡大生産を繰り返すことに重点をおいてきた傾向があると思いますが,欧米では,企業が利潤を一定の割合で社会に還元し,その活動を社会が認めてきた歴史文化があるのでしょう。日本の企業にも,利潤を社会に還元し人材づくりをしていく,という発想の転換が必要だと思います。そういう文化を築いてこなかったからやり方がわからないという側面
はあると思います。しかし,別にロボットでなくても,企業の得意分野を活かしたり地域の特色と結びつけたりして様々にかかわれると思います。また,個人としてゲスト・ティーチャーやボランティアでかかわることもできます。やり方はいくらでもあるんです。」
── 社会人の方々が学校で教育にかかわることは,企業の社会的貢献そのものを子どもたちにリアルに見せていることになりますから,あるべき社会人の姿を見せるという意味でも非常に価値の高いことだと感じました。
荒木「もっと大人が自信をもって,人としての生き方や在り方を子どもたちに示していきたいですね。そのような学校文化や企業文化が出てくれば,まだまだ我が国の将来も捨てたものではありません。子どもに夢や希望を持たせるには,私たち大人が夢や希望を語りたいですね。
私は,校長である後藤に『この学校からノーベル賞を取るような人材を輩出したい』と言われ,その一言に魅せられて立命館小学校にやってきたようなところがあります。ですから,この取り組みを発展させて,子どもたちの興味・関心を伸ばしていき,国際的に活躍し,社会に貢献する人材を育成していきたいですね。」
── 今のお話は,ライフ・ワークになりそうですね。
荒木「そうですね,何年先になるんでしょうか。50年先であれば生きているかどうかわかりませんが。(笑)」
── 先生ご自身が大きな夢をお持ちになっていることが,教え子さんにとっても大切なことだと思いますので,これからも夢を持ち続けて教育に臨んでください。本日は,開校2年後の段階でお話を伺いましたが,また,節目の年にお話を伺い,どのように進展してきたのかを教えていただけることを楽しみにしております。
Copyright(C)2008
KYOIKU SHUPPAN CO.,LTD. All Rights Reserved.