
滋賀県立琵琶湖博物館
事業部長 中島 経夫 先生
インタビュー(1)
日本最大の湖のほとりに建つ滋賀県立琵琶湖博物館は,「湖と人間」をテーマに,1996年にオープンしました。
今回は,博物館の特色や研究内容などについて,開設準備室の頃から勤務され,現在は総括学芸員の中島経夫先生にお話を伺いました。
(聞き手:編集部 岡本)

■琵琶湖博物館の特色■
─― よろしくお願いいたします。滋賀県は非常に水関係の取り組みが盛んな県と思いますが,その中での琵琶湖博物館の位
置づけをふくめて,まず博物館の特色についてから,お話をお願いします。
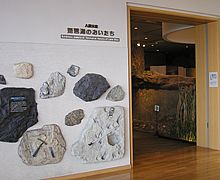 中島経夫先生
(以下,中島)「はい。まず博物館の考え方として,3つの基本理念があります。その1つめは,「湖と人間」というテーマをもった博物館であるということです。これは,いわゆる並列なのではなく,湖と人間がどのようにかかわってきたのか,そして現在のかかわりがどのように出来上がってきたのか,さらに将来どのようにかかわっていくことが必要なのか,ということまでを考えて扱う博物館なのです。ですから,研究テーマも,「湖と人間」に即した形で設定されていますし,展示もそうなっています。「湖」は,ご存じのように琵琶湖ですね。滋賀県の位
置を正確に言えるかというと,わからない人がかなりいる,滋賀と岐阜とどっちがどうなのか区別
がつかない人もいるでしょう。でも,琵琶湖の位置はほとんどの人が知っていると思います。そういう意味で,琵琶湖は滋賀県のアイデンティティーになっているわけです。それから,環境の問題があります。昔から滋賀県は,湖の環境をどう保全していくかに取り組んでいます。その延長線上に,琵琶湖博物館もあるのだろうと思います。
中島経夫先生
(以下,中島)「はい。まず博物館の考え方として,3つの基本理念があります。その1つめは,「湖と人間」というテーマをもった博物館であるということです。これは,いわゆる並列なのではなく,湖と人間がどのようにかかわってきたのか,そして現在のかかわりがどのように出来上がってきたのか,さらに将来どのようにかかわっていくことが必要なのか,ということまでを考えて扱う博物館なのです。ですから,研究テーマも,「湖と人間」に即した形で設定されていますし,展示もそうなっています。「湖」は,ご存じのように琵琶湖ですね。滋賀県の位
置を正確に言えるかというと,わからない人がかなりいる,滋賀と岐阜とどっちがどうなのか区別
がつかない人もいるでしょう。でも,琵琶湖の位置はほとんどの人が知っていると思います。そういう意味で,琵琶湖は滋賀県のアイデンティティーになっているわけです。それから,環境の問題があります。昔から滋賀県は,湖の環境をどう保全していくかに取り組んでいます。その延長線上に,琵琶湖博物館もあるのだろうと思います。
2つめは,フィールドへの誘いとなる博物館を理念にしています。どういうことかというと,琵琶湖の集水域と滋賀県の領域というのは,ほぼ一致します。要するに,県境が周りの山々になっているわけです。ですから,琵琶湖の環境問題を考えるときは,じつは,私たちの使った水すべてが琵琶湖に流れ込むのだ,という認識から始めないといけないのです。使った水が全部,琵琶湖に入るわけですから,身近な水路,田んぼの水路,家の前を流れている川,そういうものを1つ1つクリアにしていかないといけないわけです。そういう意味で,「湖と人間」というテーマについて考える対象は,滋賀県中どこにでもある。また,博物館にある資料や展示物も,滋賀県のどこにでもある。このような考え方から,本当の博物館は,博物館の中にあるのじゃなくて,どこでも博物館だというのです。琵琶湖博物館という施設は,本当の博物館に入るための入り口です。博物館に来ることで,もう一度,自分たちの暮らしや身近な環境を考え直しましょう,見つめ直しましょう,というきっかけになってもらえればいいと思います。
最後は,交流の場としての博物館,いわゆる参加型の博物館を理念にしています。今ではどこの博物館でもそういうことを言っていますが,琵琶湖博物館ができた時点では,これに関してはかなり先進的だったと思うのです。つまり,「湖と人間」というテーマについていろいろ考える人たちがこの博物館を利用して,人と人とが出会って,いろいろ交流が生まれる,そういう博物館になればという思いをもって,いわゆる準備室とよばれていた開館前のときに考えたことです。以上が,3つの基本理念です
。」
── 非常にわかりやすい理念ですね。それをどのように具現化しているのですか?
中島「この3つの基本理念をどういうふうに実現するかということで,博物館では5つの事業を行っています。それは,〔研究・調査〕〔資料整備〕〔情報〕〔交流・サービス〕そして〔展示〕です。小さな博物館では,学芸員が少ないので,これら5つの事業のどれかができていません。しかし,琵琶湖博物館では,この5つの事業どれもがうまく機能して,お互いに結び付き合いながらできていないと,うまく運営できないだろうと考えたわけです。
一般の方々が博物館を見た場合,どちらかというと〔展示〕に目がいきがちです。もう少し積極的にかかわろうという方々なら,観察会に参加したり,いろいろと実施されている講座に参加したりすることで,〔交流・サービス〕が見えてくるわけです。自らがアクティブに動いて,展示が次々に替われば,博物館は活発に動いていることになります。展示を作るときには,それを作るだけの裏付けが必要です。それから,博物館で講座をするとなれば,その話す内容が必要です。そのときに,例えば,『ある本にはこう書いてありますから』と言って,本の内容を紹介するような講座というのは面
白くないのです。」
── そうでしょうね。(笑)
中島「学校の授業だって同じだと思うのです。教科書にいろいろ書かれている事柄でも,その学校の先生が自分で知った内容ではなくて,どこかから知識をもってきて子どもたちに伝えたとしたら面
白くないでしょう。小学校から高校までの学校教育はそうなりがちではありませんか。面
白い講義にするためには,先生たちが教えるときに,いかに工夫するかだと思います。やっぱり,自分が研究して,今わかった内容をそのまま話せたら,いちばん面
白いはずです。そのときの講義って,先生自身がいちばん生き生きするのです。先生自身が楽しい講義をしない限り,聞き手もわからない。特に,難しい内容を,先生もこれでいいのかなという疑問をもちながら子どもに教えたのでは,子どものほうも辛いでしょう。しかし,難しい内容でも,先生が自分で体験したことなら,ちょっと言い方を変えるとか,いくらでも方法はあるわけです。自分で獲得した知識は何とか理解させることができますが,ほかからの知識ではそうはいかないと思います。だから,博物館の展示でも先生方の授業でも一緒ですが,いちばん基にあるのは〔研究・調査〕です。博物館では,研究・調査活動があって,それを情報システムでうまく組み合わせて,標本や資料を登録しながら,展示していく。うちの博物館の特徴を説明するときは,研究・調査活動を基礎において,他の4つの活動をしています,と言っています。」
■博物館の研究について■
─― 琵琶湖博物館の研究・調査について,具体的に説明していただけますか?
 中島「はい,わかりました。うちの研究は,基本的にはプロジェクト研究の形をとっています。プロジェクトには総合研究と共同研究があって,あとは学芸員がそれぞれの専門性を高めるための研究になります。総合研究と共同研究については,それぞれ年度ごとに学芸員が研究計画調書を提出して,それを審査会で審査して,それで採用や不採用が決められます。審査員は館外者がなっていますので,研究費の執行についてはかなり厳しくチェックをされます。総合研究は,原則的に「湖と人間」というテーマにふさわしい研究をやります。それから,共同研究の場合は,もう少し個別
テーマになります。
中島「はい,わかりました。うちの研究は,基本的にはプロジェクト研究の形をとっています。プロジェクトには総合研究と共同研究があって,あとは学芸員がそれぞれの専門性を高めるための研究になります。総合研究と共同研究については,それぞれ年度ごとに学芸員が研究計画調書を提出して,それを審査会で審査して,それで採用や不採用が決められます。審査員は館外者がなっていますので,研究費の執行についてはかなり厳しくチェックをされます。総合研究は,原則的に「湖と人間」というテーマにふさわしい研究をやります。それから,共同研究の場合は,もう少し個別
テーマになります。
わたしがやっているのは,『東アジアの中の琵琶湖−コイ科魚類の展開を軸とした−環境史に関する研究』という総合研究です。これは,コイ科魚類を中心にして,物事を見たらどう見えるか,というものです。数千万年前であれば,そこにはコイ科魚類をふくむ自然環境が研究対象です。地形はどうなっているかとか,大地や気候の問題とか,そういう環境とコイ科魚類との関係を見るのです。それは地質学であったり,古生物学であったりします。
ところが,1万年前〜数千年前,いわゆる縄文〜弥生時代であれば,今度はそこに人間が出てきます。コイ科魚類を中心に,その周りで動く生物の1つとして人間をとらえる見方ができるわけです。考古学では,基本的には人間を対象として,人間がどういう活動をしたのかを見ることになります。歴史学では,あくまでも人間が対象です。しかし,コイ科魚類のことを考えながら考古学や歴史学を見たら,あるいはコイ科魚類がいるという想定のもとに社会学で人間を研究したら,どうなるでしょうか。例えば,縄文〜弥生時代の漁労活動を考える際に,古文書の中にコイ科魚類の記載がないか,漁の仕方はどんなのだったか,という研究ができるわけです。
このように,コイ科魚類という軸を通すことによって,あるところは自然科学として見て,あるところは自然科学と社会学を結びつけて「湖と人間」というかかわりを見ます。そこでは,単なる学問としての考古学だけではなくて,生き物や自然というものも意識することによって,見方が変わってくるのです。
わたしは,専門は魚類形態学でコイ科魚類をずっと研究しているわけですが,例えば,遺跡から出てくる咽頭歯を見ることで,どういう種類の魚が捕られていたかがわかります。そして,その魚はこういう生態をしていたはずだから,こういう捕られ方をしたはずであるという考えを,自分自身が提供できます。そこではもう,咽頭歯という形態学の問題が単に形態学ではなくて,考古学の問題にもなるわけです。
つまり,それぞれの分野のデータが,異分野ではどう使われるか,というやり方をする研究です。だから,こうした研究は,博物館じゃないとできないと思います。大学ならば,学部を超えて一緒にやろうというのはかなり大変だと思います。ところが,博物館の学芸員室や事務室では,歴史学の古文書を読む人が隣になることもあります。異分野の人たちが共同で研究を進められるのは,博物館のよい点であると思っています。
」
── この研究は,どのくらいの期間やられているのですか?
中島「10年ほどです。」
── 期間はどのように決まっているのですか?
中島「だいたい10年ぐらいが最長です。基本的には何年計画でやりますと出しますが,毎年,審査があります。だから,最初の年に10年計画でやりますと言ったから10年間それが保証されるとは限りません。成果
が出なかったら,翌年,駄目と言われるかもしれない。毎年,毎年の審査ですから,かなり厳しいです。」
── そうすると,ロングスパンでの研究の概要とともに,単年度の成果
も非常にシビアに見られていて,そういう意味では1歩1歩,階段を昇らないとゴールにたどり着けないんですね。
Copyright(C)2004
KYOIKU SHUPPAN CO.,LTD. All Rights Reserved.