
生命の星・地球博物館
館長 青木 淳一 先生
インタビュー(2)
生命の星・地球博物館は,1995年3月に,横浜馬車道の神奈川県立博物館(現在の神奈川県立歴史博物館)の自然史部門が独立する形で誕生した博物館です。
今回は,この博物館の館長であり,日本のダニ研究の第一人者でもある横浜国立大学名誉教授の青木淳一先生に,博物館や教育などについて,いろいろお話を伺いました。
(聞き手:編集部 岡本)

■自然に興味をもたせるには■
── 小学校では,生活科という教科ができて,1〜2年の理科と社会科がなくなりました。低学年では,野外に出ても,科学的な考え方を身につけるより,身のまわりの自然を眺めて感じる傾向が強いと思います。
青木淳一先生 (以下,青木)「子どもたちに,自然に興味をもたせるには,まず最初に採集をさせることです。子どもは捕りたいんです。それを,虫は捕るな,植物はちぎるな,と言ったら,子どもは誰も森や川に行かないですよ。何か捕れるから自然の中に楽しんでもぐっていくわけです。それを禁止したら,子どもは自然の中で遊ばなくなってしまう。大人みたいに手を後ろに回して観察しなさいなんて,子どもは見るだけじゃ満足しないんですよ。」
── もっと観察物とかかわってほしいということですね?
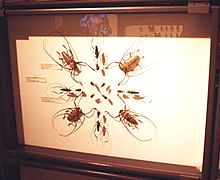 青木「そう。トンボだって,捕まえてビリビリ羽の動く振動が手に伝わってきて,『こいつ,生きてるな』ということが感触でわかる。見ていてもわかんないわけね。採集という心ときめく行為,これが,子どもを自然に引っ張り込み,生物学などの自然科学の出発点になるんです。こうした大事なことが,いま罪悪視されている。
青木「そう。トンボだって,捕まえてビリビリ羽の動く振動が手に伝わってきて,『こいつ,生きてるな』ということが感触でわかる。見ていてもわかんないわけね。採集という心ときめく行為,これが,子どもを自然に引っ張り込み,生物学などの自然科学の出発点になるんです。こうした大事なことが,いま罪悪視されている。
なぜ採集がいけないのかというと,大人は,『虫が減る,自然破壊だ』と言うんです。鳥や獣を銃で撃てば減りますよ,大型動物は少ないんですから。しかし,虫はすごい数がいるから,子どもが道沿いの虫を捕っても減るわけがない。非常に詳しい大人が絶滅しかかっている昆虫を夜討ちして捕ったり,貴重な植物を根こそぎ採ったりしたら危ない。子どもが捕っても,自然破壊とか数が減るなんてことはない。
こう言うと,大人は,『1つ1つのどんな小さな生き物でも,ちゃんと命をもっている。それを捕って殺すのはいけないことですよ』と,こんどは自然保護ではなくて動物愛護になるんです。お母さんが台所に出てきたゴキブリをスリッパでピシャッとやる,でもテントウムシは捕っちゃいけない。ゴキブリだってハエだって命はあるし,アジの開きだって命があったものです。動物愛護というのは,自分で飼っているイヌとかネコとかに限られたものでいいと思うんです。
このようなヒステリックな自然保護や動物愛護が,子どもを自然から引き離している。あまりに神経質な自然保護や動物愛護は,けっしてよい結果
をもたらさないし,子どもを理科嫌い,自然嫌いにしてしまう。 」
── 私も同感ですね,先生がおっしゃるように,虫を捕ったり魚を捕まえたり,そうした実感をもって初めて生命の大切さがわかると思いますね。
青木「昔はね,ガキ大将に引きずられて小さな子も一緒に森や川へ行って,虫や魚を捕ったりしたんですよ。子どもにとっては,昆虫,カエル,ザリガニ,どんぐり,落ちていた鳥の羽根,動物の骨,貝がら,みんな宝物です。それを持って帰って眺めるのが大事なんですね。それを禁止したらかわいそう。」
── そうですね。私が子どものころは裏山とかありましたけど。
青木「いまだってありますよ,自然がないから子どもが外で遊ばないんじゃないんです。理由は2つあって,1つは親が禁止する,もう1つはテレビゲームなど面
白い室内遊びがたくさんできた,それで子どもは自然の中で遊ばなくなってしまった。遊べる自然は探せばいくらでもあります。
子どもに自然に興味をもたせるために,採集することの大切さをこれまで説明してきましたが,2番目は教える側が夢中になることです。先生に興味がないのに,子どもに興味をもたせようとしても無理ですよ。いろいろと観察会をお膳立てしても,指導する先生に興味がなかったら子どもはついてきません。先生があまり興味ないのに無理してやっているな,というのが子どもに見えちゃう。だから,先生自身が,「面
白いから見てごらん」じゃなくて,「なんだこりゃ,すごいな!」「これなんだろう?」と自分から夢中になる姿を見せる,ときにはものも言わずに何か探している,すると,子どもは何をやっているんだろうと寄ってくるんです。この2つがあれば,子どもは絶対についてきます。
」
Copyright(C)2003
KYOIKU SHUPPAN CO.,LTD. All Rights Reserved.