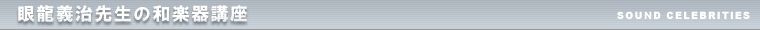 |
|
|
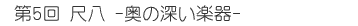 |
 |

尺八は,鎌倉時代に,中国へ留学した禅僧が持ち帰ったのが始まりとされています。江戸時代は普化宗(ふけしゅう 禅宗の一派)の法器とされ,一般の人は自由に演奏できませんでした。一尺八寸(約54cm)の長さからその名前が生れたといわれています。
真竹(まだけ)の根本を用い,指孔が表に4個,裏に1箇あるだけの極めてシンプルな楽器です。それだけに演奏はやさしくありません。管の中の構造は上部の歌口(うたぐち)が広くて,下部の音の出る口に向かって狭くなっています(オーボエやサクソフォンなどはその逆)。そのため,吹き方の加減で音が変わりやすく,音色の変化がたいへん豊かであり,微分音(びぶんおん)的な表現も可能で,大変奥の深い楽器です。独奏楽器として,箏や三味線との合奏楽器として,民謡の伴奏楽器として,さらに最近ではジャズやポピュラー音楽の楽器としても大活躍しています。
また,近年はアメリカ人のジョン・海山・ネプチューンさんのように,“竹の音色”に引かれた外国人のプロ奏者も少なくありません。
|
 |
| ※各部の名称などは教科書の表記に準拠しています。 |
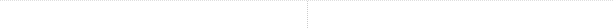 |
|
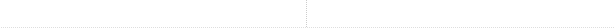 |
琴古(きんこ)流と都山(とざん)流
18世紀に琴古流ができ,20世紀に都山流ができました。それ以外にもいろいろな流派がありますが,現在はこの二つが主流となっています。“海山”のように名前に「山」が入っている奏者は,通常,都山流です。 |
|
| |
|
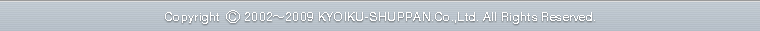 |
|