
科学技術館
館長 有馬 朗人 先生
インタビュー(5)
科学技術館は,日本の科学技術や産業技術に関する知識を広く普及・啓発する目的で,財団法人日本科学技術振興財団が設立した施設で,昭和39年4月に開館しました。
今回は,館長の有馬先生に,科学技術館の特徴や将来,科学館の社会における役割,日本の科学教育の現状と課題など,さまざまなお話を伺いました。
(2006.7.31 聞き手:編集部 岡本)
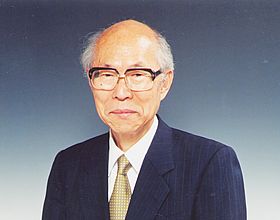
■科学技術館の未来■
── 科学技術館は,これからどのように変わっていくのでしょうか。
有馬朗人先生  (以下,有馬)「私が館長になって今議論しているのは,どんな思想でどのように科学技術を国民に知らせるかということ。私の方針は,あくまでも民が中心になって,ここを日本の産業のショウウィンドウにしようというのが基本的な考えです。事実,日本科学未来館ができるまでは,ここに外国人が大勢来たものでした。日本の産業のレベルを見ようと来る。自動車もあるし電力もあるし,ここに来れば日本の産業の力が見えるというので,ずいぶん外国人が来ていたが,残念ながら最近は,最先端というと日本科学未来館に行ってしまいます。だから,経団連には,日本の産業の本当の底力はここでなければ見せられないと言って,いくつか新しいものも入れてもらいました。この15年間ぐらいは産業界の力が弱くて調子がわるかったけど,最近,また力が出てきてまたやろうかという気運になっています。
(以下,有馬)「私が館長になって今議論しているのは,どんな思想でどのように科学技術を国民に知らせるかということ。私の方針は,あくまでも民が中心になって,ここを日本の産業のショウウィンドウにしようというのが基本的な考えです。事実,日本科学未来館ができるまでは,ここに外国人が大勢来たものでした。日本の産業のレベルを見ようと来る。自動車もあるし電力もあるし,ここに来れば日本の産業の力が見えるというので,ずいぶん外国人が来ていたが,残念ながら最近は,最先端というと日本科学未来館に行ってしまいます。だから,経団連には,日本の産業の本当の底力はここでなければ見せられないと言って,いくつか新しいものも入れてもらいました。この15年間ぐらいは産業界の力が弱くて調子がわるかったけど,最近,また力が出てきてまたやろうかという気運になっています。
例えば,電力業界の展示の隣に何をもってくるか,ガス業界の隣には……,というように,科学や技術のつながりとして展示に思想があっていいと思う。この点,上野の科学博物館は非常にすっきりしていて,基礎科学が地下にあって上に発展していくようにしてあります。博物学的な面
と,基礎物理学的・基礎化学的な面そしてその応用すべてを融合させてやっていけます。一方ここは,各企業団体を中心にやってきたから横のつながりがないし,実際に展示を変えるときは企業にお任せしている面
がある。もう少し企業と館の学芸員が組んで全般的な思想統一がはかれるといいなと思っています。
もう一つは,バイオ技術が弱い。なぜ,バイオが弱いかというと,ここが始まった1960年ごろはバイオという概念そのものが弱かった。だから,現状として,バイオ,製薬や発酵などの展示が抜け落ちています。4〜5階にDNAなどあるものの,まだまだ弱い。そこで,何とかしてバイオ関係の化学や製薬に関するものが展示できるようにならないか,一生懸命考えています。かつての重厚な分野だけでなく,もう少し軽いバイオとか,醸造,薬学,医学といった分野も日本が強いことを知らせたい。」
── 官主導ではなく,産業界を中心にできた館のよさを生かしながら,今の産業地図のようなものを展示で知らせたいという構想なんですね。
有馬「今,経団連と一緒になって構想を練り,できた構想の実現に向けて動いているところです。」
── 楽しみですね。戦後の日本を支えてきた産業界がつくった館ですから,一時的に産業界の元気がなかったからといって官主導にするのではなく,あくまでも産業界自身の力で盛り立ててもらいたいと思います。
有馬「日本科学未来館は,文部科学省の主導だから官や学とのつながりが強い。だけれども産業界とのつながりが弱くて今つながりを強くしようとしている。これも結構なことだと思う。こちらは,もともと産業界がつくったのだから,産業界が主体になっているが,学とのつながりは弱い。私が館長になったこともあって,学とのつながりを強めていこうと思っています。」
── 産業界の教育に対する取り組みを充実させることが,先生の“ゆとり教育”が目指すものにもつながるのでしょうね。地域の産業が市民とどうかかわるか,その象徴として科学技術館があり,それぞれの地域で産業が教育に貢献する,それが実現されると,本当に日本の科学教育はよくなると感じました。
Copyright(C)2006
KYOIKU SHUPPAN CO.,LTD. All Rights Reserved.