
科学技術館
館長 有馬 朗人 先生
インタビュー(6)
科学技術館は,日本の科学技術や産業技術に関する知識を広く普及・啓発する目的で,財団法人日本科学技術振興財団が設立した施設で,昭和39年4月に開館しました。
今回は,館長の有馬先生に,科学技術館の特徴や将来,科学館の社会における役割,日本の科学教育の現状と課題など,さまざまなお話を伺いました。
(2006.7.31 聞き手:編集部 岡本)
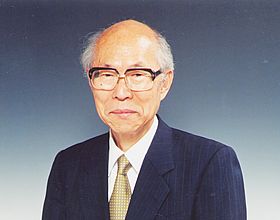
■日本の科学文化■
── 科学文化という観点から考えると,西洋では科学を哲学と同列に扱い,叡智の象徴として位
置づけている印象を受けるのに対して,日本では技術面に偏っているような気がしますが,先生はどうお考えですか。
有馬朗人先生 (以下,有馬)「それは,まず明治時代に東京大学に工学部ができたのが大きいでしょうね。当時,世界に工学部なんてどこにもなかった。あったのはグラスゴー大学ぐらいでしょう。要するに,日本という国は,技術を非常に重要視したんです。ヨーロッパでは,今言われたように科学(Science)が中心で,大学は,法学部・理学部・文学部・医学部からなるのが普通
だった。そこに,アメリカで州が金と土地を出した農学や工学を重要視する大学ができ,それを見た森有礼が,日本にも工学部・農学部をつくらなければならないと考えたと思えます。東京大学ができた1867年から10年ぐらい経ったときに,東京大学の構造改革を行い,それまでの法学部・医学部・理学部・文学部の4学部体制に加えて,日本の国力を強めていくためには工学を強くしなければならないというわけで,農学部と工学部がつくられた。このように,東大に工学部ができたのは世界でも非常に早い時期で,理学部よりはるかに工学部のほうが大きくなった。だから,日本では,各大学で圧倒的に工学部が強く,伝統的に理学部の力が弱い。見方を変えれば,こうした政策によって,戦前から戦後にかけて,日本の産業が急速に発展したともいえます。
このように,日本の大学が,工学に非常に先進的だったことは大成功でした。しかし逆にいうと,やや技術に中心をおきすぎた。それで,基礎科学をもっと強くしようと言われるようになりました。基礎科学的精神が多少弱かった日本においては,戦後湯川先生・朝永先生のおかげで基礎科学の重要性が認識されましたが,このごろは再び工学・技術が中心になってきています。
私は,科学と技術は車の両輪だから両方きちんと進めていかなければならない,とあちこちで言っています。私は,中庸論者だから,基礎科学者には技術の重要性を言うし,技術者には基礎科学の重要性を言う。例えば,計算機について考えると,量
子力学が進んで半導体がつくられ,現在の情報科学が発達して計算機が進歩を遂げた。しかし,この計算機がなければ,小柴さんのニュートリノの発見にしてもその大発見で活躍したカミオカンデにしても存在しないわけです。計算機の技術が非常に進んだことや,微量
な光を測定する技術が進んだことで基礎科学も進む。また,NMRは基礎物理学者が発見したものを基にして高度なものにする技術を進めた。そのNMRの技術が大変進んで高性能な測定器として活躍するようになると,今度は脳科学が進む。だから,技術が進むと科学が進むし,科学が進むと技術が進む。両方が噛み合って進んで行くわけです。どっちかが偉いとか偉くないとか,そういうことはないんです
。」
── どちらかに携わっている方は,もう一方がなかなか見えにくい状況にあると思いますから,先生が他方のよさを説いていただくのは,お互いにとっていい効果
があると思います。
有馬「日本においていちばん弱いのは,どちらにしても基礎ですね。基礎科学だけでなく,基礎技術を含めた基礎研究を大切にしなければならないが,日本はそこが弱いですね。どちらかというと日の当たる研究ばかり行おうとする,これは無理もないことですが。しかし,それだけじゃダメで,やはり基礎研究は大切です。だから,中村さんのLEDなんて立派ですね。あれはもともと基礎研究だから。」
── ここは,科学技術館という名前ですが,科学と技術をまさに融合させることが大切ですね。本日は,いろいろと貴重なお話を有り難うございました。
Copyright(C)2006
KYOIKU SHUPPAN CO.,LTD. All Rights Reserved.