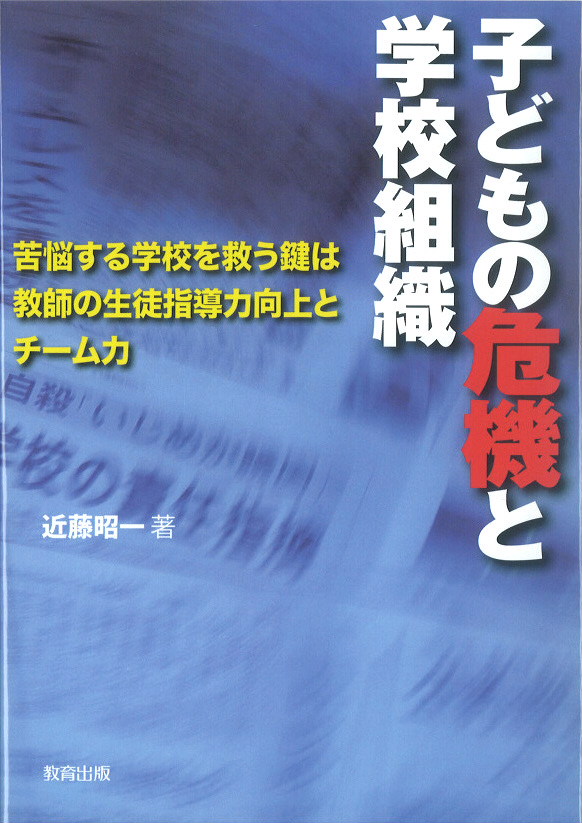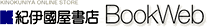子どもの危機と学校組織
子どもの危機と学校組織 苦悩する学校を救う鍵は教師の生徒指導力向上とチーム力
- 近藤昭一著
- A5判 並製 176頁
- 2012年12月 発行
- ISBN 978-4-316-80377-7
- 定価 (税込) 2,200円(本体 2,000円+税)
- 読者対象:教師
商品内容
「子どもが高層マンションから転落!いじめ・自殺か…?」
「不登校の原因は学校だとする損害賠償請求が届いた!」
――子どもの危機,それは同時に学校の危機だ。
教師の生徒指導力と組織行動が子どもを救い,学校を強くする。
目次
Ⅰ 【概論編】子どもの危機場面と生徒指導
――苦悩する学校を救う鍵は教師の生徒指導力向上とチーム力
1 課題山積の学校現場
(1) 子どもたちの暴力やいじめ
(2) 対教師暴力という現象から見えるもの
(3) 役割と協働を忘れた保護者――“モンスター・ペアレント”といわれる親の正体
(4) 大量退職時代と新採用教員の苦悩
(5) 1件の校内盗難で信頼を失う学校
(6) 訴訟社会と学校
(7) 「丸投げされる学校」という見方
(8) すべての教師が学校経営の意識をもつこと
2 現代の子ども・若者の行動傾向
(1) とらえておきたい子どもの実像と成長上の課題
(2) 暴力行為から見えてくること
(3) 学校現場での出来事から見えるもの――“番長”と“キレる”の違い
(4) いじめをめぐる人間関係から見えてくること
(5) 個人化・自閉化する行動傾向
(6) 自立から遠のく子どもたち――行動の個人化・自閉化の意味するもの
(7) 「社会人基礎力」が求められる日本の若者たちの実態
(8) 大卒新入社員の早期離職率の上昇から見えること
3 社会の変容と「生徒指導の深化」
(1) 学校の荒廃がもたらした「生徒指導の深化」
(2) 行動規制中心の生活指導の限界
(3) 物の豊かさと教育観の変化
(4) 横浜の生徒指導の転換――屋外生活者連続殺傷事件がもたらした衝撃
(5) 行動規制からカウンセリングマインドへ
(6) 子どもの変容はどこから――人間関係の質の変化が子どもの変容をもたらす
4 たくましい子どもたちの育成のために
(1) 「生徒理解の質」を考える
(2) 自立を支える「自律的なアプローチ」と「他律的なアプローチ」
(3) 「厳しい指導」と「客観的な自己認識」
(4) 横浜市で成果を上げている取り組み――「他律的なアプローチ」の具体例
(5) 学校の役割と「中間集団」
(6) 自らを変革していく教師
Ⅱ 【実践・演習編】子どもたちの危機を救う生徒指導実践力と組織行動
――子どもを守る戦略的学校危機管理の組織と行動サイクル
1 身近なところにある子どもの危機と生徒指導
(1) 演習課題による研修のすすめ
(2) 身近な危機場面を考察する(1)
(3) 身近な危機場面を考察する(2)
2 生徒指導実践演習
(1) 学校の組織行動のための7つの視点
(2) 演習課題(1) 教室のドアに指を挟んだ生徒のけが(中学校)
(3) 演習課題(2) 夜遅くなっても帰宅していない女子児童の保護者からの連絡(小学校
(4) 演習課題(3) 自宅マンションから生徒が転落(中学校)
(5) 演習課題(4) いじめ被害による不登校にかかる責任追及文書への対応(小学校)
(6) 学校の危機管理のための重要戦略としての生徒指導実践力
3 学校の組織行動力=チーム力向上のために
(1) 学校危機管理の行動サイクル
(2) 学校の危機管理における職員の組織と体制
ご購入方法
ご購入希望の際は,お近くの書店にご注文下さい。
また,この本は,下記のオンライン書店でもご購入いただけます。
送料・お支払い方法等につきましては,各オンライン書店のホームページをご参照下さい。