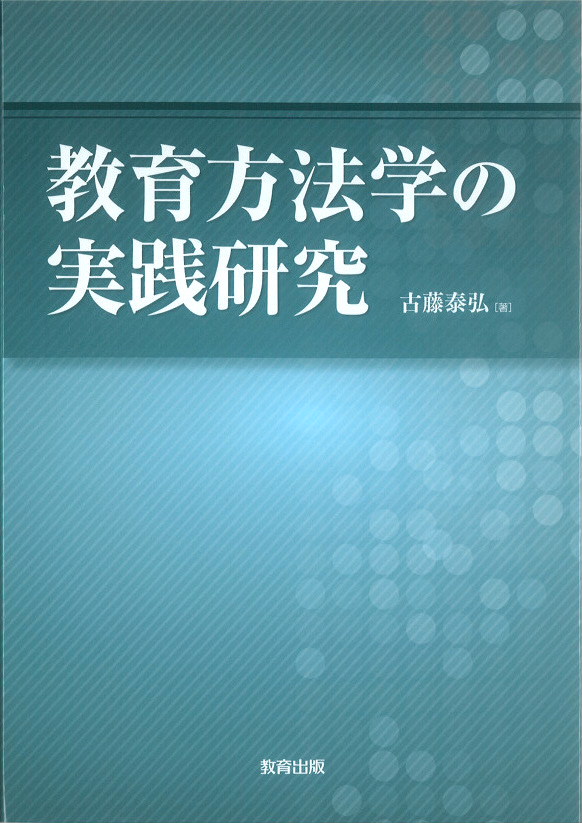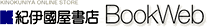教育方法学の実践研究
教育方法学の実践研究
- 古藤泰弘著
- A5判 並製 224頁
- 2013年4月 発行
- ISBN 978-4-316-80391-3
- 定価 (税込) 2,860円(本体 2,600円+税)
- 読者対象:教師,学生
商品内容
「共生」「情報」といった今日的課題を踏まえた,新しい「教育方法学」のテキスト。
目次
プロローグ
第1章 教育方法学を学ぶ
第1節 教育方法学と授業研究
1.教育方法学の学問的性格
2.実践の学としての授業研究
第2節 「共生」を視野に入れた授業研究
1.「共生」の意味と共生科学
2.教育における「共生(kyosei)」
(1) ユネスコの活動にみる「共生」
(2) 「サラマンカ声明と行動大綱」とインクルーシブ教育
(3) 『学習:秘められた宝』にみる「共生」
(4) 持続発展教育(ESD)にみる「共生」
(5) PISAのキー・コンピテンシーにみる「共生」
第3節 学習力の育成と授業研究
1.「学力(低下)論争」と国際学力調査
2.「PISA型学力」と平成20年版学習指導要領
3.問われているのは「学習力」
第4節 デジタルメディアの活用と授業研究
1.情報教育との関連をどうとらえるか
2.学習指導要領・総則の立場
3.多様化する「デジタル授業」とICT活用
第2章 教える心理,学ぶ心理
第1節 教えることと学ぶこと
1.「教える」という所為
2.「学ぶ」という所為
3.「教える」の二つの意味
4.「学び」の心理からみた授業像
5.「学び」の心理からみた教師像
6.カウンセリング・マインド
第2節 教える技術の法則性と評価・評定
1.教える技術の特質と教育におけるパラドックス
(1) 教える技術の特質―法則性の検討
(2) 反省的実践説の検討
(3) 教育におけるパラドックス
(4) 「主体性を育てる」を考える
2.自己評価能力を育てる学習評価
(1) 評価と評定
(2) 評価と評定の意義
(3) 自己評価self evaluation
(4) 「鏡に映った自己」との対話
(5) 自律的学習行動力の育成
(6) サンライズ(加点的)評価
(7) 評価は始発駅
第3章 学習と授業
第1節 学習の心理学と学習のとらえ方
1.「わかる」と「できる」の心理学と授業
(1) 授業で「わかる」の意味
(2) 「わかる」の心理状況
(3) 「わかる」授業と指導目標
(4) 指導目標の三つの領域―事例で検討
(5) 授業で「できる」の意味
(6) 「できる」の心理学的意味
(7) 「できる」授業と目標行動―事例で検討
(8) 目標行動(学習目標)の設定条件
(9) 指導目標と目標行動(学習目標)
2.構成主義などにおける「学び」の意味
(1) 構成主義(constructivism)の学習理論
(2) 正統的周辺参加論における「学び」
(3) 「学び」と「学習」―「学習」の再定義
第2節 授業のとらえ方と授業技法
1.「授業」の意味ととらえ方
(1) 「授業」の意味
(2) 授業の使命
(3) 授業は「生きもの」
(4) 「反省的授業」の考え方
(5) 授業の所産的とらえ方と過程的とらえ方
(6) 実践的な授業のとらえ方
2.授業の双方向コミュニケーションにおける授業技法
(1) 双方向コミュニケーション
(2) 最初の「発問」
(3) 「刺激情報」提示の条件―バーラインに学ぶ
(4) 「反応情報」における方策
(5) カードで挙手の工夫
(6) 大切な「KR」情報
(7) 情的KRの工夫
(8) 授業過程の支援モデル
(9) 「総合的な学習の時間」と学習活動
第3節 様々な授業様式
1.「探究学習」系譜の授業様式
2.デューイの問題解決学習
3.「プログラム学習」系譜の授業様式
4.「○○型」授業に固執しない
5.習熟度別指導と個人差
6.「学びやすさ」からみた個人差の検討
第4章 学力観の変遷と学習力のとらえ方
第1節 「学力観」からみた授業づくりの変遷
1.「新教育」と問題解決学習
2.生活中心の経験主義教育
3.基礎的知識と系統的学習
4.科学的知識と探究的学習
5.ゆとりある充実した教育
6.「新学力観」と情意重視の授業
7.社会変動と「生きる力」の育成
8.「生きる力」の学力観への批判
9.「学力低下」対「確かな学力」
10.PISAショックと「活用力」の重視
11.「人間力」育成は国家的改革目標
12.平成20年版学習指導要領の基本的な考え方
第2節 学力のとらえ方と学習力の検討
1.学力のとらえ方
(1) 「学力」問題から学ぶ
(2) 「学力」とは何か
(3) 「学力」の領域の検討
(4) 「学力」の階層(レベル)の検討
2.「学習力」の意味ととらえ方
(1) 「学習力」という言葉
(2) 「学習力」は社会的な課題
(3) 不毛な学力低下論争
(4) 「学力」よりも「学習力」
(5) 「学習力」を構成する三つの能力と構造
(6) 学習力の「基盤になる能力」
(7) 「方法的能力」の中身
(8) 「推進する能力」の中身
第5章 授業づくりの基本と学習指導案
第1節 授業の方略と授業づくり
1.授業の方略と方策
2.「内容知」重視の方略と授業づくり
3.完全習得学習(mastery learning)
4.「方法知」重視の方略と授業づくり
5.「体験知」重視の方略と授業づくり
第2節 「学習力」を育てる授業づくり
1.出発点は「なぜ,教えるの?」
2.「ワン・オブ・ゼム」の姿勢で臨む
3.単元全体の見通しを立てる
4.授業の味つけに変化をつける
5.本時の目標は二刀流で
6.体温を感じるコミュニケーションの場をつくる
7.やり遂げた成就感と達成感の共有
第3節 授業計画と学習指導案
1.授業の方略と授業の実践計画
2.授業の実践計画と学習指導案
3.授業の安全弁
4.教師の自己研修
5.授業の共同研究
6.授業の科学的な改善
7.学習指導案の記載事項
第6章 メディアの活用と情報教育
第1節 授業におけるメディアの活用
1.テレビ放送利用と映像教育
2.デールの「経験の円錐」
3.教育工学と教育機器の活用
4.1985年はコンピュータ教育元年
第2節 コンピュータ利用の変遷
1.CAI学習から始まった
2.「コンピュータ利用」と「情報教育」の関係
3.コンピュータの「道具的利用」
4.マルチメディアと「自己表現道具」
5.全教連の共同研究にみる情報教育のとらえ方
6.情報教育の見直し
7.インターネット利用による「受発信学習」
8.「IT新改革戦略」とICTの活用
9.平成20年版学習指導要領と教育の情報化
10.「フューチャースクール」構想とデジタル教科書
11.テクニカル・プッシュと今後の課題
12.再考したい「情報教育」とコンピュータ利用
第3節 情報教育の課題
1.「情報教育」を取り入れた教科横断的授業
(1) 情報教育の「分散型」の問題点
(2) 「教科等を横断して改善すべき事項」(中教審)
(3) 教科横断的な授業の編成
(4) 国語の指導に情報教育を取り入れた授業例
2.「情報モラル」の意味と共生を視野に入れた「著作権」の指導
(1) 「情報モラル」の意味
(2) 「情報モラル」の内容の検討
(3) 「著作権」指導の問題点
(4) 著作権指導のあり方―共生を視野に入れて
(5) 共生の視点からの「引用」の指導
エピローグ
索 引
ご購入方法
ご購入希望の際は,お近くの書店にご注文下さい。
また,この本は,下記のオンライン書店でもご購入いただけます。
送料・お支払い方法等につきましては,各オンライン書店のホームページをご参照下さい。