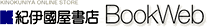詩の教材研究
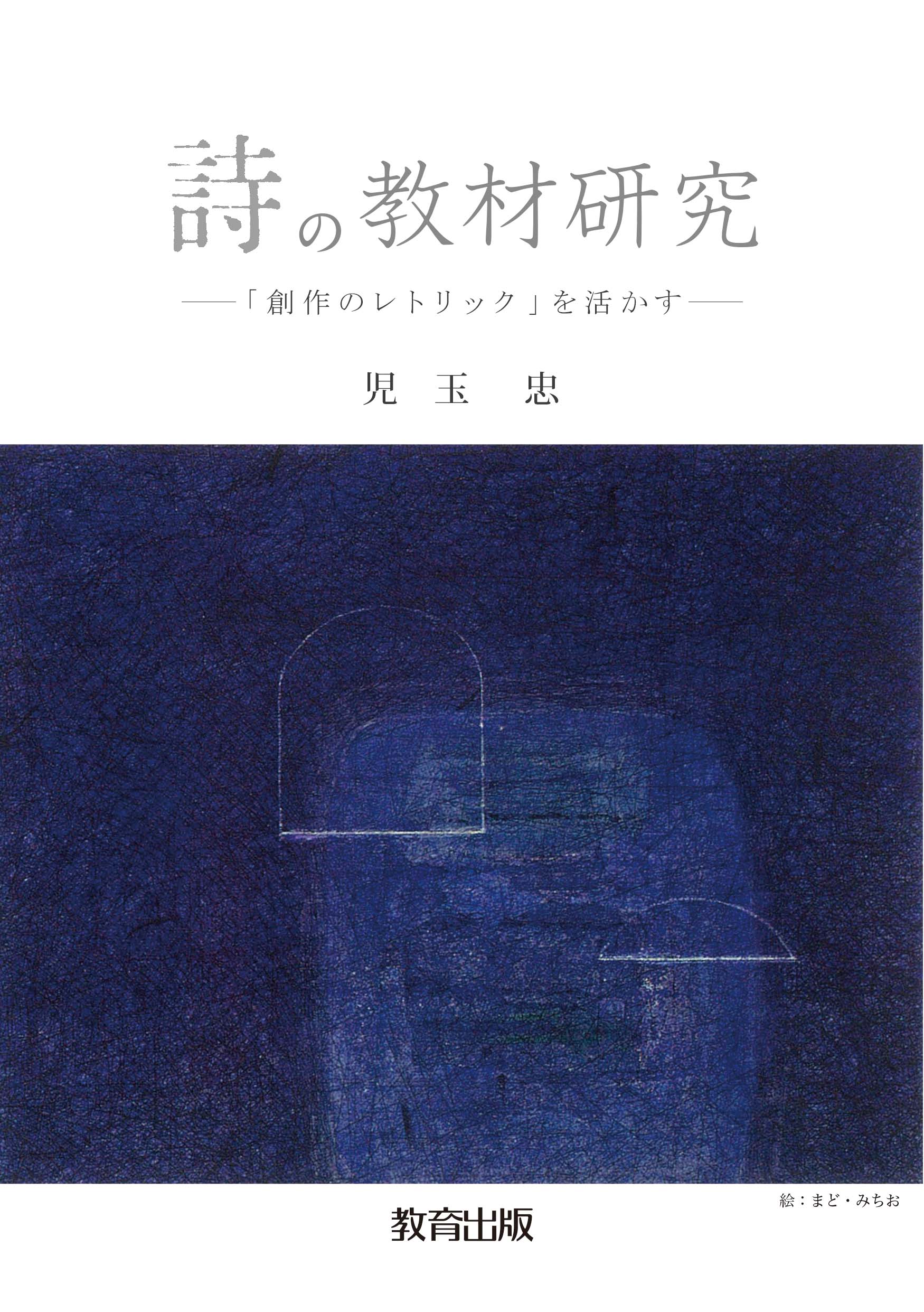
詩の教材研究――「創作のレトリック」を活かす
- 児玉 忠著
- A5判 並製,カバー装 328頁
- 2017年4月 発行
- ISBN 978-4-316-80445-3
- 定価 (税込) 2,640円(本体 2,400円+税)
- 読者対象:小学校・中学校・高等学校 教師,学生
商品内容
「詩の授業で何を教えたらよいのかわからない」
そんな先生にぜひ読んでほしい本です。
***
視点・語り手
発想・認識
想像・イメージ
比喩・象徴
オノマトペ
音韻・リズム
文字・フォルム
方言・語り口
8つのレトリックを軸に,
創作と鑑賞の両面から,
詩作品の教材性や授業のあり方を提案します。
第三章では,戦後の児童詩教育史を俯瞰。
付録として年表も収載。
目次
第一章 創作指導の側から考える詩の教材性
第一節 詩教育の現状と課題
⑴ 詩の現在と詩教育の課題
⑵ 教科書における創作教材と読み教材との乖離・断絶
第二節 創作指導と受容指導の関連・往還のために
⑴ 創作と受容との関連・往還をめざした詩の教材性と教材編成
⑵ 「創作のレトリック」に基づく教材性と教材編成
第二章 「創作のレトリック」を活かす詩の創作と受容
第一節 「わたし」を変換して見える世界を広げる――視点・語り手――
⑴ 創作のレトリックとしての「視点・語り手」
⑵ 「視点・語り手」を活かした詩の創作
⑶ 「視点・語り手」でつなぐ詩の受容
第二節 矛盾の向こう側を見つめて常識を超える――発想・認識――
⑴ 創作のレトリックとしての「発想・認識」
⑵ 「発想・認識」を活かした詩の創作
⑶ 「発想・認識」でつなぐ詩の受容
コラム 現代児童詩を読む① ――詩人の発想・子どもの発想――
第三節 現実を変形させてまだ見ぬ世界を創造する――想像・イメージ――
⑴ 創作のレトリックとしての「想像・イメージ」
⑵ 「想像・イメージ」を活かした詩の創作
⑶ 「想像・イメージ」でつなぐ詩の受容
第四節 異質な言葉を結び付けて新しい意味を紡ぎ出す――比喩・象徴――
⑴ 創作のレトリックとしての「比喩・象徴」
⑵ 「比喩・象徴」を活かした詩の創作
⑶ 「比喩・象徴」でつなぐ詩の受容
コラム 現代児童詩を読む② ――創作における「感動」のありか――
第五節 感覚と言葉とが初めて出会う現場に分け入る――オノマトペ――
⑴ 創作のレトリックとしての「オノマトペ」
⑵ 「オノマトペ」を活かした詩の創作
⑶ 「オノマトベ」でつなぐ詩の受容
第六節 声に出して「からだ」と「居場所」を取り戻す――音韻・リズム――
⑴ 創作のレトリックとしての「音韻・リズム」
⑵ 「音韻・リズム」を活かした詩の創作
⑶ 「音韻・リズム」でつなぐ詩の受容
コラム 現代児童詩を読む ③ ――ことば遊びが「詩」になるとき――
第七節 漢字と戯れ、文字をオブジェとして眺める――文字・フォルム――
⑴ 創作のレトリックとしての「文字・フォルム」
⑵ 「文字・フォルム」を活かした詩の創作
⑶ 「文字・フォルム」でつなぐ詩の受容
第八節 ふるさと言葉に切り替えてそのキャラクターになる――方言・語り口――
⑴ 創作のレトリックとしての「方言・語り口」
⑵ 「方言・語り口」を活かした詩の創作
⑶ 「方言・語り口」でつなぐ詩の受容
コラム 現代児童詩を読む ④ ――「方言話者意識」の発達――
第三章 わが国の児童詩教育の歴史
第一節 わが国の児童詩教育とその歴史
第二節 一九五〇年代までの児童詩教育
⑴ 童謡・児童自由詩(一九二〇年代~)
⑵ 児童生活詩(一九四〇年代~)
第三節 一九六〇年代の児童詩教育の対立(「児童生活詩」と「主体的児童詩」)
⑴ シュールレアリズムの児童詩教育への応用
⑵ 松本利昭の児童詩教育論
⑶ 稲村謙一の児童詩教育論
⑷ 滑川道夫の児童詩教育論
第四節 一九七〇年代以降の児童詩教育
⑴ 一九七〇年代の児童詩教育(「主体的児童詩」のその後)
⑵ 一九八〇年代の児童詩教育(「ことば遊び」の台頭)
⑶ 一九九〇~二〇〇〇年代の児童詩教育(「第三の世界」の児童詩の展開、他)
付録 児童詩教育史文献年表
ご購入方法
ご購入希望の際は,お近くの書店にご注文下さい。
また,この本は,下記のオンライン書店でもご購入いただけます。
送料・お支払い方法等につきましては,各オンライン書店のホームページをご参照下さい。