なぜクラスじゅうが理科に夢中なのか
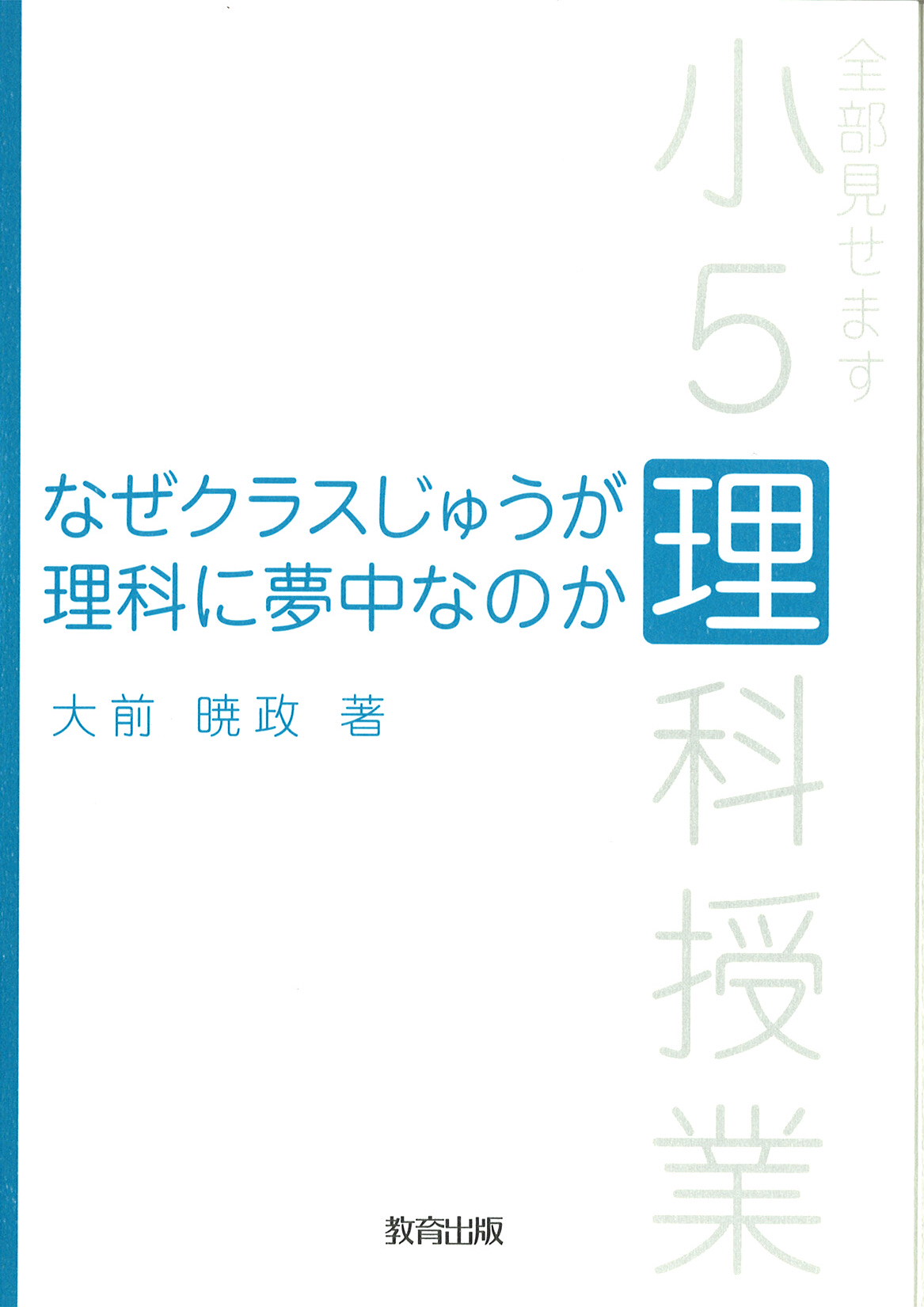
なぜクラスじゅうが理科に夢中なのか 全部見せます小5理科授業
- 大前暁政著
- A5判 並製・カバー装 232頁
- 2010.3.31 発行
- ISBN 978-4-316-80302-9
- 読者対象:小学校教師
商品内容
課題,発問,児童とのやりとり,実験や観察の方法,児童ノート例などを
つぶさに紹介。
微生物の集め方,インゲン豆を育てるのに最適な土,台風の風速を体感させる方法……,
授業づくりの舞台裏も大公開しました。
単元ごとの「指導計画」,「習得させたい知識」,「習得させたい技能」も
しっかりおさえています。
大前暁政先生のオフィシャルウェブサイトはこちら!
↓↓
<大前暁政の教育>
http://akimasa.s1007.xrea.com/
目次
Ⅰ 雲と天気の変化
単元のはじめに
第1時 いろいろな種類の雲を知る
第2時 雲の量や種類によって天気が変化することを知る
第3時 雲の有無によって天気が変化することを知る
第4時 雲の動きによって天気が変化することを知る
第5時 雲の動きを予想して天気の予報を行う
第6時 天気の変化のまとめを行う
Ⅱ 植物の発芽と成長
単元のはじめに
第1時 種から芽が出るために何を与えればよいか
第2時 発芽の条件を調べる実験方法を考える
第3時 調べたい条件を選んで1人1つの実験を行う
第4時 実験の結果を考察する
第5時 植え替えを行う
第6時 植物の成長に使われた栄養は何かを考える
第7時 さらに成長するために必要なものは何かを調べる
第8時 植物をもっと大きく成長させるための条件をまとめる
Ⅲ メダカのたんじょう
単元のはじめに
第1時 メダカの飼育のための準備を開始する
第2時 オスとメスの体の違いを知る
第3~5時 卵が変化していく様子を観察する
第6時 生まれたメダカと親メダカの違いを観察する
第7時 水中の小さな生き物を観察する<低倍率>
第8時 水中の小さな生き物を観察する<高倍率>
第9時 陸上の小さな生き物を観察する
Ⅳ 花から実へ
単元のはじめに
第1時 雄花と雌花を観察する
第2時 いろいろな花の花粉を観察する
第3時 花粉がつかないと実や種はできないのか
第4時 花粉の有無で雌花のもとがどう変化するのか
第5時 おしべとめしべのある花があることを知る
第6時 ほかの花の花粉をつけたら実や種はできるか
第7時 受粉から結実までのしくみをまとめる
Ⅴ 台風と天気の変化
単元のはじめに
第1時 台風の構造と天気を知る
第2時 台風による災害とその原因を知る
第3時 台風の進路と天気の変化を知る
第4時 季節による天気の特徴を調べる
Ⅵ 流れる水のはたらき
単元のはじめに
第1~2時 自分の川をつくろう
第3時 流れる水のはたらきを資料から読み取る
第4時 流れる水のはたらきをもう一度確認しよう
第5時 泥や砂は川のどこに集まるのか
第6時 川のカーブにおける水のはたらきを考える
第7時 水のはたらきによって土地が変化する様子を知る
第8時 河原の石がなぜ丸いのかを調べる
第9時 水による災害を防ぐ工夫を知り,学習したことをまとめる
Ⅶ 人のたんじょう
単元のはじめに
第1時 人は何から生まれるのか
第2時 受精卵が成長していく過程を知る
第3~4時 疑問を解決するための調べ学習
第5~6時 調べた情報を2ページにまとめて発表する
Ⅷ ふりこの運動
単元のはじめに
第1時 ふりこを作って遊ぶ
第2時 ふりこの実験をさらに蓄積させる
第3時 多くの子が発見した法則を検証する
第4時 「往復する時間」を変える方法を考える
第5~6時 仮説が正しいかどうかを検証する
第7時 教師実験で検証する
第8~9時 子供の疑問を解決する
Ⅸ ものの溶け方
単元のはじめに
第1時 「溶ける」という言葉の定義を知る
第2時 「溶ける」ものを探そう
第3時 「溶ける」ものを確認する
第4~5時 食塩は水にどれぐらい溶けるのか
第6時 食塩が水に溶けると,食塩の重さはなくなるか
第7時 水の温度を上げたら食塩はもっと溶けるか
第8時 ホウ酸は食塩と溶ける量が違うか
第9~10時 ホウ酸と食塩の溶け方を比べる
第11時 温度差を利用してホウ酸を取り出す方法を知る
第12時 子供の疑問を追究する
第13時 学習のまとめを行う
Ⅹ 電流が生み出す力
単元のはじめに
第1~3時 電流のはたらきを調べる
第4時 仮説をつくる
第5~6時 導線の曲がったところとまっすぐなところのどちらによく鉄粉が付くのか
第7時 くぎが変わると磁力が変わるか
第8時 電磁石に極はあるか
第9時 巻き方によって極は変わるか
第10時 電流をたくさん流すと磁力は上がるか
第11時 直径の大きなコイルでも磁石になるか
第12時 くぎに電流を流すと磁力は変化するか




