なぜクラスじゅうが理科のとりこなのか
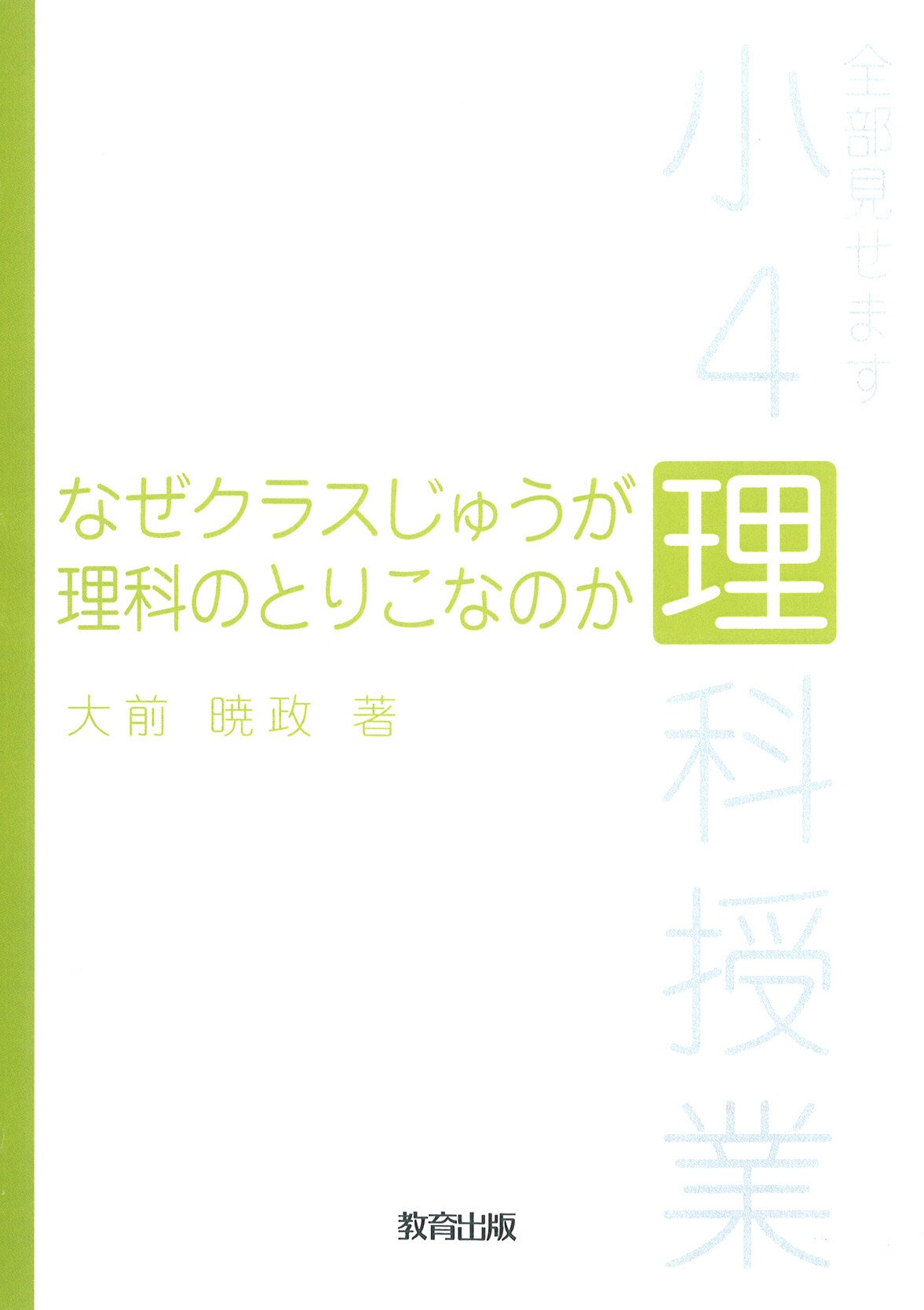
なぜクラスじゅうが理科のとりこなのか 全部見せます小4理科授業
- 大前暁政著
- A5判 並製・カバー装 200頁
- 2013.4.2 発行
- ISBN 978-4-316-80372-2
- 読者対象:小学校教師
商品内容
新学習指導要領に準拠した小4の理科授業を,1年分まるごと収めました。
小学校の先生の半分は理科の授業が苦手,という調査結果があります。
本書は,小4の学習内容にそって発問や課題を1時間ずつ丁寧に紹介しながら,
そんな先生がたが自信をもって実践できる理科授業を提案します。
身につけさせたい知識と技能,指導計画,発問や反応例,実験や観察のコツなどを満載。
クラスじゅうが理科を好きになる,好きになるだけでなく力もついてしまう,
そんな理科授業をお見せします。
大前暁政先生のオフィシャルウェブサイトはこちら!
↓↓
<大前暁政の教育>
http://akimasa.s1007.xrea.com/
目次
目次
0 授業びらきの指導
単元のはじめに
第1時 空気と水の授業
Ⅰ 季節と生物(1)あたたかい季節
単元のはじめに
第1時 フィールドビンゴで春探し
第2~3時 サクラを観察する
第4時 ヘチマの種を観察する
第5~6時 植物を観察する
第7時 花が散ったあとのサクラを観察する
第8時 動物と虫を観察する
第9時 動物と虫の名前を調べる
第10時 ヘチマとヒョウタンの成長の様子を調べる
第11~12時 ヘチマとヒョウタンの植え替えをする
第13~14時 ヘチマとヒョウタンの成長をまとめる
Ⅱ 天気の様子と気温
単元のはじめに
第1時 1日の気温の変化を調べる準備をする
第2時 気温の測り方を確認する
第3時 1日の気温の変化を調べる
第4時 気温のグラフを検討する
第5時 1日の気温の変化を振り返る
Ⅲ 電気のはたらき
単元のはじめに
第1時 電気でモーターを動かす
第2時 電流には向きがあることを知る
第3時 検流計で電流の向きを見る
第4~5時 電気で走る自動車を作って遊ぶ
第6時 回路の作り方をもう一度確かめる
第7~8時 もっと速く自動車を走らせるにはどうするか
第9時 直列回路を知る
第10時 ショート回路と並列回路を知る
第11時 並列回路では乾電池が長もちすることを知る
第12時 光電池でモーターを動かす
第13時 光電池を使ってさらに速くモーターを動かす
Ⅳ 動物のからだのつくりと運動
単元のはじめに
第1時 体に骨があることを知る
第2時 骨の形と役割を知る
第3時 関節の役割を知る
第4時 筋肉が全身にあることを知る
第5時 人体模型で体のつくりと運動の仕方を確認する
第6時 人と動物の体のつくりを比べる
Ⅴ 月と星
単元のはじめに
第1時 星座を調べる
第2時 夏の星を観察する
第3時 月は動くか
第4時 月はどのように動くか
第5時 月の動きの観察結果をまとめる
第6時 星はどのように動くか
第7~8時 星の動き方をまとめる
第9時 冬の星を観察する
第10時 冬の星の動き方を知る
Ⅵ 季節と生物(2) 寒い季節
単元のはじめに
第1時 夏休み明けのヘチマの観察
第2時 秋の動物の観察
第3時 秋のサクラの観察
第4時 秋のヘチマの観察
第5時 冬の動物の観察
第6時 冬の動物はどこに行ったのかを調べる
第7時 冬のヘチマの観察
第8時 冬のサクラの観察
第9時 冬の生き物の様子をまとめる
第10時 見つけられなかった生き物を探しに行く
第11~12時 生き物の1年の様子をまとめる
Ⅶ 空気と水の性質
単元のはじめに
第1時 空気は縮むのかを確かめる
第2時 空気と水の性質を比べる
第3~4時 空気の性質をさらに深く知る
第5~6時 水と空気の性質を利用したおもちゃで遊ぶ
Ⅷ ものの体積と温度
単元のはじめに
第1時 シャボン液を膨らませる
第2時 シャボン液はなぜ膨らんだか
第3時 空気がなぜ膨らんだのかを実験で確かめる
第4時 空気を冷やすと縮むのか
第5時 水を温めると膨らむのか
第6時 水の重さはどうなっているか
第7時 アルコールランプの使い方を知る
第8時 金属を温めると膨らむのか
Ⅸ 水のすがたとゆくえ
単元のはじめに
第1~2時 水を温めるとどう変化するか
第3~4時 水の中から出てくる泡は何か
第5時 水を温めるとどうなるかをまとめる
第6~7時 水を冷やすとどうなるか
第8時 水は自然に蒸発しているのか
第9時 水は何度ぐらいで蒸発するか
第10時 空気中の水蒸気を水に戻そう
第11時 ろうそくは温度によって変化するか
第12時 総復習を行う
Ⅹ ものの温まり方
単元のはじめに
第1~2時 水の温まり方を調べる
第3時 大きな容器で温めると水はどのように温まるか
第4時 さらに疑問を追究する
第5~6時 金属の温まり方を調べる
第7時 金属の板で温まり方を確かめる
第8~9時 空気の温まり方を自由に確かめる
第10時 空気の温まり方を目で見る
第11時 ものの温まり方の総まとめを行う




