教育研究所
№811「桜の楽しみ」
北海道や日本海側に大雪が降っている2月中旬に,もう伊豆半島の河津町のカワヅザクラ(写真1)やアタミハヤザキの開花が伝えられました。3月に入ると紅色のカンヒザクラ(写真2)やカンザクラが咲き始め,もう間もなくソメイヨシノが開花します。ソメイヨシノ(写真3)の桜前線が北海道に達するのは5月上旬ですから,我が国の人々は約3か月間桜の開花や便りを楽しみます。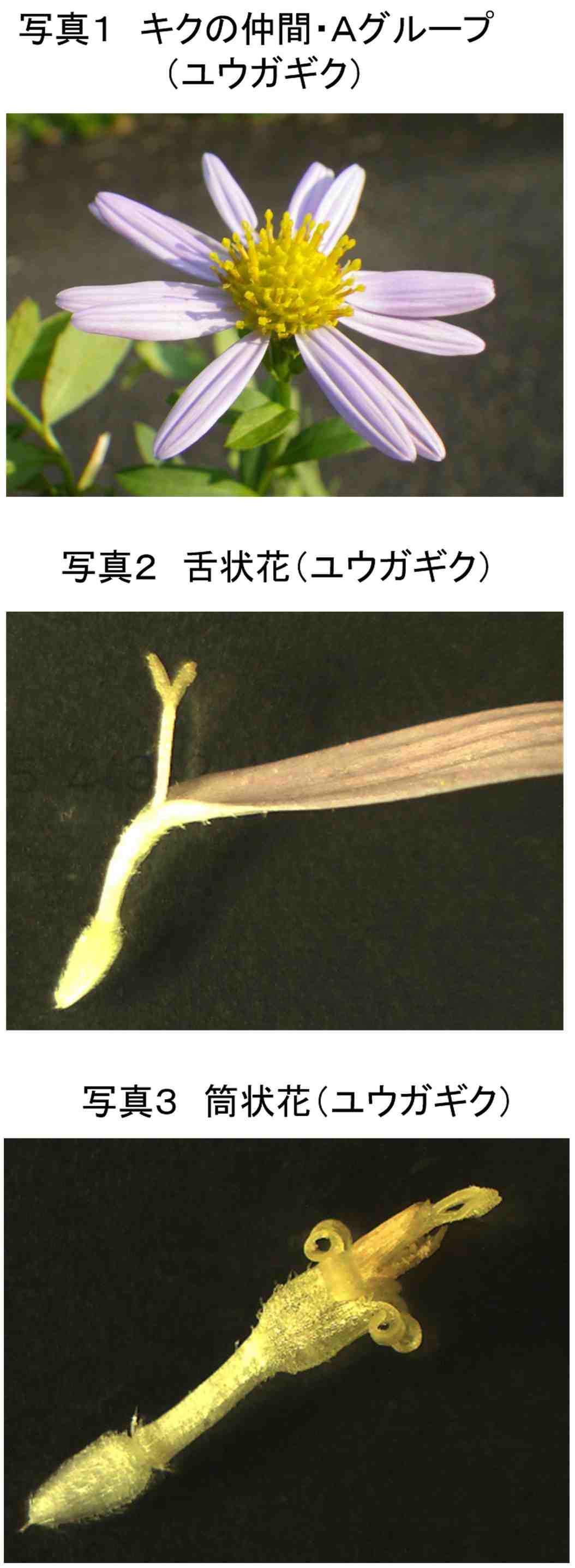

1 日本の桜の野生種
世界のサクラの発生の地は,ヒマラヤ地方(中国南西部)であり20数種があったと言われています。ヒマラヤから西に分布を広げたのがヒマラヤザクラ(写真4)等ですが,春に咲くのではなく秋に開花します。日本で見られるカンヒザクラに似た紅色のサクラです。東に分布を広げて中国経由で日本に達したサクラが,ヤマザクラ(写真5)やエドヒガン等です。日本の山野に自生しているサクラは9種でヤマザクラ,エドヒガン,オオシマザクラ,オオヤマザクラ,マメザクラ,チョウジザクラ,ミヤマザクラ,タカネザクラ,チシマザクラです。皆さんの地元でも数種類は見ることができると思います。

今年の3月13日にもう1種自生のサクラが100年ぶりに発見されたとNHKが放送しました。発見されたのはクマノザクラと命名された,紀伊半島に自生するサクラです。研究し発表したのは東京都八王子市にある森林総合研究所ですが,このサクラが新種として一般に認められると,日本の自生のサクラは10種になります。前の9種が形態・形質を若干変えて変種や亜種等を生み出し20種ぐらいのグループを形成しています。加えて9種が交雑して種間雑種として新しい種を生みだしています。ニッコウザクラ(カスミザクラ×チョウジザクラ)やヤブザクラ(マメザクラ×エドヒガン)等約30種です。以上のサクラは人の手が加わらない,自然の営みにより発生し進化した野生種です。
2 人の手によるサクラ(栽培品種)
現在,サクラは野生種と栽培品種を合わせて200数十種以上あると言われています。その大部分が人の手で作出されるか増殖されたサクラで,この仲間を「栽培品種」と呼び,野生のサクラと区別しています。前に出てきたカワヅザクラやアタミハヤザキ,カンザクラ,ソメイヨシは全て人が作出したか増殖したサクラですので栽培品種になります。植物分類学では,分類体系を完全に分けていて野生種は「国際藻類・菌類・植物命名規約」により命名していて,栽培品種は「国際栽培植物命名規約」により命名しています。
栽培品種は幾つかのグループに分けられますが,最も大きいグル―プはオオシマザクラを片親とする「サトザクラ」と呼ばれるグループです。このグループは八重桜が多く,花弁が5枚,6~10枚,11~20枚,20枚以上等と分けられます。中には100枚を超えるサクラもあります。
日本では栽培品種は何時頃から栽培されるようになったのでしょうか。古い文献に現れるのは平安時代からで「枝垂桜」が最初ではないかと言われています。文献では「糸桜」や「しだり桜」の名称で記述されています。多くの枝垂桜は「エドヒガン」が枝垂れる形になるので,平安時代の「糸桜」や「しだり桜」も,野生のエドヒガンの突然変異型を増殖して庭園や社寺に植えたのではないかと考えられています。鎌倉・室町時代を経て江戸時代にさらに多くの栽培品種が作出・増殖され,庭園や寺社の他に庶民のための桜の名所に植えられました。江戸の名所は墨田堤や飛鳥山,御殿山等ですが,全国各地に名所が設定されたことと思います。ただ,江戸時代の末期までソメイヨシノはありませんでしたので,名所のサクラの主たるものはヤマザクラやオオヤマザクラ,栽培品種等でした。
3 ソメイヨシノの起源
ソメイヨシノの起源については,いくつかの説があります。江戸末期に江戸染井村(東京都豊島区)の植木屋が作出したという説,伊豆大島原産地説,小泉源一博士の済州島原産地説,そして,現在有力な説として伊豆半島でオオシマザクラとエドヒガンが自然交雑してできたとの説です。江戸染井村の植木屋が苗木を売り出したことは確かなようですから,伊豆半島説が有力なら染井村の植木屋が伊豆半島又はその他でソメイヨシノの稚樹を手に入れ,増殖して広めたことになりますが,まだ仮説の段階で今後の検証が必要です。
4 特色ある栽培品種
栽培品種にはソメイヨシノのように美しいサクラがありますが,さらに変わったサクラや豪華なサクラがあり,少し例を挙げてみましょう。
(1)ギョイコウ(御衣黄)とウコン(鬱金)
一つ目は花が八重咲で緑色のサクラです。初めて見た人はその色の異様さにぎょ!としますが,名はギョイコウ(御衣黄,写真6)と言います。花弁の緑色は普通葉にある葉緑体が花弁にもあるという変わった性質が原因です。もう一種花弁が黄色になるウコン(鬱金)というサクラがあります。やはり花弁に葉緑体があるのですが量が少ないので黄色に見えるのです。両者ともオオシマザクラとヤマザクラの雑種ですが,遺伝子を受け継ぐときに突然変異があったと考えられます。もっとも,古生代(約3億年前)において花の全ての部分は葉が変化したものと考えられていますから,花弁が葉のように先祖返りしても不思議は無いのかもしれません。
(2)カンヒザクラ(寒緋桜)
二つ目は緑色のサクラではなく,紅色のサクラのことです。一般にサクラの色はソメイヨシノのようにうすいピンク色が大勢を占めています。いわゆる淡紅色とか淡紅紫色と言われる色のサクラです。ところが,3月初めに開花するカンヒザクラ(写真2)は紅色をしており,サクラとは思えない真っ赤な色です。全ての花が,下向きに垂れ下がるように咲くのも変わっています。このサクラは沖縄原産のように考えられていますが,沖縄に自生地は無いのではないかと疑われ中国や台湾原産説が有力です。戦後このサクラは日本各地に植えられたことから,オオシマザクラなどと交雑し多くの雑種をつくりました。前のカワズザクラやアタミハヤザキ等がこのグループで,ソメイヨシノより一段とピンク色の濃い花色を呈しています。日本のサクラの色を変えたサクラと言えそうです。
(3)ケンロクエンキクザクラ(兼六園菊桜)
三つ目は花弁の数の話です。多くのサクラは花弁が5個ですが,増え続けてとうとう100~300個に達した種があります。ケンロクエンキクザクラ(兼六園菊桜,写真7)と言うサクラで,名前の通り石川県金沢市の兼六園に原木があったそうです(1970年に枯れ死し接ぎ木により増殖)。1865年ごろ孝明天皇から前田家に下賜されたとのことですから,約150年前にすでに花弁が300個のサクラを栽培していたことになります。八重咲の花弁は雄しべが変化して花弁化したものですが,普通雄しべの数は25~30個ですから300個の花弁はどのようにして増えたのでしょうか。
上記のようにサクラを楽しんできましたが,学校では樹木の成長,変化を観察する教材としてサクラは大変適しています。特に小学校4学年や中学校1学年の植物教材として扱ってはいかがでしょうか。 (Y・H)
(2018年3月26日)





