第1回 「あぁ! 学級崩壊!」
―私が学んだもの― ①
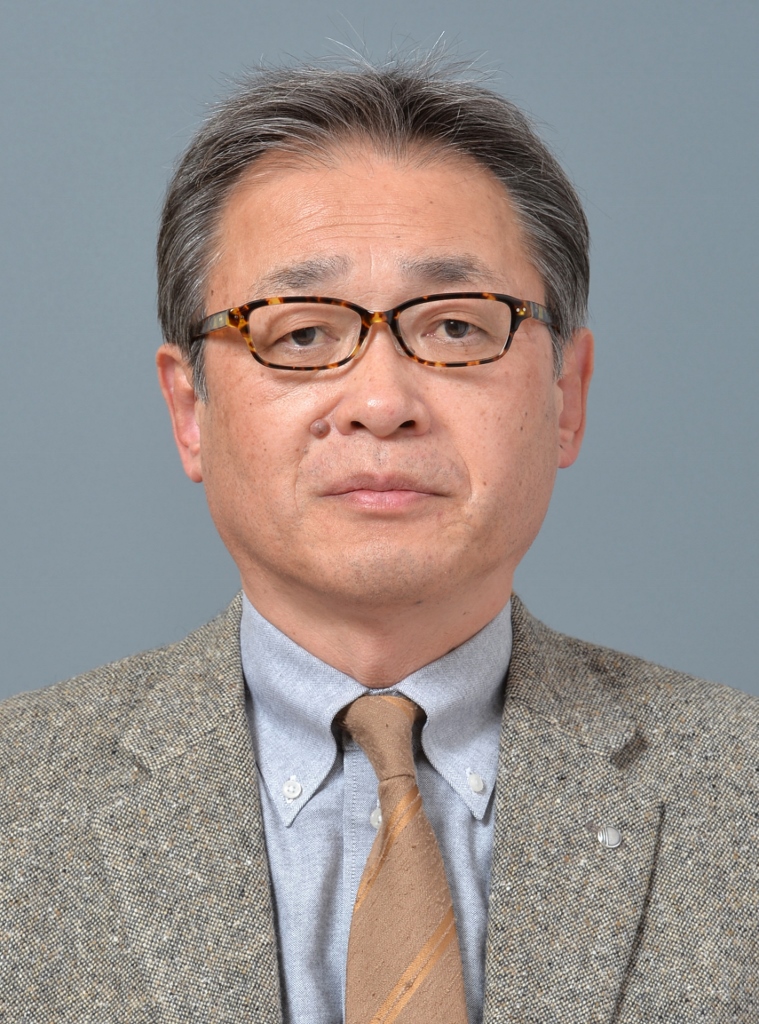 |
神奈川大学人間科学部 非常勤講師 |
私は、学校現場で奮闘されている皆さんの力に少しでもなれるように、この連載で話題を提供しながらともに学んでいく場にしたいと思っています。
最初に自己紹介をします。私は、横浜市の中学校に初任教員として着任し、以来22年間教諭を務めました。その後は横浜市教育委員会で生徒指導担当の課長・部長、教育センターの所長等を務めました。中学校と高校の校長の経験もあります。2012年以降は大学教育に携わり、玉川大学、神奈川大学、大正大学などで教員養成と研究に取り組み、現在も授業や研究活動、講演や執筆活動を続けています。
初任教員以来の長い職歴を振り返ると、それぞれの現場で直面するさまざまな課題や困難の連続でした。そのなかで私は二つのことを継続しました。「常に問題意識を持ち続けること」「常に打開策を暗中模索し続けること」です。それはなま易しいことではなく「葛藤・模索・対立・対決・挫折・妥協・自信喪失」がありました。しかし、一方で貴重な「出会い・仲間・組織力・課題克服・成就」を私にもたらしました。この経過なしに現在の私は存在していません。職業人であることは、学びと成長をもたらすのです。
今回と次回の2回にわたって、この葛藤・模索の日々から、私が"学級崩壊"した経験を話題提供します。それは教員7年め、異動したY中学校の1年生の担任の時でした。初任校X中学校の6年間で、私は授業も学級経営も楽しく行い、生徒会も学校行事も任せられるほど"実力"を付けたつもりでした。異動したY中学校でも同様に活躍するはずでした。しかし、夏休み明けから私の学級は崩壊しました。4人の男子生徒を中心に担任への反発が激しくなり、授業も学活も大騒ぎ、注意すれば反発、威嚇に暴力、他の生徒もおもしろがって盛り上がります。授業中、おもちゃの自走するミニカーでレースごっこ、さらには私に向けて火のついた雑巾や水風船が飛んできます。帰りの学活に行くと生徒は皆勝手に下校していて、教室は椅子と机がすべて投げられ、ピラミッドのようになっていました。保護者からも学級運営を糾弾される状況になります。退職も考えました。
なぜ、こうなってしまったのか。その答えがやがて私にも見えるようになります。その生徒たちが私を理解してくれて"和解"が成立し、私は立ち直ります。次回、私に見えた"答え"についてお話しします。ともに教師の在り方を考えていきましょう。
【著者プロフィール】
神奈川大学人間科学部 非常勤講師(教職課程)。北里大学保健衛生専門学院 非常勤講師。専門分野は、生徒指導論、教職論、学校経営論、情報メディア論、教育相談。
【略歴】
22年間、横浜市立中学校3校で教諭として(うち8年間は生徒指導専任教諭として)勤める。その後、横浜市教育委員会指導主事、同市立中学校校長、横浜市教育委員会児童・生徒指導担当課長及び部長、横浜市教育センター所長を経て、横浜市立南高等学校校長を務めた。2012年以降は大学教育に携わり、玉川大学教職大学院准教授、同教授、神奈川大学・大正大学等で非常勤講師を務め、2018年から神奈川大学人間科学部特任教授を務め、2022年3月定年退職し、現職。
【著書】
「実践 教職論 ―未来の創り手となる子どもたちのために―」(ナカニシヤ出版)、「モバイル社会を生きる子どもたち-『ケータイ』世代の教育と子育て-」(時事通信出版局)、「子どもの危機と学校組織 ―苦悩する学校を救う鍵は教師の生徒指導力向上とチーム力」(教育出版)




