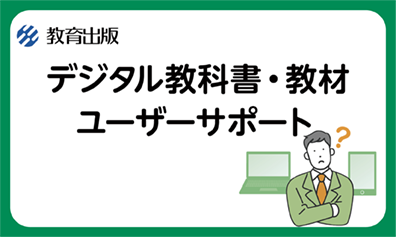第1回 「できなさ思考」の落とし穴
広島大学大学院人間社会科学研究科准教授
久しぶりに会ったカトウ先生はなんだか浮かない顔です。
カトウ先生:ううん......。
ハヤシさん:どうしたのカトウさん。浮かない顔して。
カトウ先生:いや、今年さ、新しいクラスにベトナムから子どもが来ることになったんだよ。そういう話は聞いたことあるけれど、僕がいる学校はそんな都会の学校じゃないし......。ハヤシさんは大学院で今そういうこと勉強しているんだよね? ちょっと相談に乗ってほしいんだ。
ハヤシさん:ああ、なるほど。最近よくニュースでも見るようになったね。先輩に経験がある人はいないの?
カトウ先生:先輩もあまり経験がないみたいなんだ。
ハヤシさん:そっかあ。どんなことに困っているの?
カトウ先生:もうそれはいっぱいあるんだけど、やっぱりさ、まだ日本語ができないらしいんだよね。どうしたらいいんだろうって。
ハヤシさん:そうだよねえ。日本語指導のようなことはできないの?
カトウ先生:今、校長先生が市の教育委員会に相談をして、誰かいないか探してる。
ハヤシさん:うまく見つかるといいね!
カトウ先生:そうなんだ。でも心配なのはさ、その子が何を考えているのか知りたいし、伝わっているかどうかとか、あと、不安じゃないかとか。
ハヤシさん:そうだね。言葉がわからないと、考えていることや困っていることがこっちも見えにくいし、心配になるよね。
カトウ先生:そうなんだよ。学力面も心配になって......。
ハヤシさん:あ、でも、「日本語ができない」ということと「学力が低い」ということは一緒ではないんじゃないかな?
カトウ先生:そうか、確かにね。
ハヤシさん:私たちって、日本にいると日本語だけできれば困らないから見えにくいけど、日本語ができないことは決して「何もできない」ということではないもんね。その子には母語だってあるし、考えだってあるしね。
カトウ先生:そうかあ。確かに。そういう視点で考えることって大事だよね。
外国につながる子どもに関わる教育の話は「現代の教育課題」のように語られることが多くあります。
しかし、2人の会話にあるように、外国につながる子どもたちがたとえ「日本語ができない」と見えるからといって、それをなんでもかんでも「できなさ」と結びつけてしまうことは早計かもしれません。
これはなにも外国につながりをもつ子どもたちだけの話ではありませんが、子どもをまなざすときには、「できなさ思考」でどうしても捉えてしまいがちです。しかしここには大きな落とし穴があります。
「できなさ思考」とは、いわば「欠損的発想」です。私たちはついつい子どもたちの「できない」ことに着目しがちです。しかしそれは焦りとプレッシャーを教師自身にもたらし「できない......だからせめてこれだけは」という気持ちになりやすく、子どもたちに対しても、それを示してしまうことも多くあります。配慮に満ちた考えともいえますが、一方で、漢字の書き取り、計算ドリル、語彙の書き取り、文法プリントのような基礎基本の繰り返しばかりに陥ってしまい、子どももいつしか「学ぶことのおもしろさ」からも「教室で目ざされていること」からも遠ざかり、つまらなさのスパイラルにはまり込んでしまうことも多く見受けられます。
必要なのは、勇気をもって「のびしろ思考」(資本的発想)で考えることなのでしょう。子どもたちは実はいろいろな「資本」をもっています。例えば日本とは異なる社会や文化につながる言葉や文化(いわゆる母語や母文化)とつながっていること、そうした世界とのつながりの中で、さまざまなものの見方・考え方をもっている可能性もあること、将来につながる人間関係や社会関係のつながりをもっていることなどがあるはずです。ただ、こうした、いわば子どもたちのもっている「武器」を見すえていこうとする視点は、あまり外国につながる子どもたちに関わる報道では出てくることがありません。でも、視点として重要です。「この子、こんないいものをもっている!」という考え方は、その子自身がまだ気づいてない可能性や「資本」に気づかせていくことでもあります。そうした積み重ねが、自信をもって可能性を実現していく力にもつながります。そうした「のびしろ思考」で子どもを伸ばしていくために何が必要か。それを見すえたうえで外国につながる子どもたちの教育も考えていけたらと思います。
カトウ先生とハヤシさんの会話をとおして、それを見つけていきましょう。
【著者プロフィール】
言語的文化的に多様な子どもたちをめぐって、ことばと文化の共生の点から力のある授業と学校をデザインしていこうとする教師教育の仕事をしています。