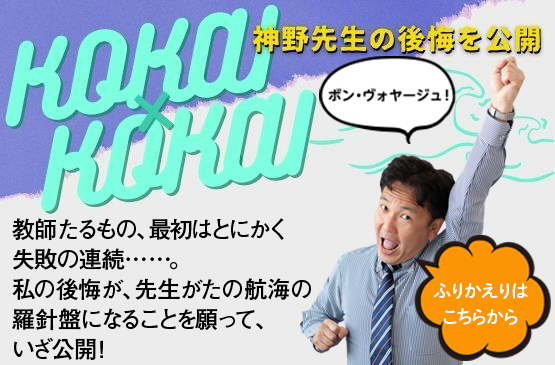最終回 神野先生から先生がたに伝えたいこと
香川大学教育学部准教授
神野先生が約1年にわたった連載にこめた思いと、改めて先生がたへ伝えたいことをお聞きしました。
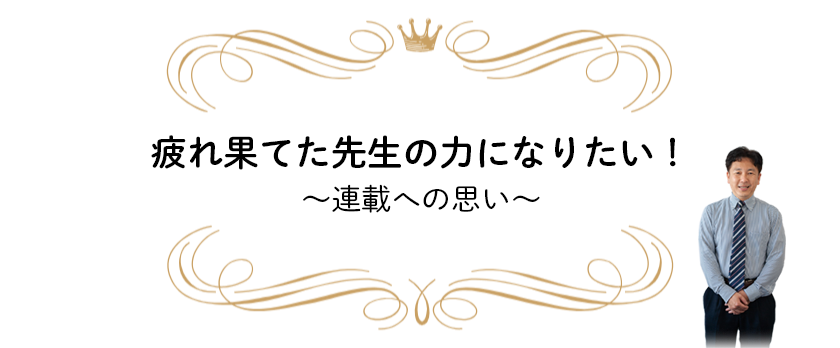
20本の連載企画を始めたきっかけは、子どもたちと過ごす先生がたはとても忙しく、平日に教育書などの本を読む時間がとれないという実態があったからでした。私自身も同様で、学級担任時代はトイレに行く暇もなかったほど多忙でした。
ある時、東京にある大型書店の教育書コーナーを訪れた日のことです。私が教職をスタートさせた二十数年前と比較して、教育書のコーナーが4分の1になっていることに気づきました。新規採用者が増えている中、むしろ教育書のコーナーは面積が増えるはずなのに、反比例しています。実際に月刊誌が隔月になったり、廃刊になったりと、教育書や授業関連の本を手に取る機会が減っています。紙の書籍ではなく、デジタル媒体で情報を入手しているのかもしれませんが、やはり、先生がたの日常が忙しく、本を読みたいのに読む時間がとれないのだと推察しています。そのような状況が 少しでも解消できればと思い、朝の通勤時や放課後の職員室など、3分程度で読める記事を届けられないだろうか、というのがそもそもの発想でした。
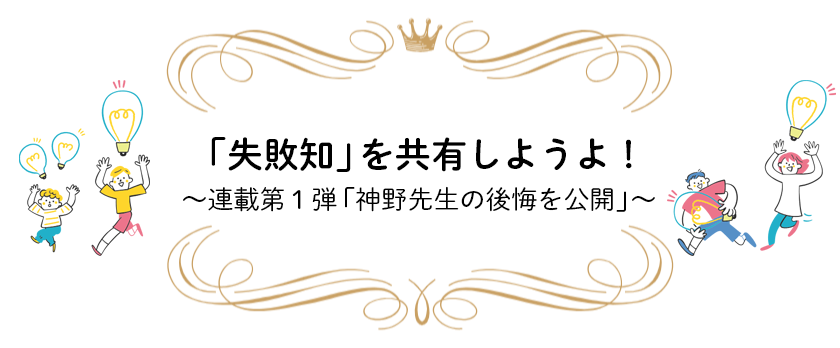
前半の連載は「私の失敗を公開する」というものでした。教育界は、失敗を公開して共有するということをほとんどしていません。公開研究会なども、成功した授業の報告がメインです。でも、その成功の陰には、多くの試行錯誤と失敗とがあったはずです。私の問題意識はそこにあります。うまくいかなかった授業という「失敗知」も、後続の授業者には有益だと考えています。
私たち「先生」とは、「先」に「生」まれた人であり、先に多くの失敗をした人です。でも、プライドが邪魔をするのか、自分の失敗を後輩に語ってくれる先輩は多くありません。懇親会など、フランクな場所での失敗知の共有や伝達も、最近は少なくなっています。後輩は、同じ失敗をする必要はないのです。「失敗知の共有」というものが広がると、教育界はさらに一歩前進すると思っています。私の失敗が少しでもお役に立てればありがたいです。
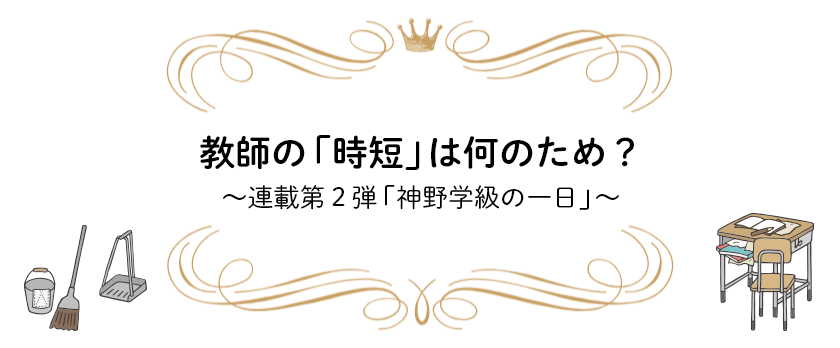
後半の連載「神野学級の一日」で取り上げた、時短のコツや微細な指導技術も、結局のところ、目的は、教師が子どもたちと関わる時間を増やすことであり、落ち着いた学級経営をしてほしいからです。若手の教師にとって学級経営は、最初は難しく感じるかもしれませんが、いくつかのポイントを意識することで、確実によい方向に導くことができます。やはりいちばんの基本は、子どもたち、さらには保護者との信頼関係を築くことです。そのためには、子どもたち一人一人に関心をもって様子を深く観察し、話をよく聞くことがポイントになります。ちょっとした声かけや気配りが、子どもたちにとっては「先生は自分を大切にしてくれている」、保護者にとっては「先生は、自分の子どもをよく見てくれている」という安心感につながり、結果的に信頼関係が深まります。
私も先輩に「クラス全員と一人一日一回は会話するとよい」と教わったことがありますが、手のかからない落ち着いた子とは、意識をしないと数日間、会話をしないということもありました。子どもたちとの日々のコミュニケーションを大切にしましょう。コミュニケーションを深めて一緒に活動すると、とても多くのことに気づけるからです。そのために私は、掃除の時間などにテストや宿題の採点をすることは避けてきました。
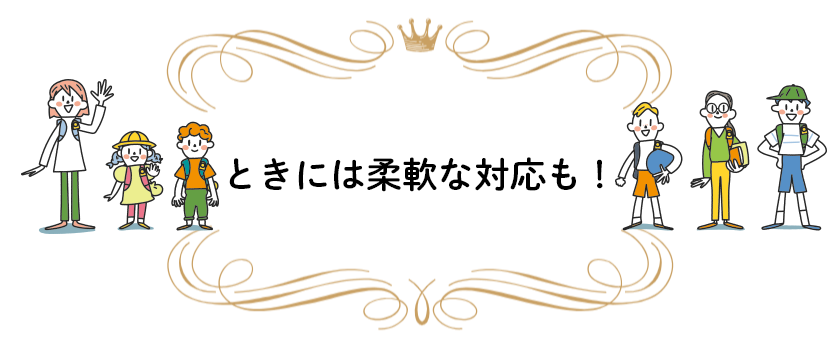
学級経営には明確なルール設定が欠かせません。最初にクラスのルールをしっかり伝え、それを一貫して適用しましょう。ルールは、シンプルでわかりやすく、子どもたちが理解しやすいものにすることが大切です。そして、全ての子どもたちに公平に適用することが、学級の秩序を保つポイントです。それと同時に、柔軟な対応も必要になります。子どもたちには一人一人個性があり、クラスの状況も刻々と変化していきます。ときには個別に対応したり、クラス全体の状況に応じて方針を見直したりすることも求められます。特定の子が困難を抱えている場合には、その子に対してのサポートや励ましを加えることが、クラス全体の雰囲気をよくすることにつながることもあります。
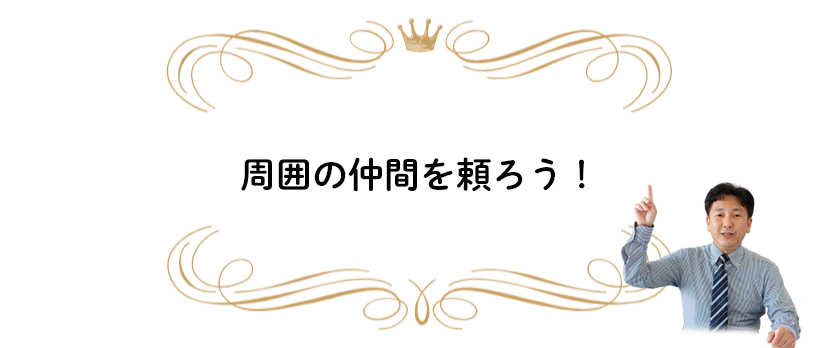
最後に、他にも皆さんにお伝えしたいポイントを、いくつか書きます。
まず、先生がたご自身の成長を忘れないことです。そのためには毎日の振り返りが重要です。何がうまくいったのか、改善点は何かを考え、必要に応じて指導方法を改善していきましょう。また、先輩や同僚からアドバイスをもらうことも非常に有効です。教育は一人で行うものではなく、学校全体で支え合いながら進めるものです。困ったときには、ぜひ他の先生に相談をしてください。周囲には多くの知識や経験をもった教師がいます。困ったことや悩みがあれば、一人で抱え込まずに、気軽に相談することをお勧めします。他の先生と情報や意見を共有することで、より効果的な方法を学ぶことができます。自分自身だけでなく、チームとしての力を活用していくことが、学校全体の雰囲気をよくし、学級経営や授業の質向上にもつながります。
次に、そのうえでご自身のストレスケアも忘れないでください。教師の仕事は多くの責任を伴い、大きなプレッシャーを受けることがあります。ストレスをため込まず、自分なりのリフレッシュ方法を見つけておくことが大事です。例えば、趣味を楽しむ、友人や家族と過ごす、軽い運動をするなど、仕事以外の時間をうまく活用して心身をリフレッシュする習慣をもちましょう。メンタルケアは、教師のパフォーマンスにも直結します。 日々の業務は多忙ですが、これらのポイントを意識しながら過ごすことが、教師としての成長はもちろん、健康的な働き方を実現することにつながります。
教師生活は長く、持久走のようなものです。焦らず、無理をせず、自分を大切にしながら日々の研鑽を積み重ねていってくださいね。「無事これ名馬」です。
※バックナンバーは、下のバナーをクリックしてご覧ください。
【著者プロフィール】
東京都小学校、広島大学附属三原小学校等を経て現職。小・中学校の先生がたと社会科、総合的な学習の時間、生活科の授業づくりにともに取り組んでいる。