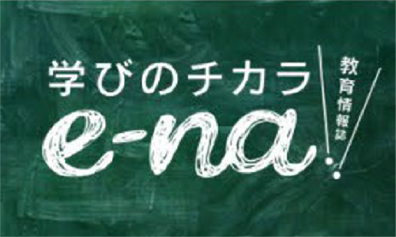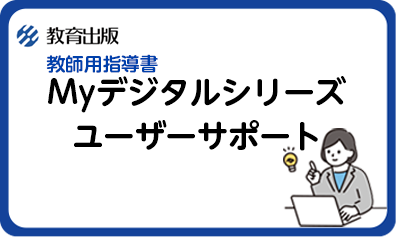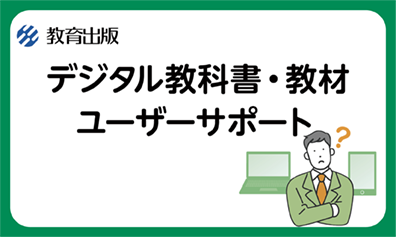私たちの実践・研究
第1回
すすんでコミュニケーションを図ろうとする児童の育成
~校内研修を核とした取組の工夫~
1 はじめに
本校は,群馬県高崎市の北部にあり,校区内には大型ショッピングセンターを抱えています。平成30年度は24学級,610名の児童でスタートしました。
高崎市においては,平成28年度から市内全58小学校が教育課程特例校に指定され,1年生から外国語活動を実施し英語にかかわる授業時数を増やしたり,ALTを全小中高校に1名ずつ配置したりするなど,英語教育に力を入れています。
また,平成29年度には全県で12名のEAT(英語教育アドバイザー教員)の配置がありました。うち1名が本校に配属され,校内研修も英語教育を中心に据えました。ささやかではありますが,本校の平成29年度の主な取組を紹介してまいります。
2 研修の取組について
(1)授業モデルの共有化
HRT(学級担任)がALTと授業を進めていくにあたっての課題として,HRTが授業のイメージを十分にもてていないことから,自分が中学校時代に受けてきたような文法説明や訳読中心の授業になってしまわないようにすることが大切と考えました。そこで,まずはEATが,その役割の一つである「先生方のモデル」になって,ALTと授業を行いました。
成果として,T1としてのHRT,T2としてのALTの役割を先生方がしっかりと理解できたことや,T1とT2のデモンストレーションの仕方などについて,学べたことが挙げられます。
(2)教材作成・整備・管理の工夫
授業で使用する絵カードや単語カード,黒板への掲示物などを学年ごとに作成し,学年ごとの手提げかごに授業で使用する道具をセットで入れるようにしました。HRTがそのかごをもって教室に行くだけでよいのです。
また,ALTと協力して,校内での掲示物を作成し,いつでも児童が英語に触れられる環境をつくりました。

校内の英語掲示物の例。「ウィークリーイングリッシュ」(今週の英語表現)やALTによる文化紹介なども。



子どもの目にいつでも触れられるよう,階段にはアルファベットや月の名前,国名などを書いたカードを掲示。
(3)「一人1授業」の公開をめざして
校内研修の取組の「一人1授業」として,HRT全員がALTとのティーム・ティーチング(TT)を行い,授業研究を深めました。
先生方は,校内であるとはいえ,苦手な英語の授業を公開し,各授業でよくできているところと修正点を確認することで,授業をすすめる自信をもつことができました。
1月には,直山木綿子教科調査官を迎え,市内に向けて公開授業と講演会を開き,調査官からご指導を受けることができました。


HRTとALTのTTによる公開授業の様子。直山教科調査官に見ていただきました。
(4)児童に伝えたコミュニケーション・ポイント
授業の中でコミュニケーションを図る活動をする際,児童に大切なポイントを伝え,毎回確認しました。そのポイントは,低学年と高学年で少し異なりますが,次のとおりです。
Smile Clear Voice Listen Carefully
Eye Contact Gesture Response (Responseは高学年のみ)
この取組によって,児童には,笑顔で相手の目を見ながら,よく聞き,はっきり伝えるような姿が見られるようになりました。

2年生の外国語活動より「サイモン・セッズ」の活動中。
3 ALTとの協力体制を整える
(1)打合せ時間の確保の工夫
ALTの勤務時間が教員より短いため,打合せ時間を確保できるように,ALTの勤務開始の時刻を教員より遅らせて,勤務終了の時刻を揃えるようにしました。
また,学年ごとに打合せの曜日を決めるとともに,低学年は5時限終了後に打合せをすることにより,放課後の時間に高学年の打合せをすることが可能になりました。
(2)英日版の指導計画を共有
指導計画というと,通常は日本語版のみですが,指導歴の長いALTが日本語から翻訳した英語版の指導計画が作成され,市内の全ALTに配布されています。従って,HRTとALTの打合せにおいても,同じ内容の指導計画で確認ができ,スムーズに授業の準備ができています。
4 児童の変容について~教員の工夫で英語好きな児童を育成~
年度始め(6月)と年度末(2月)で,全児童にアンケート調査を行い,研究前と研究後の児童の変容を見ました。
各項目とも概ね増加,または横ばい傾向でしたが,特に1年生の「英語の学習は大切だ」,「英語の授業の内容がよくわかる」では,10%の上昇がみられました。「英語の学習は大切だ」の項目は,他学年でも上昇しています。特に3年生~6年生では,「英語の学習は大切だ」の項目で,「全くそう思わない」という児童は0%でした。また,4年生では,「英語の授業は好きです」との回答が100%でした。
以上から,学校全体で英語教育に取り組んだことで,児童もその大切さを認識しているということがわかりました。また,教員が授業研究をし,工夫をしていることが英語好きな児童を育てていることも明らかになりました。
授業中,黒板に掲示している授業の流れの例(5年生)。児童が先を見通して授業を受けられるようにするための配慮で,先がわからないと不安になりがちな児童にも有効。
5 おわりに
わずか1年間の研究でしたが,先生方が一生懸命に協力しながら取り組み,児童の変容を見とることができました。そして,英語の授業に自信をもてるようになってきました。今後は,ALTとのTTをさらに充実させ,英語が好きで,コミュニケーションに意欲のある児童をさらに育てていきたいという思いでいっぱいです。