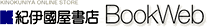特別支援教育への招待 [改訂版]
特別支援教育への招待 [改訂版]
- 宮城教育大学特別支援教育講座 編
- A5判 196頁
- 2019年10月 発行
- ISBN 978-4-316-80415-6
- 定価 (税込) 2,420円(本体 2,200円+税)
- 読者対象:教師・学生
商品内容
特別支援教育の原理,および障害児の理解と支援について解説した基本テキスト。初版を全面改訂。
目次
【Ⅰ 特別支援教育の基礎】
[1章 特別支援教育の原理]
1.現代的な障害観
(1) 障害とは
(2)「ICIDH」から「ICF」へ
(3) ノーマライゼーションとインクルージョン
2.特別支援教育とは
(1) 特殊教育とは
(2) 3つの「特別な指導の場」
(3) 特殊教育から特別支援教育への転換
(4) 特別支援教育とは
(5) 特別な教育的ニーズ(Special Education Needs)とは
3.特別支援教育を推進するための仕組み
(1) 特別支援教育を支える3本の柱
(2) 小・中学校等における特別支援教育の推進
4.共生社会に向けた「インクルーシブ教育システムの構築」へ
(1) インクルーシブ教育システムの構築
(2) 就学先を決定する新たな仕組み
5.学習指導要領等の改訂について
(1) 学習指導要領等の改訂の方向性
(2) 特別支援学校の教育課程への新学習指導要領の導入
【Ⅱ 特別支援教育の実際】
[2章 視覚障害児の理解と支援]
1.視覚障害とは
(1) 学校教育における視覚障害
(2) 見えにくさの程度
2.視覚障害教育の実際
(1) 学びの場
(2) 学ぶ道具
3.覚えておきたい視覚障害児の発達を促す主な教育課題
(1) 乳幼児期からの早期支援の重要性
(2) 視覚障害教育の根幹をなす「イメージ操作」を高める指導の重要性
(3) 空間イメージの広がりを支援する指導の実際
[3章 聴覚・言語障害児の理解と支援]
1.聴覚障害とは
(1) はじめに
(2) 音の性質と会話域
(3) 聴覚障害
(4) 聴力検査
2.聴覚障害教育の実際
(1) 早期発見・早期支援
(2) 初等教育・中等教育
(3) 高等教育
3.言語障害とは
(1) はじめに
(2) 言語障害の捉え方
4.言語障害教育の実際
(1) 構音障害
(2) 吃音
(3) 言語発達遅滞
(4) 音声障害
(5) おわりに
[4章 知的障害児の理解と支援]
1.知的障害とは
(1) DSM-5(アメリカ精神医学会の診断統計マニュアル)の定義
(2) 米国知的・発達障害協会(AAIDD)の定義
(3) 文部科学省の定義
(4) 知的障害の実態把握
2.知的障害教育の実際
(1) 障害特性を踏まえた教育的対応の基本
(2) 連続性のある学びの場
(3) 知的障害の教育課程の特徴
3.知的障害教育の展望と課題
4.学習指導要領等の改訂の要点
(1) 知的障害のある児童生徒のための各教科の改善と充実
(2)「学びの連続性」を意識した教育課程
[5章 肢体不自由児(重度・重複障害児を含む)の理解と支援]
1.肢体不自由とは
(1) 肢体不自由の定義
(2) 肢体不自由の範囲と程度
(3) 肢体不自由児の分類と代表的疾患
2.肢体不自由児教育の実際
(1) 肢体不自由教育における教育の場と教育内容
(2) 肢体不自由のある子どもの特性と困難の理解に基づく支援の考え方
3.重度・重複障害とは
(1) 重度・重複障害の定義
4.重度・重複障害児教育の実際
(1) 状態像の把握と支援の在り方
(2) 教育支援における視点
(3) 医療的ケアについて
[6章 病弱児の理解と支援]
1.病弱とは
2.病弱教育の実際
(1) 生活規制の難しさについて5
(2) 自分の病状を知る難しさについて8
(3) 年齢とともに変わる病気との関わりについて
(4) 教育的支援のポイントについて
(5) 特別支援教育の中の病弱教育
[7章 発達障害児の理解と支援]
1.発達障害とは
(1)「軽度発達障害」から「発達障害」へ
(2) AD/HD
(3) 高機能自閉スペクトラム症
(4) 学習障害(Learning Disability)
2.発達障害教育の実際
(1) 通常の学校・学級
(2) 通級による指導
(3) 特別支援学級
(4) 特別支援学校
3.発達障害児に対する指導・支援のポイント
(1) 二次障害の理解と支援
(2) 共生を目指した学校集団での支援のポイント
【Ⅲ 特別支援教育の応用】
[8章 疑似体験から考える合理的配慮]
1.障害の疑似体験
(1) 疑似体験とは
(2) 疑似体験から考える合理的配慮
2.疑似体験の実際
(1) 視覚障害の疑似体験
(2) 聴覚障害の疑似体験
3.その他の留意点等
(1) 安全と衛生の管理
(2) 当事者の活用
[9章 個別の教育支援計画・指導計画]
1.“個別の計画”の作成と活用
(1) 作成作業の前に行うべきこと
(2) アセスメント(実態把握)
(3) 目標の設定
(4) 具体的な支援内容の決定
(5) 活用と評価
2.知能・発達検査によるアセスメント(実態把握)
(1) ビネー式知能検査
(2) ウェクスラー式知能検査
(3) 発達検査
(4) 知能・発達検査から得られる情報
(5) 知能・発達検査の留意点
3.記録の集積と分析
(1) 時間の壁と要因の複雑さ
(2) コンピュータの活用
(3) 画像の利用
(4) 主観の大切さとデータによる補完
[10章 特別支援教育におけるICT・AAC の活用]
1.情報・通信技術の活用
2.AT・AACの選択
(1) スイッチ類
(2) コミュニケーション支援機器
(3) パソコン・タブレットの活用
3.導入にあたっての課題
4.実際の活用事例
(1) AAC(50音表,表情カード,VOCA)及びパソコンの活用事例
(2) AAC(スイッチ:ルールの認識と動作の統合)
(3) ICT(タブレット端末)の活用事例
(4) 視覚障害児のためのICT の活用
[11章 障害児・者の福祉と支援]
1.障害者福祉のあゆみ
(1) 戦前から戦後にかけての障害者福祉
(2) 国際障害者年とその影響
(3) 障害者権利条約とその影響
2.障害児・者福祉の制度
(1) 障害者手帳制度
(2) 年金・手当について
3.障害児・者の生活環境
(1) 福祉用具の活用
(2) アクセス権の拡大
[12章 適応困難と教員のカウンセリングマインド]
1.学校適応をめぐる問題と背景
(1) 教育相談とスクールカウンセリング
(2) 不登校やいじめの実態
(3) 学校適応に影響する背景的要因
2.カウンセリング
(1) カウンセリングの考え方
(2) 教員とカウンセラーの専門性と支援方法の特徴
(3) 指導的サポートとカウンセリング的サポートとのバランスと使い分け
(4) カウンセリング的サポートの注意点
3.支援の実際
(1) 実際の対応方法
(2) 支援の取り組みにおける基本的視点
ご購入方法
ご購入希望の際は,お近くの書店にご注文下さい。
また,この本は,下記のオンライン書店でもご購入いただけます。
送料・お支払い方法等につきましては,各オンライン書店のホームページをご参照下さい。