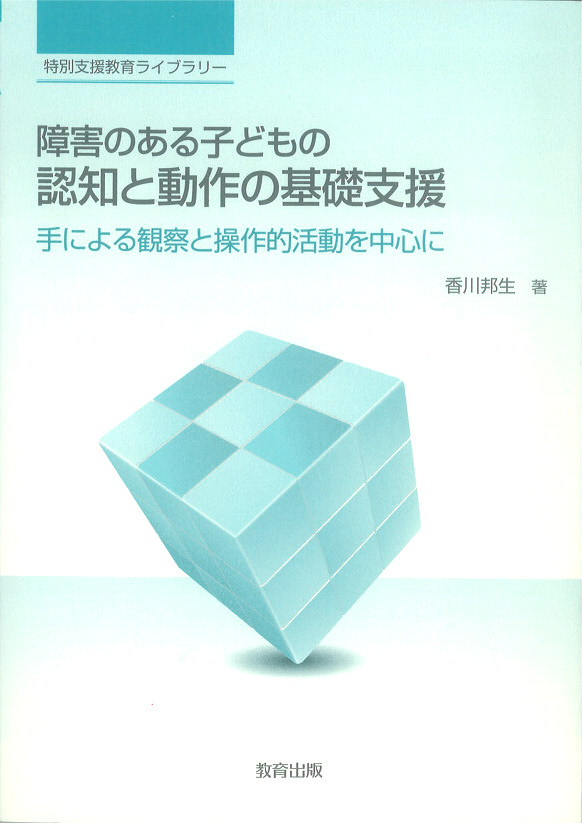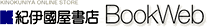障害のある子どもの認知と動作の基礎支援
特別支援教育ライブラリー 障害のある子どもの認知と動作の基礎支援 手による観察と操作的活動を中心に
- 香川邦生著
- A5判 並製 160頁
- 2013年10月 発行
- ISBN 978-4-316-80395-1
- 定価 (税込) 2,640円(本体 2,400円+税)
- 読者対象:特別支援学校教師
商品内容
子どもの身のまわりにある様々な形のイメージづくりや空間の概念形成の過程を,手による探索活動を中心課題にすえて丹念に経験させるプログラムを紹介。視覚に障害のある子どもだけでなく,障害のない子どもの支援にも活用できる。
視覚障害児など外界からの情報収集・活用に関して不利がある子どもたちに,操作的活動等を通してイメージづくり・概念形成の支援をするためのプログラム。現場での実践に基づく具体的な方法が満載。
目次
序章 認知と動作の基礎支援への思い
1 私と「自立活動」領域との出会い
2 盲児の発達は遅れるのか
3 「空間に関する情報の障害」の改善
第1章 認知と動作の基礎支援の意義
1 認知と動作の基礎支援とは
2 認知と動作の基礎支援の位置づけ
(1) すべての子どもに大切な認知と動作の基礎支援
(2) 人間発達の筋道の共通性
(3) 内容を吟味する視点
3 認知と動作の基礎支援の内容選定の観点
(1) 認知と動作を一体としてとらえることが大切
(2) 必要な特別な支援の場の設定
(3) 核になる経験の重視
(4) B型タイプの核になる体験
第2章 プログラム作成に向けての検討
1 プログラム作成に当たっての原則
2 弁別・尺度化・標識化
(1) 弁別の学習
(2) 尺度化の学習
1)名義尺度
2)序数尺度
3)距離尺度
4)比例尺度
5)生活に役立つ尺度の導入
(3) 標識化の学習
3 学習を構成する領域の構造
第3章 認知と動作の基礎支援の学習プログラムⅠ―モノの属性の認知を中心に―
1 手指の操作技能の学習
(1) 学習の位置づけとねらい等
(2) 手指の基本的操作技能の内容
(3) 支援や指導を進める上でのいくつかのヒント
1)乳幼児期において手指を活発に動かすようにするための工夫
2)なでたりたどったりする運動を誘発するための工夫
3)直線運動を誘発するための工夫
4)円運動を誘発するための工夫
5)遊具や道具等を用いた遊びの促進
2 モノの属性の弁別と尺度化の学習
(1) 学習の位置づけとねらい等
(2) モノの属性の弁別と尺度化の学習内容
1)属性に着目した一対一対応の見本合わせ
2)基本形に着目した一対一対応の見本合わせ
3)属性に着目した複数のモノの一対一対応
4)基本形に着目した複数の形の一対一対応
5)基本的な概念形成
6)食べられるモノと食べられないモノ
7)食べ物の種類による仲間分け
8)機能による仲間分け
9)相似な基本形の仲間分け
10)材質に着目した仲間分け
11)材料に着目した仲間分け
12)一つの属性に着目した順序づけ
13)二つの属性に着目した順序づけ
14)身近な具体物を基準とした測定
15)竹ひごによる長さの関係の理解
16)客観的な基準による距離尺度の再構築
17)広さの概算
18)重さの保存
(3) 支援や指導を進める上でのいくつかのヒント
1)子どもの実態に応じた指示の出し方の工夫
2)効率的な分類整理のための枠づくりの工夫
3)試行錯誤から効率的な活動への深化を大切に
4)明確な概念に裏づけられた名称の付与
第4章 認知と動作の基礎支援の学習プログラムⅡ―身のまわりのモノの形のイメージづくりを中心に―
1 学習の位置づけとねらい
2 身のまわりのモノの形のイメージづくりの学習内容
(1) 丸・三角・四角(基本形)などのイメージづくり
1)基本形に着目した仲間分け
2)同系列の基本形に着目した仲間分け
(2) 基本形態のイメージづくり
1)合同な基本形態の一対一対応
2)相似な基本形態の一対一対応
3)合同な基本形態の仲間分けⅠ
4)合同な基本形態の仲間分けⅡ
5)相似な基本形態の仲間分けⅠ
6)相似な基本形態の仲間分けⅡ
7)柱状体の仲間分けⅠ
8)柱状体の仲間分けⅡ
9) 球状体の仲間分けⅠ
10)球状体の仲間分けⅡ
11)錐状体の仲間分けⅠ
12)錐状体の仲間分けⅡ
13)錐状体とその変形
14)基本形態の再分類
15)秩序立った変化の観察Ⅰ
16)秩序立った変化の観察Ⅱ
17)粘土などを用いたモデル製作
(3) 基本形態と具体物の対応関係の理解
1)基本形態と具体物との一体一対応Ⅰ
2)基本形態と具体物との一対一対応Ⅱ
3)具体物の同形分類
4)類似形探しⅠ
5)類似形探しⅡ
6)類似形探しⅢ
(4) 立体の合成分解
1)基本形態の組み合わせによる具体物の表現
2)具体物の分解・構成
3)ブロックによる単純な形のモデル製作
4)粘土によるモデル製作
5)ブロックによる複雑な形のモデル製作
(5) 基本形態と基本形の対応関係の理解
1)基本形態の面と基本形との対応
2)展開図による箱作り
3)基本形態と基本形の投影的対応Ⅰ
4)基本形態と基本形の投影的対応Ⅱ
5)合同・相似な基本形の重ね合わせ
6)基本形態の組み合わせによる立体の自由製作
(6) 面図形のイメージの構成
1)立体と受け枠との対応
2)受け枠と基本形の対応
3)合同な基本形の仲間分けⅠ
4)合同な基本形の仲間分けⅡ
5)相似な基本形の仲間分け
6)円状形・三角形・四角形の仲間分け
7)長方形・平行四辺形・二等辺三角形の一辺の長さの変化
8)多少凹凸のある面図形の仲間分け
9)面図形の合成
10)面図形の分解
(7) 面図形と線図形などとの関係の理解
1)面図形などの輪郭たどり
2)線図形の構成
3)合同な線図形カードの一対一対応
4)線図形カードの同形分類Ⅰ
5)線図形カードの同形分類Ⅱ
6)線図形カードの合成
7)線図形カードの分解
8)重なった線図形の読み取り
(8) 基本形態の二次元的表現や読み取り
1)基本形態の投影的表現や読み取り
2)具体物と凸図および線図の対応
3)「トンネル法」による見取り図の読み取りと表現
4)「トンネル法」による簡単な絵の理解
(9) 支援や指導を進める上でのいくつかのヒント
1)算数等の教科学習との関連
2)基本形態のイメージづくりの重要性を大切に
3)体験を通した理解の重視
4)試行錯誤や失敗を奨励して積極的な活動を促す
5)指導の順次性に配慮を
6)プログラム補強の大切さ
第5章 空間のイメージづくりの学習
1 学習の位置づけとねらい等
2 学習プログラムの概要
(1) 活動中心的定位の段階
(2) ルートマップ型表象の段階
(3) サーヴェイマップ型表象の段階
3 学習プログラムの具体的展開
(1) 活動中心的定位の段階における支援
1)特定の閉じた空間における効率的な移動
2)身体像および身体図式の明確化
(2) ルートマップ型表象の段階における支援
1)身体座標軸の形成
2)身体座標軸の原点移動
3)空間座標軸形成の基礎
4)歩いた軌跡と指の運動等との対応関係の理解
5)よく知っている教室等の位置の表現
6)教室模型の組み立て・分解
7)教室の備品等の配置と表現上の約束
8)指歩行と実際の歩行との対応
(3) サーヴェイマップ型表象の段階
1)モデル製作による発達レベルのチェック
2)メンタルローテーションによる教室備品の表現
3)1階部分の教室模型の配置
4)校舎の全体像の理解
5)広さや距離の導入
6)学校敷地内の建物等配置図の構成
7)学校敷地内の建物等配置図の読み取りと実際歩行
4 支援や指導を進める上でのいくつかのヒント
(1) 教材教具の整備と工夫
(2) 比較的広い空間の理解には日常的な歩行経験が重要
(3) 具体的な学習プログラムのとらえ方
(4) 指導の継続性と連続性
(5) 歩行地図の活動への発展
ご購入方法
ご購入希望の際は,お近くの書店にご注文下さい。
また,この本は,下記のオンライン書店でもご購入いただけます。
送料・お支払い方法等につきましては,各オンライン書店のホームページをご参照下さい。