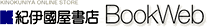分かりやすい「自立活動」領域の捉え方と実践
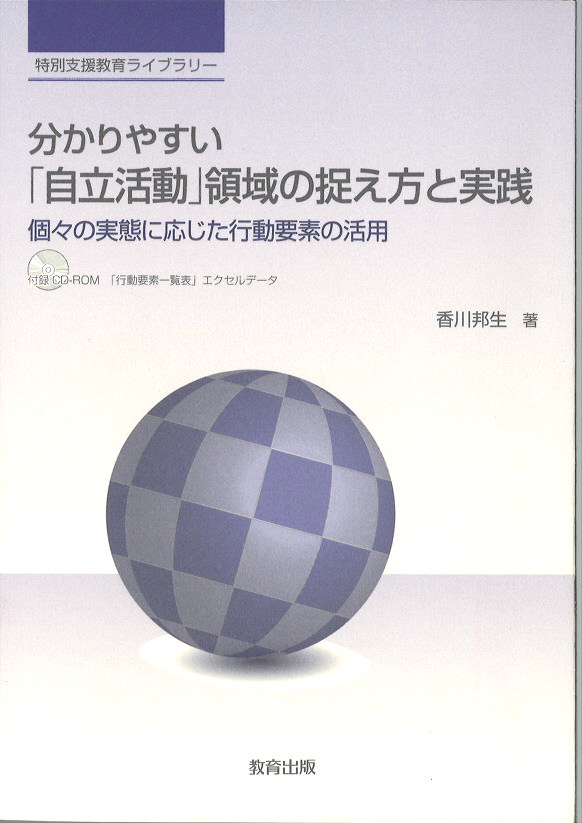
特別支援教育ライブラリー 分かりやすい「自立活動」領域の捉え方と実践 個々の実態に応じた行動要素の活用
- 香川邦生 著
- A5判 並製 136頁 CD-ROM付
- 2015年7月 発行
- ISBN 978-4-316-80429-3
- 定価 (税込) 2,420円(本体 2,200円+税)
- 読者対象:小・中学校教師,特別支援学校教師
商品内容
千項目を超える「行動要素一覧」から,児童生徒の実態に応じて重点的に指導する項目を抜き出し,効果的な自立活動の指導を実現する手法について,具体的に解説。「行動要素一覧」エクセルデータを収めたCD-ROM付き。
目次
Ⅰ 自立活動の基本と展開
第1 社会情勢の変化と「自立活動」領域の使命
1 特別支援教育への移行
2 障害者権利条約と共生社会の課題
3 時代の変化を越えて変わらず大切な「エンパワーメント」
4 「自立活動」という名称とその背景
第2 自立活動の位置付けと構造
1 特別支援学校の教育目標と「自立活動」領域との関係
2 教育課程における「自立活動」の位置付け
3 改善・克服すべき障害の捉え方
4 「自立」の意味の検討
5 「自立活動」領域の内容の構造
(1) 障害種別間や学部間を越えて共通の内容を示す意図
(2) 教科の内容の示し方との違い
(3) 自立活動領域における具体的な指導事項の選定
(4)「自立活動」の内容のL字構造
(5) 「自立活動」と重複障害者の特例との関係
6 教え込む指導から学び取る指導へ
7 大切にしたい技術と技能の関係 8 小・中学校に在籍する障害児への対応
第3 指導の充実に向けた個別の指導計画
1 大切な「指導に役立つ」という視点
2 多様な側面からの実態把握の必要性
(1) 行動観察による実態把握
(2) 検査による実態把握
(3) 面接による実態把握の深化
(4) チェックリストの活用による実態把握の構造化
3 具体的で達成可能な目標・内容の設定
4 核になる内容の重視
5 個別の指導計画と具体的な指導の場
6 学校における教育計画全体と個別の指導計画との関係の明確化
7 個別の教育支援計画との関係
8 大切な保護者との連携
9 チームアプローチの重要性
第4 通常の学級に在籍する障害児に対する自立活動の実践
1 基本的な考え方
2 指導の対象となる児童生徒
3 特別な支援を行う際の手続き
(1) 先ずは担任の判断による要請
(2) 実態把握
(3) 「校内委員会」等での検討
(4) 保護者との連携
(5) 指導目標の明確化
(6) 指導経過等に関する情報の共有
第2編 各分野・領域ごとの行動要素とその活用
第1 各分野・領域ごとの行動要素作成の意図と活用の方法
1 各分野・領域の構造と項目配列の考え方
2 5段階区分の考え方
3 行動要素の活用の仕方
4 行動要素活用の事例
事例1 Y視覚障害児の場合
事例2 T聴覚障害児の場合
事例3 「ADHDと診断されているA児の場合
事例4 B肢体不自由児の場合
第2 5段階に分けた行動要素一覧
1 障害の理解と心身の調整
(1) 自己の障害等の理解
(2)障害を改善する態度と障害を克服する意欲の形成
2 探索操作
(1) 手や腕による探索操作
(2)視覚による探索操作と視覚補助具等の活用
(3)聴覚による探索操作
(4)味覚・嗅覚・皮膚感覚等による探索操作
(5)足と全身の皮膚による探索操作
3 行動の枠組みの形成と活用
(1)モノの機能と質 (2)数量の概念の活用と時間的順序付け
(3)空間の表象や概念の形成と活用
4 運動と姿勢
(1) 全身の運動と姿勢
(2) 上肢の運動機能
(3)作業時と座位における姿勢
5 移動とその手段
(1) 介添による移動
(2) 目的単独移動
(3) 移動に必要な補助具の活用
(4) 移動環境の関係的理解
6 日常生活基本動作
(1) 食事
(2) 排泄
(3) 着脱と着こなし
(4) 清潔と身繕い
(5) 睡眠
(6) 整理整頓<br/ >7 作業基本動作
(1) 作業の基本技能
(2) 道具と接着材料等の活用技能
(3) 作業における構想と手順の見積もり
(4) 共同作業
8 コミュニケーション
(1) 対話
(2) 音声・語彙・語法
(3) 文字と符号
(4) 人間関係と社会性
【補足】 重複障害児にたいする行動のチェック項目
付録 行動要素一覧(CD)
ご購入方法
購入ご希望の際は,お近くの書店にご注文下さい。
また,この本は,下記のオンライン書店でもご購入いただけます。
送料・お支払い方法等につきましては,各オンライン書店のホームページをご参照下さい。