第2回 「あぁ! 学級崩壊!」
―私が学んだもの― ②
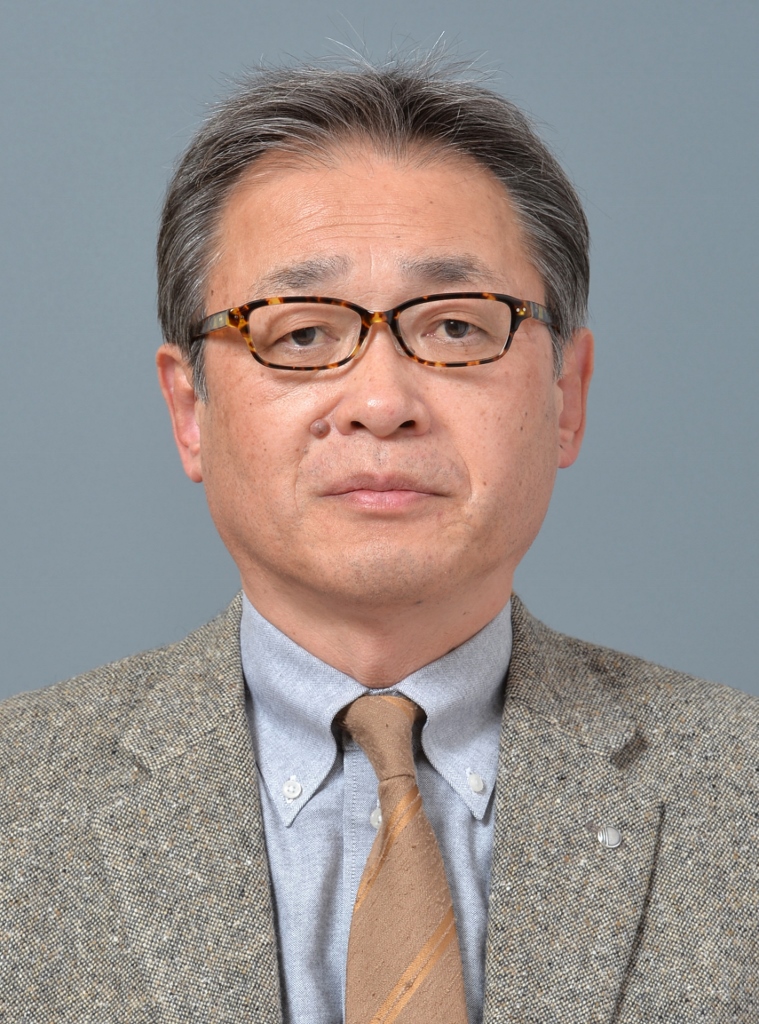 |
神奈川大学人間科学部 非常勤講師 |
前回に続き、私が経験した"学級崩壊"についてお話しします。初任校での6年間は授業や学級運営等の校務も評価され、一定の専門能力は身に付いていたはずでした。そうした自負は7年めの"学級崩壊"でみじんに壊れました。その葛藤のなかで私は、自分に何が足りなかったのかに気付かされました。それが見えてきた"答え"です。
初任校での6年間、私は生徒たちに「よーし! 今度はこの問題をやるぞ。いいな!」「おい、おい! 早くやった!やった!」などと快活に声をかけ、生徒たちも明るく応じてくれ、よい関係で楽しく授業や学級活動等を行っていました。若さもあり、少々乱暴な言葉づかいでも生徒には"うけて"、親しみとして伝わると思っていました。
しかし、教師の言葉かけや態度は、受ける相手によって全く違う印象や意味になることに気付いたのです。生育環境のなかで、理不尽な経験をさせられた子どもや大人への不信感を積み重ねてきた子どもにとっては、私の親しみを込めたつもりの声かけは、乱暴で過去の理不尽な経験を思い起こさせるものになり得ます。そうした子どもが数人いれば、感覚は強化されて集団としての強い不信感となります。私は自分の傲慢さに気付きました。子どもの立場に立っていたつもりで、何もできていなかったのです。
どうしたら、この子どもたちが私の話を聞いてくれるようになるのか。私は自分を変えることにしました。子どもたちのありようは多様です。その子ども一人一人にしっかりと向き合える教師になる。それは自分自身を耕し続ける自己変革の始まりでした。
私は主任や同僚の助けもあり、なんとかその学級担任を終えることができました。その頃からその生徒たちも私に近づくようになって"和解"もでき、ともに進級して、私は第2学年の担任になりました。生徒たちがしだいに私を理解し、認めるようになりました。教師の生徒理解は、生徒の「先生理解」と裏腹の関係で、同時に進んでいくのです。
教師は専門能力を身につけ、指導者・育成者・観察者・分析者・評価者などとして子どもに向き合います。しかし、これらの能力を身につければ教師なのでしょうか。私はあの1年間、子どもにとって無意味な存在でした。子どもは教師の人間性を直感で見抜きます。自分は「子どもの心に位置づけられている人」なのか、子どもにとって意味ある存在なのか、こうした問いを自分に課し続けるのが教師だと思っています。
【著者プロフィール】
神奈川大学人間科学部 非常勤講師(教職課程)。北里大学保健衛生専門学院 非常勤講師。専門分野は、生徒指導論、教職論、学校経営論、情報メディア論、教育相談。
【略歴】
22年間、横浜市立中学校3校で教諭として(うち8年間は生徒指導専任教諭として)勤める。その後、横浜市教育委員会指導主事、同市立中学校校長、横浜市教育委員会児童・生徒指導担当課長及び部長、横浜市教育センター所長を経て、横浜市立南高等学校校長を務めた。2012年以降は大学教育に携わり、玉川大学教職大学院准教授、同教授、神奈川大学・大正大学等で非常勤講師を務め、2018年から神奈川大学人間科学部特任教授を務め、2022年3月定年退職し、現職。
【著書】
「実践 教職論 ―未来の創り手となる子どもたちのために―」(ナカニシヤ出版)、「モバイル社会を生きる子どもたち-『ケータイ』世代の教育と子育て-」(時事通信出版局)、「子どもの危機と学校組織 ―苦悩する学校を救う鍵は教師の生徒指導力向上とチーム力」(教育出版)




