第3回 子どもの変容はどこから?
―「心に位置づけられている人」― ①
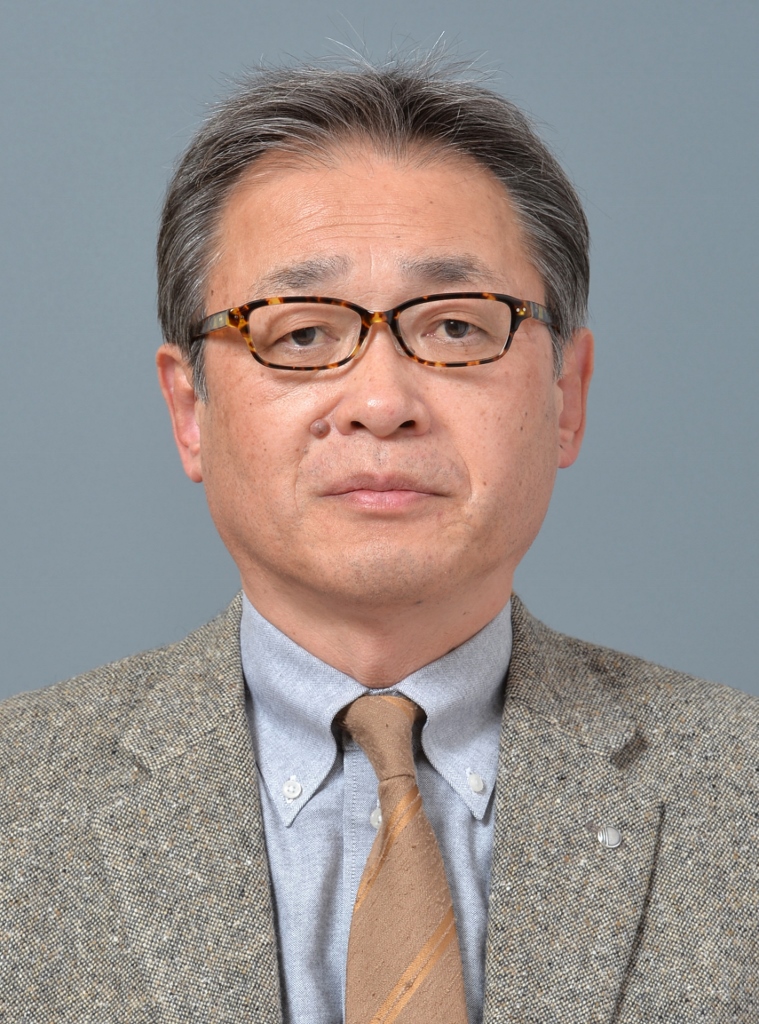 |
神奈川大学人間科学部 非常勤講師 |
皆さんが日々向き合っている子どもたちは、さまざまな表情を見せます。時にはかわいく、時には皆さんをイライラ気分にさせることもあるのでしょう。いずれにせよ、子どもたちにはよい方向に変わってほしいし、その成長を願わぬ教師はいません。
では、成長や変容は、どこから起こるのでしょうか。毎回毎回、口酸っぱくなるほど注意すれば成長しますか。子どもがそれほど単純ではないことは、おわかりと思います。
前回、教師は専門能力の他に「子どもの心に位置づけられている人」であることが求められると述べました。私は大学で、自己形成につながるような「心に位置づけられている」教師との出会いの体験を調査してきました。次の文章はその中の学生Aさんの体験談です。
|
私は小学校に入学した時から、週に1回は親が学校に呼び出されるほど問題を起こしていました。ですが、担任の先生は、私のことを問題児だと見捨てることをせず、私に、どうしてそんなことをしたのか、なぜしてはいけないのかなどを根気強く教えてくれました。その時は、ただ、したいからしているだけ、理由もなく、当時の私には何も響きませんでした。 ある日、私がしていないのに、私のせいになった問題がありました。その時は、周りの先生もまた私がやったと思い、注意を受けました。その時に、担任をしていた先生だけが最初から私のことを疑うのではなく、私の話を最後まで聞いてくれました。そして、問題を解決してくれました。 その時に私は、私のためにここまでしてくれる先生を悲しませることをやめようと思い、問題を起こすのをやめました。この経験から、人間としてみんなが信頼できるような人になろうと思いました。 |
皆さんも、親身になって子どもを導こうとしても、文中の「したいからしているだけ、理由もなく、何も響きませんでした」のように、全く響かない経験もあることでしょう。しかし、この先生は間違いなく、幼いAさんの心のなかに存在しています。なぜ幼いAさんは自分の行動を変えようと思ったのでしょうか。ここに子どもの成長しようとする力と教師の存在する意義が見えています。子どもの成長はどのように起こるのか、ご自分の教師との出会いも思い出しながら考えてみてください。 続きは次回!
【著者プロフィール】
神奈川大学人間科学部 非常勤講師(教職課程)。北里大学保健衛生専門学院 非常勤講師。専門分野は、生徒指導論、教職論、学校経営論、情報メディア論、教育相談。
【略歴】
22年間、横浜市立中学校3校で教諭として(うち8年間は生徒指導専任教諭として)勤める。その後、横浜市教育委員会指導主事、同市立中学校校長、横浜市教育委員会児童・生徒指導担当課長及び部長、横浜市教育センター所長を経て、横浜市立南高等学校校長を務めた。2012年以降は大学教育に携わり、玉川大学教職大学院准教授、同教授、神奈川大学・大正大学等で非常勤講師を務め、2018年から神奈川大学人間科学部特任教授を務め、2022年3月定年退職し、現職。
【著書】
「実践 教職論 ―未来の創り手となる子どもたちのために―」(ナカニシヤ出版)、「モバイル社会を生きる子どもたち-『ケータイ』世代の教育と子育て-」(時事通信出版局)、「子どもの危機と学校組織 ―苦悩する学校を救う鍵は教師の生徒指導力向上とチーム力」(教育出版)




