第5回 学級づくりの基本は40通りの信頼関係
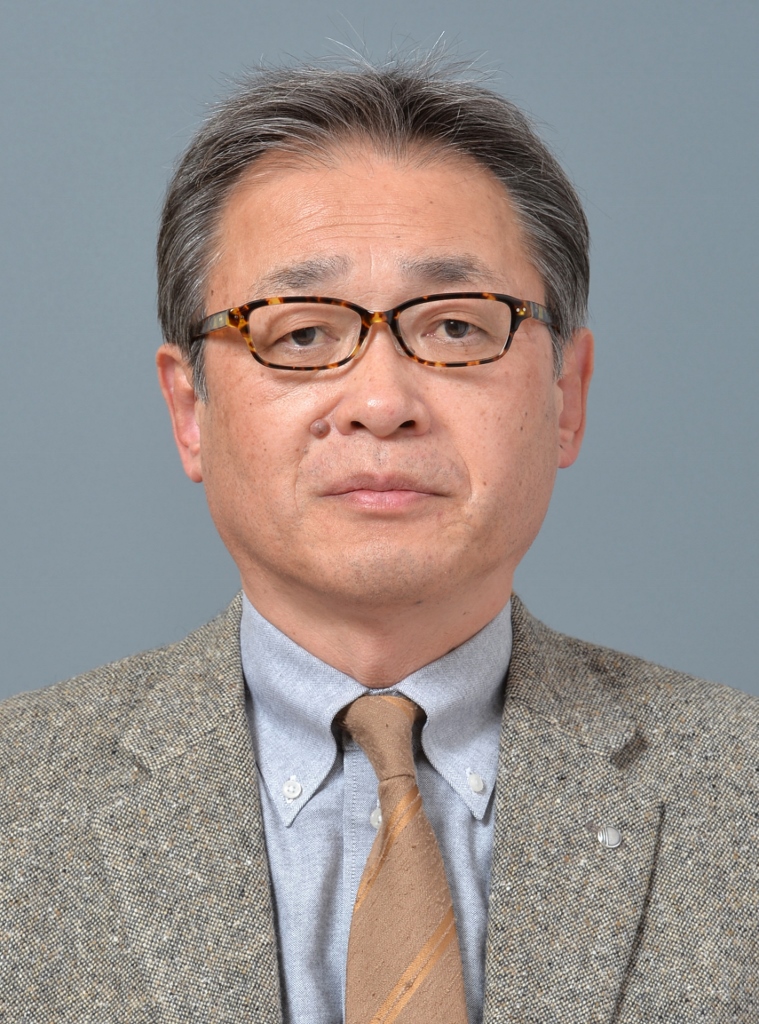 |
神奈川大学人間科学部 非常勤講師 |
学級担任をしていて、子どもたちが活発で仲がよく、温かな雰囲気の学級になってくると、ほっとします。逆に、人間関係がギスギスして、子どもの表情が暗く、イジリやからかいが多く、特性の違い等からトラブルが続くと、担任の表情もきつくなります。
子どもたちは、家庭内のストレスや葛藤、自己形成上の不安や発達上の課題等を抱えながら集団生活をしており、時に、そのストレスが集団のなかで強化され、集団生活を不健全な方向に引きずる負のエネルギーが高まることがあります。担任はこうした子どもたちやその集団にどう向き合えばいいのでしょうか。
私の失敗は子どもたちを集団として捉え過ぎたことでした。「この子たちはまとまってきてるから大丈夫」「この子たちはまとまろうという意識が弱いからダメ......」などの見方です。これでは子どもたちを見ているつもりでも、実際は見ていません。ストレスや悩みを見落としたり、トラブルから深刻ないじめに発展したりすることもあります。
健全な集団づくりのためには、担任が児童・生徒理解、とりわけ子ども個々の特性を十分に認識して、信頼関係を築くことが基本であることはご存じのとおりです。そして、担任は40人の集団と向き合うという意識ではなく、子ども一人一人と向き合って「1対1」の信頼関係を40通り築こうという意識をもつ必要があります。その40通りの信頼関係の"束"が学級だと理解したいところです。担任と個々の子どもとの信頼関係がしだいにできていくと、子ども間の人間関係にも影響し、良好な関係性が広がっていき健全な集団づくりにつながります。数人の子どもと「1対1」の信頼関係ができると、それは "口コミ"で他の子どもたちにも広がります。思うよりは早く、40通りの信頼の束はできるはずです。学級づくりなどに悩んでいたら、こうした見方を参考にスタンスを変えてみて、取り組むのもよいでしょう。また、一人で抱え込まず同僚の先生たちと学級づくりのコツを話し合い、チームで取り組むとよい結果につながります。学級づくりについては、今後も取り上げていきます。
最後に皆さんに質問です。なぜ、学級の子どもたちを集団として捉えるより、「1対1」の信頼関係を築くことを優先するのでしょうか。その理由を考えてみてください。次回は、このへんから始めます。
【著者プロフィール】
神奈川大学人間科学部 非常勤講師(教職課程)。北里大学保健衛生専門学院 非常勤講師。専門分野は、生徒指導論、教職論、学校経営論、情報メディア論、教育相談。
【略歴】
22年間、横浜市立中学校3校で教諭として(うち8年間は生徒指導専任教諭として)勤める。その後、横浜市教育委員会指導主事、同市立中学校校長、横浜市教育委員会児童・生徒指導担当課長及び部長、横浜市教育センター所長を経て、横浜市立南高等学校校長を務めた。2012年以降は大学教育に携わり、玉川大学教職大学院准教授、同教授、神奈川大学・大正大学等で非常勤講師を務め、2018年から神奈川大学人間科学部特任教授を務め、2022年3月定年退職し、現職。
【著書】
「実践 教職論 ―未来の創り手となる子どもたちのために―」(ナカニシヤ出版)、「モバイル社会を生きる子どもたち-『ケータイ』世代の教育と子育て-」(時事通信出版局)、「子どもの危機と学校組織 ―苦悩する学校を救う鍵は教師の生徒指導力向上とチーム力」(教育出版)




