第7回 「行動規制の生徒指導」から「関係性の生徒指導」へ
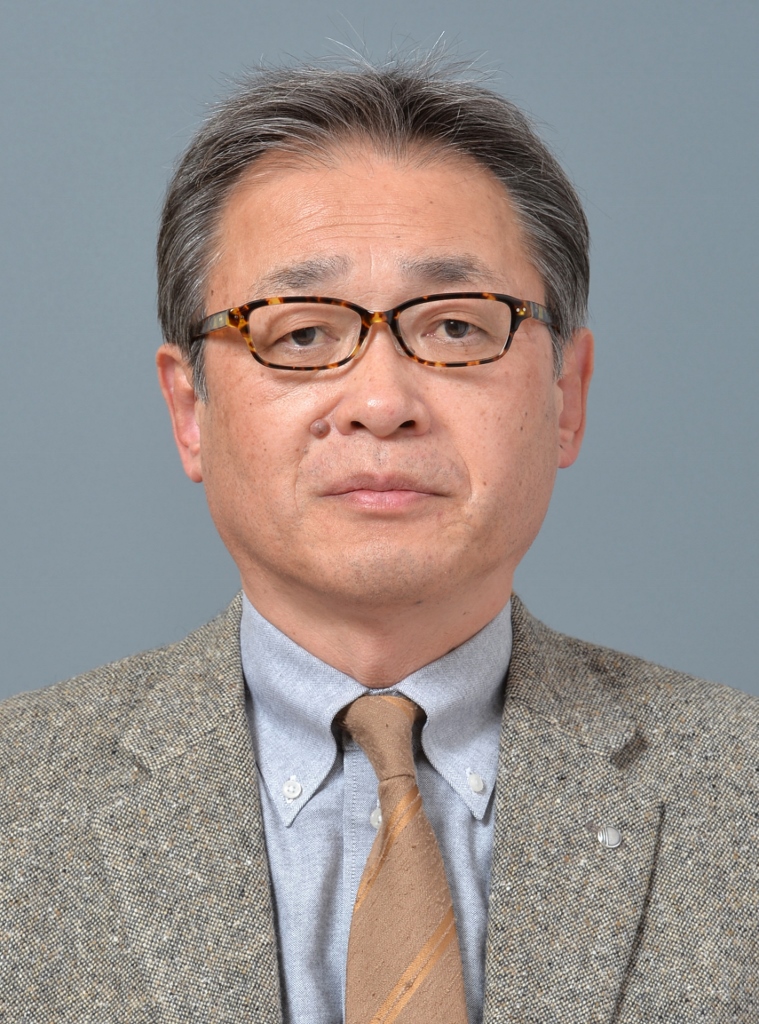 |
神奈川大学人間科学部 非常勤講師 |
不登校やいじめ、ネット依存や自傷行為、いわゆるキレる暴力行為など、子どもたちの不適応や問題行動の対応に悩む方も多いと思います。
さて、生徒指導というと、服装・髪型等の検査や違反時のペナルティーなど、「行動規制」のイメージが先行します。果たして「行動規制」による管理主義的な生徒指導で現代の子どもの深刻化する不適応や問題行動に対応できるのでしょうか。いじめに悩む子どもが相談に来てくれるでしょうか。近年、子どもたちの内向化が進み、自殺死亡率も顕著に高くなってきています。生活管理や自己管理は大切なものであり、集団生活上の規則は必要です。しかし、規則を押しつけて、枠に子どもを入れておけば、社会性は身につき成長するという考え方は誤りです。かつて、行動規制中心の管理主義の教育は、校内暴力やいじめ・不登校の増加などによって、修正を余儀なくされた経緯があります。
現代の子どもたちの不適応や問題行動の背景に、自他への不信や不安、内向化や低い自己肯定感等があることを踏まえておく必要があります。さらに、子どもたちが個別に抱える発達課題や情緒不安、心身の疾患、児童虐待やDV、保護者の情緒不安や不適応、貧困や健康問題など、多様な要因があることも理解しておく必要があります。こうした状況下において、行動規制を第一とする生徒指導では対処できません。
第4回で「互いが大切だと実感できる関係性」が子どもに成長をもたらすと述べました。そうであるなら教師は、子どもにとって「大切な人」「重要な他者」といえる存在に近づく努力を続ける真摯さが求められます。子どもがどのような状況にあっても真摯に向き合い、受け止め、寄り添う姿勢を貫くことが基本です。相談の技量や能力、指導上の技量も必要ではありますが、それよりも、人としてのその愚直な姿勢を子どもは必ず感じてくれます。やがて、信頼関係が芽生え、そのなかで自己の大切さを実感した子どもは自らの力で成長しようとします。こうした関係性を築けた教師ならば、いじめに関わった子どもたちの人間関係に介入することもでき、引きこもってうち沈んだ子どもの心情を受け止めることもできるはずです。このような関係性を基盤とする支援や指導を私は「関係性の生徒指導」と呼んでいます。次回は「関係性の生徒指導」の具体的なアプローチの仕方について考えていきます。
【著者プロフィール】
神奈川大学人間科学部 非常勤講師(教職課程)。北里大学保健衛生専門学院 非常勤講師。専門分野は、生徒指導論、教職論、学校経営論、情報メディア論、教育相談。
【略歴】
22年間、横浜市立中学校3校で教諭として(うち8年間は生徒指導専任教諭として)勤める。その後、横浜市教育委員会指導主事、同市立中学校校長、横浜市教育委員会児童・生徒指導担当課長及び部長、横浜市教育センター所長を経て、横浜市立南高等学校校長を務めた。2012年以降は大学教育に携わり、玉川大学教職大学院准教授、同教授、神奈川大学・大正大学等で非常勤講師を務め、2018年から神奈川大学人間科学部特任教授を務め、2022年3月定年退職し、現職。
【著書】
「実践 教職論 ―未来の創り手となる子どもたちのために―」(ナカニシヤ出版)、「モバイル社会を生きる子どもたち-『ケータイ』世代の教育と子育て-」(時事通信出版局)、「子どもの危機と学校組織 ―苦悩する学校を救う鍵は教師の生徒指導力向上とチーム力」(教育出版)




