第8回 「関係性の生徒指導」
(1)自律的なアプローチとカウンセリングマインド
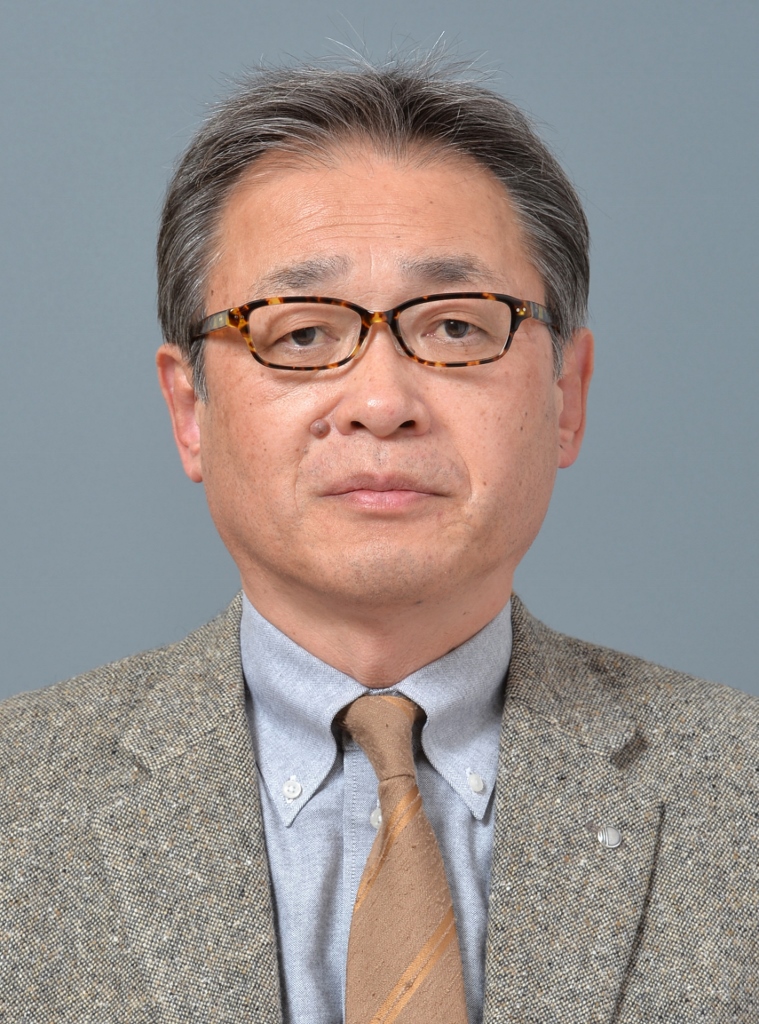 |
神奈川大学人間科学部 非常勤講師 |
前回、現代の子どもたちの深刻な課題に向き合うには「関係性の生徒指導」が必要だと述べました。私は、その定義を「児童・生徒が自己や他者がかけがえのない尊い存在であることを実感できるよう、児童・生徒間及び児童・生徒と教師の間に豊かな人間関係を築き、児童・生徒が自らの大切さを実感して、健やかに生かしていけるよう自己実現を支援すること」としています。
では、どのように子どもにアプローチするのでしょうか。いじめを繰り返しながらうそをついて事実を認めない子ども、キレて暴力を繰り返す子ども、薬物や恐喝等で検挙された子どもなど、教師は苦闘のなかで時にむなしくなり、「あの子はもともと変だから・・・」「家庭がダメだから仕方ない・・・」などとつぶやくこともあるのではないでしょうか。
そこで思い出してもらいたいのは第3回のAさんの言葉です。「私のためにここまでしてくれる先生を悲しませることをやめようと思い、問題を起こすのをやめました。」とありました。ここにアプローチの基本があります。それはカウンセリングマインドといえ、私はそれを「目の前にいる子どもが、どんな状況にあっても、どんな言動をしていても、その子どもが、自分の力で自分を成長させ、課題を乗り越えていく力があると信じることのできる、人間として、そして教師としての心のありよう」と定義しています。このマインドは教師のまなざしや語感に表れます。それを子どもたちは鋭敏に感じ取り、教師に素直に向き合うきっかけとなります。逆に、先の「あの子はもともと変だから・・・」の思いは子どもに読み取られ、子どもに拒否感や不信感を増殖させます。
教師が子どもの心性と成長の力を信じて向き合うことが信頼を育み、やがて子どもが教師を理解して「大切な人」「重要な他者」と感じるようになり、子どもは心を開き、悩みを話すようになります。こうなって初めて教師は子どもの人間関係やそこに絡み合う感情を理解できるようになるのです。子どもの人間関係で起こるいじめへの指導や支援を考えれば、教師には子どもの人間関係に介入できるような信頼関係を築くことが求められます。「重要な他者」となった教師との出会いは、子どものもつ成長の力を支えます。子どもの自律的な成長の力を信じたアプローチを「自律的なアプローチ」と呼びます。次回は、さらに「関係性の生徒指導」の進め方について深めていきます。
【著者プロフィール】
神奈川大学人間科学部 非常勤講師(教職課程)。北里大学保健衛生専門学院 非常勤講師。専門分野は、生徒指導論、教職論、学校経営論、情報メディア論、教育相談。
【略歴】
22年間、横浜市立中学校3校で教諭として(うち8年間は生徒指導専任教諭として)勤める。その後、横浜市教育委員会指導主事、同市立中学校校長、横浜市教育委員会児童・生徒指導担当課長及び部長、横浜市教育センター所長を経て、横浜市立南高等学校校長を務めた。2012年以降は大学教育に携わり、玉川大学教職大学院准教授、同教授、神奈川大学・大正大学等で非常勤講師を務め、2018年から神奈川大学人間科学部特任教授を務め、2022年3月定年退職し、現職。
【著書】
「実践 教職論 ―未来の創り手となる子どもたちのために―」(ナカニシヤ出版)、「モバイル社会を生きる子どもたち-『ケータイ』世代の教育と子育て-」(時事通信出版局)、「子どもの危機と学校組織 ―苦悩する学校を救う鍵は教師の生徒指導力向上とチーム力」(教育出版)




