第9回 「関係性の生徒指導」
(2)一人で抱え込まず組織で支援を
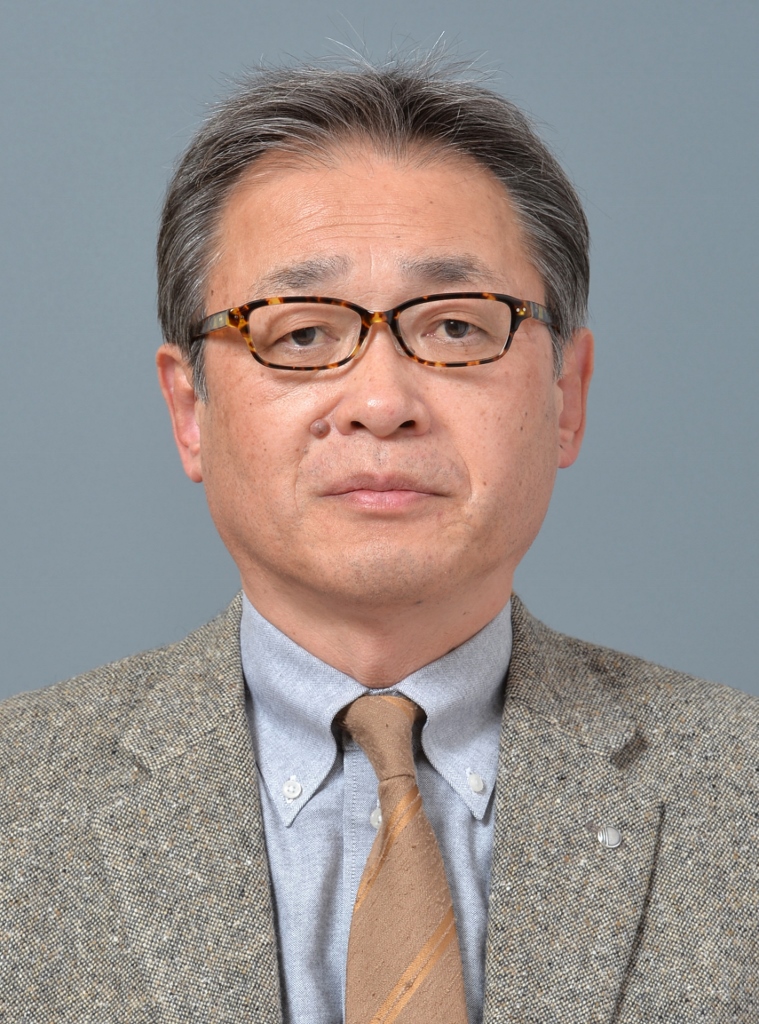 |
神奈川大学人間科学部 非常勤講師 |
前回、教師が子どもたち一人一人と信頼関係を築き、子どもにとって「重要な他者」となる必要があると述べました。しかし、一人で抱え込むのは厳禁です。子どもの心情や課題への理解を全教職員で共有し、相互に連携して支援する風通しのよい組織が必要です。子どもにとっては、いろいろな先生が声をかけてくれ、理解してもらえるような安心感のある学校が望まれます。子どもに向き合う教師を周囲が支える体制を整え、学校組織として継続的にケースカンファレンスを行う必要があります。教師は、関係する他の教師たちや先輩教師と、子どもへの理解や対応について協議し、思い込みのない的確な分析を行う必要があります。そうしたケースカンファレンスにおいて、校外の専門機関と連携し、医療・心理・福祉・司法など、状況に応じた専門的な知見を活用したり、アセスメントやスクリーニング等を行ったりすることによって、子どもの特性や集団構造などを正確に把握でき、支援や指導の実効性を高めることができるのです。
ところで、悩んでいる子どもが心を開いて話し始めてくれると、向き合ってきた教師はうれしいものです。教師としてやりがいを感じたり、自分の存在意義を実感したりして、さらに一生懸命に関わり、悩みの解消に役立ちたいと思うのは自然です。
では、次のような事例はいかがでしょうか。皆さんのところによく話しに来て、心身の不調を訴えていた生徒が、ある日、「先生にだけに話すから」と言い、手首と太ももの深い傷を見せ、自傷行為を繰り返してきたことをうち明け、さらに、母親がうつ病で情緒不安定であることを話してくれました。そして、「親や他の先生に絶対言わないで」と懇願したとします。皆さんは、どのように向き合い、どのように対処しますか。
当初はなにげない心身の不調の相談であっとしても、背景に自傷行為や希死念慮、深刻な精神疾患、児童虐待やDV、性暴力被害や妊娠、犯罪行為や犯罪被害などが潜んでいる場合もあります。そうした可能性は常に考えられ、先述のとおり一人で抱え込んで、のめり込む状況に陥ることは絶対に避けなければなりません。皆さんが子どもに向き合うのは公務であり、職務であり、教育活動なのです。学校組織の一員として、ケースカンファレンスや機関連携などを行い、組織の総合力を挙げて、その子どもに受け入れやすい適切な支援方法を用意して、柔軟に対応していくのが教師の職務なのです。
【著者プロフィール】
神奈川大学人間科学部 非常勤講師(教職課程)。北里大学保健衛生専門学院 非常勤講師。専門分野は、生徒指導論、教職論、学校経営論、情報メディア論、教育相談。
【略歴】
22年間、横浜市立中学校3校で教諭として(うち8年間は生徒指導専任教諭として)勤める。その後、横浜市教育委員会指導主事、同市立中学校校長、横浜市教育委員会児童・生徒指導担当課長及び部長、横浜市教育センター所長を経て、横浜市立南高等学校校長を務めた。2012年以降は大学教育に携わり、玉川大学教職大学院准教授、同教授、神奈川大学・大正大学等で非常勤講師を務め、2018年から神奈川大学人間科学部特任教授を務め、2022年3月定年退職し、現職。
【著書】
「実践 教職論 ―未来の創り手となる子どもたちのために―」(ナカニシヤ出版)、「モバイル社会を生きる子どもたち-『ケータイ』世代の教育と子育て-」(時事通信出版局)、「子どもの危機と学校組織 ―苦悩する学校を救う鍵は教師の生徒指導力向上とチーム力」(教育出版)




