第10回 「関係性の生徒指導」
(3)自律を支える他律的なアプローチ
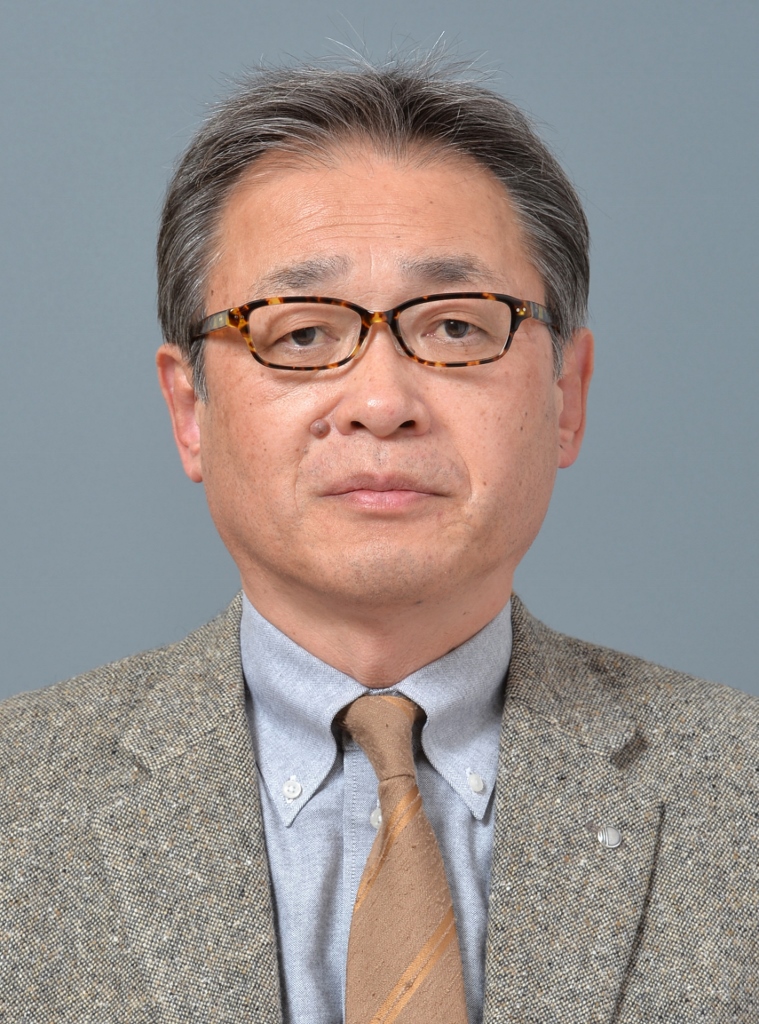 |
神奈川大学人間科学部 非常勤講師 |
本連載では、自他の尊さを実感できる関係性を基盤に、子どもが自ら成長しようとする力を信じて支援する「自律的なアプローチ」について述べてきました。では、事例として、教師に椅子を投げつけた生徒、キレて学級の花瓶を投げ割った児童、いじめから級友を突き飛ばした児童などの加害行為があったとします。この場合はどう向き合えばよいのでしょうか。こうした場合、「もっと"厳しい指導"が必要だ」、「カウンセリングマインドでは指導できない」という考えもあるかと思います。
では、"厳しい指導"について考えましょう。 "厳しい指導"とは何でしょうか。複数の教師で子どもを取り囲んで威圧し、怒鳴りつけて謝らせ、反省文を書かせたとして、これが"厳しい指導"でしょうか。子どもには、"怖い指導"には不服でも従っておくことを学ばせ、問題の本質を理解して自分を見つめ直す機会を奪っているように見えます。
加害に及んだ子どもの背景には、埋めきれない不安や不信、孤独感やストレス、自己不適応やゆがめられた発達など、多様な要因があることを理解する必要があります。そして、子どもの自暴自棄や反発の心情を理解して受け止めることで、子どもは教師を少しずつ認めはじめ、やがて自分の苦衷や後悔を話し始めます。子どもがどんなことをやったにしても、その心性を信じ、成長の力を信じることなしに支援や指導は子どもに届きません。加害の子どもに対しても「自律的アプローチ」を行って、子どもを内省に導き、自己認識を新たにさせて、その成長を支えることが基本なのです。
しかし、そうした指導で改善が見られたとして指導は終わりではありません。自分の行動の結果について、社会的責任を明確に示して社会的な存在であることを自覚させる必要があります。謝罪だけでなく、器物損壊であれば弁済を求め、暴力であれば治療費の支払い、警察との連携指導など、保護者の協力の下、社会的な責任のとり方を学ぶ教育場面を用意する必要があります。謝罪を含む、こうした指導や対応を私は「他律的なアプローチ」を呼んでいます。これが"厳しい指導"の本質です。子どもを威圧する必要などなく、「自律的なアプローチ」で静かに自分を見つめさせ、その上に「他律的アプローチ」を重ねて学びを深めさせます。「他律的なアプローチ」が「自律的なアプローチ」を支える相乗効果が期待できるのです。(了)
【著者プロフィール】
神奈川大学人間科学部 非常勤講師(教職課程)。北里大学保健衛生専門学院 非常勤講師。専門分野は、生徒指導論、教職論、学校経営論、情報メディア論、教育相談。
【略歴】
22年間、横浜市立中学校3校で教諭として(うち8年間は生徒指導専任教諭として)勤める。その後、横浜市教育委員会指導主事、同市立中学校校長、横浜市教育委員会児童・生徒指導担当課長及び部長、横浜市教育センター所長を経て、横浜市立南高等学校校長を務めた。2012年以降は大学教育に携わり、玉川大学教職大学院准教授、同教授、神奈川大学・大正大学等で非常勤講師を務め、2018年から神奈川大学人間科学部特任教授を務め、2022年3月定年退職し、現職。
【著書】
「実践 教職論 ―未来の創り手となる子どもたちのために―」(ナカニシヤ出版)、「モバイル社会を生きる子どもたち-『ケータイ』世代の教育と子育て-」(時事通信出版局)、「子どもの危機と学校組織 ―苦悩する学校を救う鍵は教師の生徒指導力向上とチーム力」(教育出版)




