#6 「もう言いましたよ。」の後悔
香川大学教育学部准教授
【著者プロフィール】
東京都小学校、広島大学附属三原小学校等を経て現職。小・中学校の先生がたと社会科、総合的な学習の時間、生活科の授業づくりにともに取り組んでいる。
ホーム > LINE > ライブラリ > 共通記事 > 2023年~2024年 > 連載 KOKAI×KOKAI 神野先生の後悔を公開 > #6 「もう言いましたよ。」の後悔
香川大学教育学部准教授
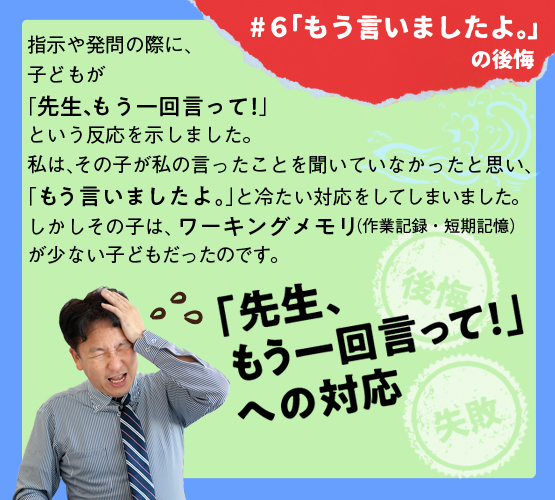 |
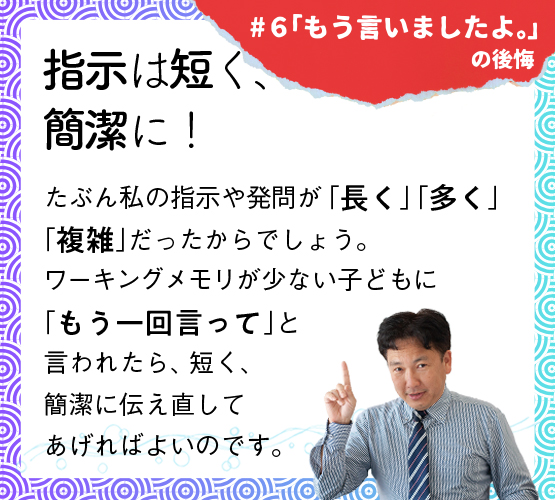 |
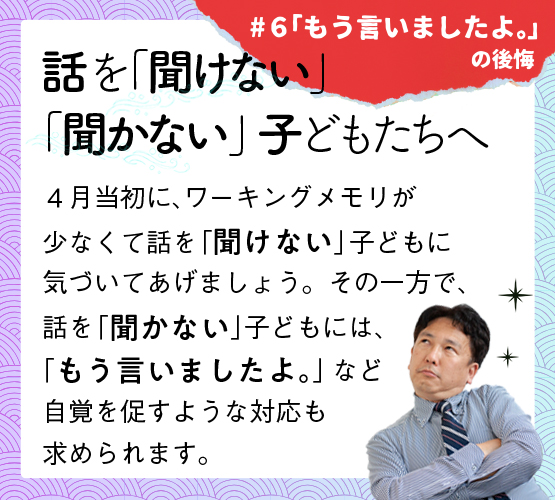 |
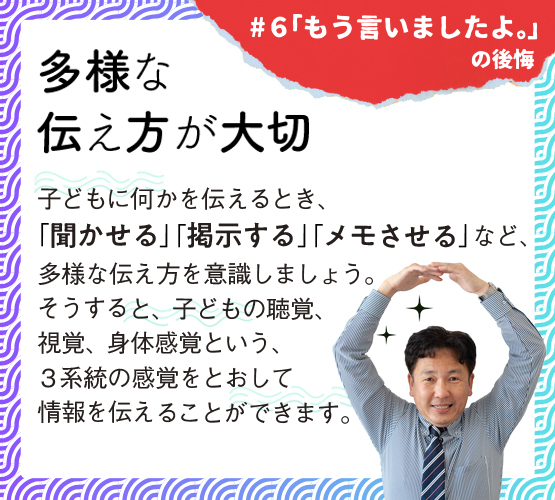 |
|
私は先輩教師から「いつも丁寧に応じてあげるだけでは、先生の話を聞かなくてもよいと勘違いしてしまう子どもが増えるので、ときには『もう言いましたよ。』という対応も大事だ。」と教わりました。その反面、ワーキングメモリが少ない子どもへの配慮が欠けていました。 ワーキングメモリが少ない子どもには、順序立てた指示を短い言葉で出すことがポイントです。例えば、教科書の3ページを開いてほしい場面では、①「教科書を出しましょう。」②「3ページを開きましょう。」というように伝えます。その際には「これ」「それ」「あれ」という指示代名詞は控えましょう。 「○○をしたあとに□□をすること。でも○○ができなかった場合には△△するように。」などと、教師は一度に多くのことを伝えがちです。声による音声情報だけではなく、文字や絵を書いたカードも示して時系列に並べてあげると、行動の順序が伝わりやすくなります。 インターネットで「ワーキングメモリを鍛える方法」や「長期記憶に転換する方法」という語句で検索すると多くの情報が得られます。ぜひやってみてください。 |
【著者プロフィール】

東京都小学校、広島大学附属三原小学校等を経て現職。小・中学校の先生がたと社会科、総合的な学習の時間、生活科の授業づくりにともに取り組んでいる。
