#8 「資料を出すタイミング」の後悔
香川大学教育学部准教授
【著者プロフィール】
東京都小学校、広島大学附属三原小学校等を経て現職。小・中学校の先生がたと社会科、総合的な学習の時間、生活科の授業づくりにともに取り組んでいる。
ホーム > LINE > ライブラリ > 共通記事 > 2023年~2024年 > 連載 KOKAI×KOKAI 神野先生の後悔を公開 > #8 「資料を出すタイミング」の後悔
香川大学教育学部准教授
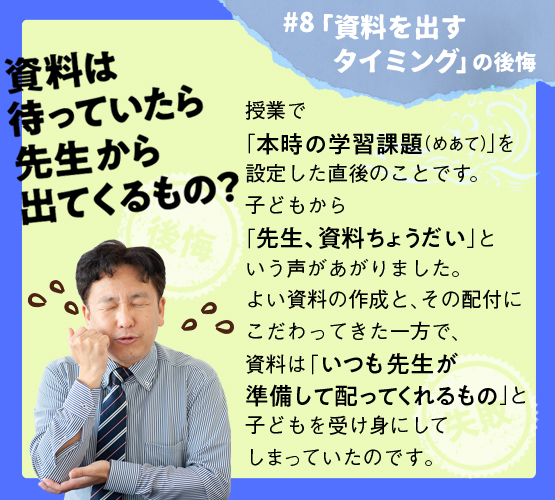 |
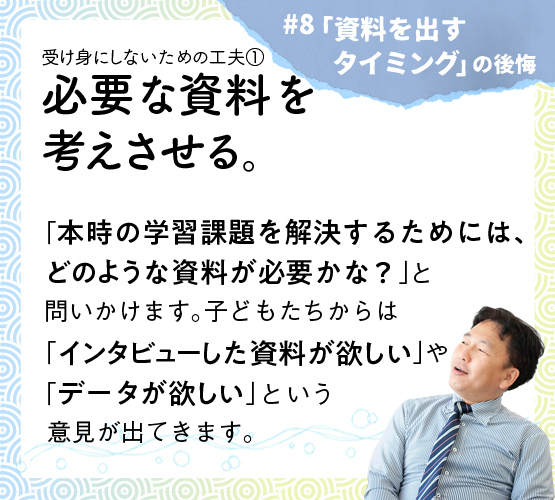 |
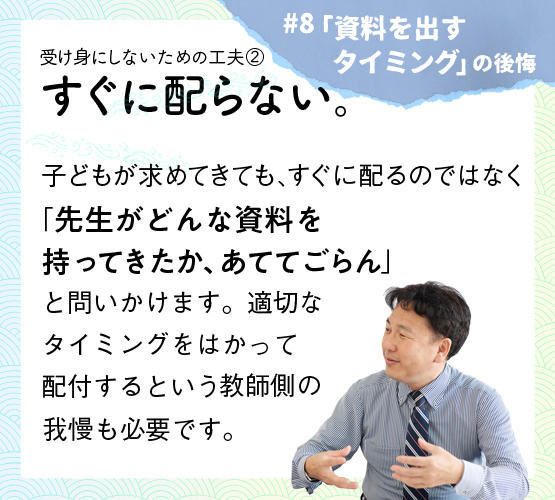 |
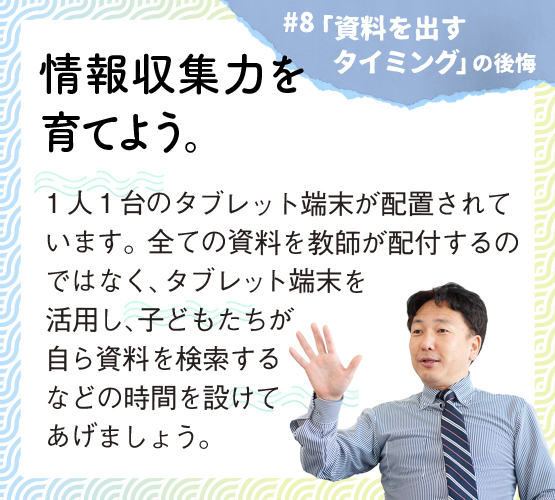 |
|
学習に必要な資料を考える直前には、「本時の学習課題(めあて)」について考察する「予想場面」が位置づいているとよいでしょう。学習の内容や流れを予想して見通しがもてると、課題解決に必要な資料も焦点化されていくはずです。「どんな資料が必要だろう?」とクラスで必要な資料のアイデアを出し合うことも協働的な学びとして素敵ですね。 「自ら資料を探す」ということは、学び方を子ども自らが自己決定していることになります。したがって、授業の最後に位置づけられる「振り返り場面」での「学びの自己調整」につながっていくのです。学習の全ての段階で、教師がレールを敷いてしまわないように留意し、自立した学習者を育てていきましょう。 |
【著者プロフィール】

東京都小学校、広島大学附属三原小学校等を経て現職。小・中学校の先生がたと社会科、総合的な学習の時間、生活科の授業づくりにともに取り組んでいる。
