第7回 勇気凜々 学校づくり
─機を見つつ、子どもの舞台をチームでつくる─
広島大学大学院人間社会科学研究科准教授
カトウ先生:ミンさんがね、新学期に放送委員になったんだ。
ハヤシさん:放送委員? それはすごいね。
カトウ先生:新学期に委員を決めたんだけれどね。その前に、ミンさんに「放送委員、やってみない?」と聞いてみたんだ。しばらく考えてから、「やってみる」って。
ハヤシさん:そうだったんだ。
カトウ先生:実は校長先生が「やらせてみたらどうか」って、言ったんだよ。最初、僕は反対したんだけれど。
ハヤシさん:確かに、ミンさんにとっては、まだ日本語に対する苦手意識もあるだろうし、コンプレックスもあるかもしれないもんね。
カトウ先生:そうなんだよ。でも校長先生は「きっと、ミンさんにとってもいい気がするんだよね」って。実際にミンさんが「やってみる」と言ったので僕もびっくりしたよ。でも、最近、友達と一緒に何かすることも増えてきて、ちょうどいいタイミングだったのかもしれない。事前に、「ミンさんが放送委員をがんばるから、放送されたら先生がたが率先して、ミンさんのがんばりを認める声かけをクラスのみんなにしてほしい」って、校長先生が職員室で言ってくれて。
ハヤシさん:ミンさんにとっていいタイミングだったのもあるし、校長先生が事前に意味を先生たちに伝えてくれると安心だね。
カトウ先生:そうそう。そしたらね、放送室で、始まる前にみんなで「ミン、こう言うんだよ」って練習したりしてるの。それで放送するじゃない。当然、ミンさんの日本語も、校内に流れるよね。そうしたら、その後で、いろんな先生や子どもたちが「ミンさんすごい!」「日本語もうまくなったね」って声をあげたんだよ。
ハヤシさん:確かに、校内放送で話すのって、目だつものね。目だつことってさせたくないって思いがちだけれど、ある意味で「舞台の上に立つ」って、それができたら勇気をもらえたり、自信になったりもするもんね。
カトウ先生:そうなんだよね。その後、ミンさんも自信が出てきたのか、いろんなところで発言する機会が増えたような気がするよ。
ハヤシさん:みんなの言葉が勇気になったんだね。
カトウ先生:そう! それともう一つ、なんというか、放送委員は、別に
ハヤシさん:それってすごく大事なことだと思う。確かに、日本語を伸ばすことは大事かもしれないけれど、周りにいる人たちが、ミンさんや、ミンさんだけじゃなくて、いろんな人の言葉をそのまま認めていくことだってすごく大事だと思う。「日本語学び中だって、流暢でなくたって、放送委員はやっていい」と思えることって素敵だよね。
前回までは、「授業」を中心に見てきましたが、今回は「学校づくり」の観点から見てみたいと思います。授業をどうするかだけではなく、学校の一員としてどう子どもを迎えていくかということは重要です。
こうした「放送委員」という仕事は、ハヤシさんやカトウ先生が言うように、「子どものタイミング」を考えることがとても重要です。ただ、一方で「挑戦」というきっかけを見つけることも重要です。「子どもの伸びる瞬間」を捉えながら、その子に光が当たるように「見せ場」をつくることができると、自信になるばかりか、周囲の子の刺激にもなっていきます。「見せ場」は舞台に上がることでもあります。それは「公につくられたかっこいい場所」であるために、そこに上がることやそこでパフォーマンスをすることは、周囲の子にとっても
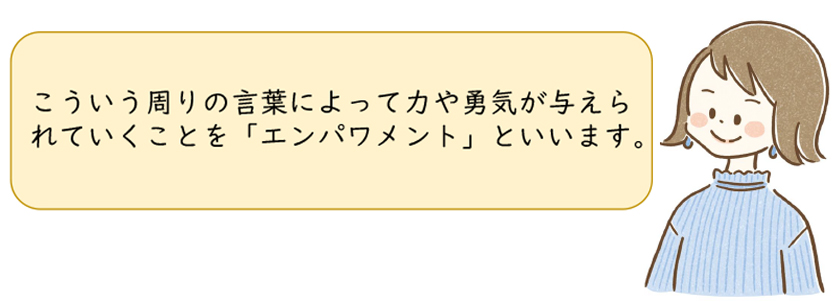
また、その姿を見ることは、周囲が「できないと思っていた子の力を知る」ということで、それは、「日本語ができないということは、その子が何もできないことではない」ということや「正確な日本語、流暢な日本語じゃなくても、その子の言葉はその子の言葉」という感覚につながっていきます。こうしたことの繰り返しが、やがて「いろいろな子どもを認めていく世界」にもつながっていきます。
大切なのは、この「放送委員」のエピソードは、単体で存在しているわけではなく、校長先生の「やってみたらどうか」という促しにあるように、もっと広い学校づくりの視点や長期的な視点から考えていく必要があるということです。
実はこのエピソードは、広島市の外国人児童生徒拠点校になっているある小学校で、実際にあったものです。当時の校長先生は、「放送委員」を外国から来た子どもたちにも任せるにあたって、そうしたことを事前に職員会議で意味とともに伝え、先生たちとの間で共有していたそうです。あらかじめ教員間で意味を共有しておくことで、教員がチームとして連携を取れるようになります。それぞれのクラスで、そうした放送があったときに、先生が率先して「わあ! かっこいいね!」という言葉を出して価値をつくることによって、「笑われる」「馬鹿にされる」という状況を回避したり、「大事な価値は何か」という問いを学校全体で共有していくことにもなっていきます。それはまさに、学校全体で、いわゆる「チーム学校」として、異なる文化や言語の価値を認めていくことを促しているのだといえます。学校は、年度ごとに先生たちが入れ替わっていきます。だからこそ、こうして職員室内での取り組みの意味を共有する対話を繰り返し繰り返し行うことが大切になっていきます。こうした土壌を地道につくっていくことで、「放送委員」のエピソードのような一つ一つの取り組みも輝くようになっていくのです。
もちろん、「放送委員」のエピソードはあくまで一例ですが、ほかにも、小さなものでいえば、子どもたちのがんばった作品を掲示することもそれにつながるでしょうし、大きなものでいえば、学校行事への取り組みも入るでしょう。それらは実は、先生がたが「ふだんからしていること」の一部なのではないでしょうか。多文化を認め合っていく学校づくりは、その意味で特別何も変わったことではなく、先生がたのふだんの取り組みの延長線上にいつもあるのだと思います。
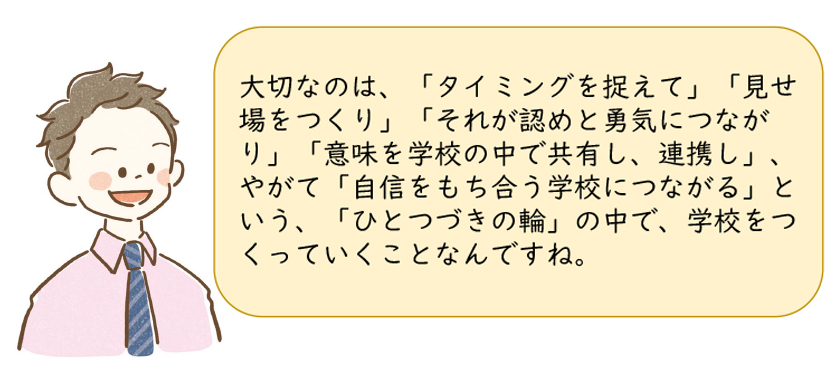
【著者プロフィール】
言語的文化的に多様な子どもたちをめぐって、ことばと文化の共生の点から力のある授業と学校をデザインしていこうとする教師教育の仕事をしています。







