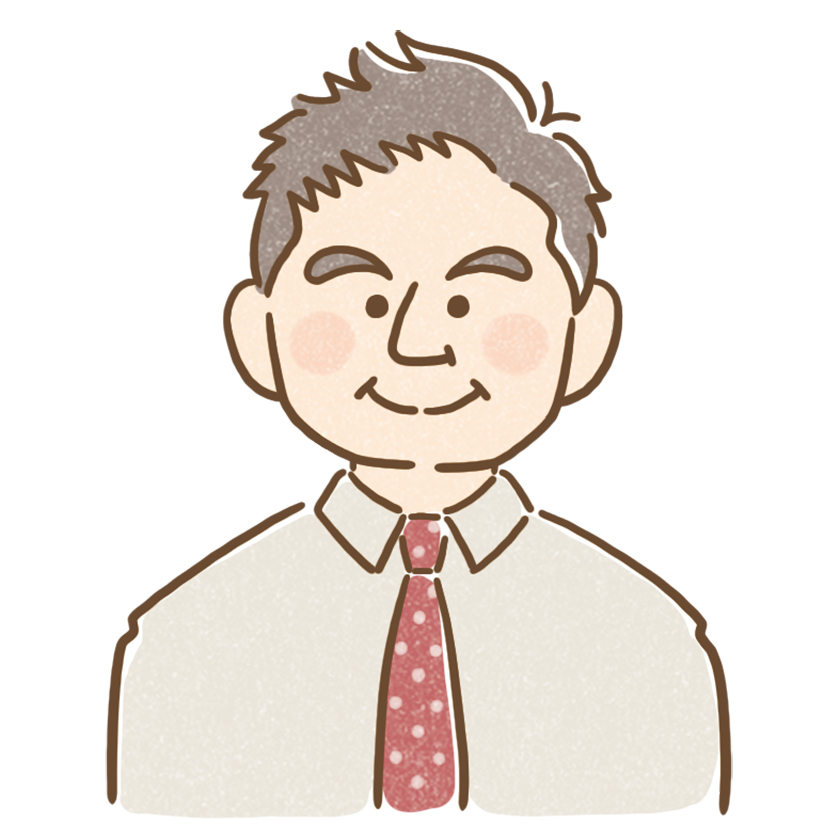第9回 子どもののびしろを評価する、価値づける
広島大学大学院人間社会科学研究科准教授
カトウ先生:評価をするって難しいなと改めて思った。結果的によかったんだけどね。
ハヤシさん:ミンさんのこと?
カトウ先生:そう。学期末になって通知表をつけるところで、ミンさんをどうするかということになって。
ハヤシさん:日本語がまだ十分じゃないということが、成績をつけるうえで問題になったの?
カトウ先生:いいところはいっぱいあるのだけれど、テストの点が高くないから、それをどう考えるかということになって。
ハヤシさん:でも、「テストの点」と「評価をすること」と「成績をつけること」って、一緒じゃないんじゃないの?
カトウ先生:まさにそうなんだよ。それ、実は校長先生にも「テストが全てじゃないでしょう。ミンさんのことを見てあげないと」と言われて、ハッとしたんだ。
ハヤシさん:そもそも何のための成績づけなのか、ということがあるもんね。
カトウ先生:そうなんだよ。僕は何のために、何を見て、何をつけているんだろうという気になった。
ハヤシさん:評価には、子どもの力を確かめて伸ばしていく面と、子どもの力を他者に示して納得をつくる面の両面があるよね。でも、ついつい前者の方は忘れて、後者の方ばかり気にすることってあるよね。
カトウ先生:そうだね。学期末の通知表って、本来は前者の方を保護者と共有していくものだと思うんだけどそれがうまくいかなくて。そんなときに、校長先生が「通知表はテストの評価で値踏みするものじゃないから」と言ってくれたのはありがたかった。
ハヤシさん:それでどうしたの?
カトウ先生:うん、大きくは2つのことを大事にしたよ。
ハヤシさん:2つ?
カトウ先生:1つはね、テストだけではなくて、ふだんの学習への取り組みの様子や、日本語指導の先生からお話をうかがったりして、ミンさんのがんばりや成長を見てそれらを大事にしたんだ。
ハヤシさん:いわゆる「個人内評価」を大切にするということだね。ミンさんの中での成長を、クラスの中と日本語教室の間で共有しながら見たんだね。
カトウ先生:そう。もう1つは、何というか、言葉と内容を分けて考えてみようとしたことかな。
ハヤシさん:それはすごく大切なことだね。「言葉の不十分さ」と「考えていること」を一緒にしないということだもんね。
カトウ先生:そうなんだ。実際はちょっと難しいことでもあるんだけど、ミンさんが言っていることの意味をちゃんと解釈して「ああ、こういうこと考えているんだな」ということを見ていこうとしたんだよ。
連載第9回は「外国につながる子どもたち」と「評価」について考えます。「評価」のやっかいなところは、この言葉がとても多様な意味をもっているからです。
今回、カトウ先生が「難しい」と言っていたように、学校現場では「客観性、公平性、説明責任」という言葉が評価をめぐって浸透しています。これは2つの意味で問題を抱えています。
第1の問題は、「何のための評価なのか」ということです。本来、学校においてなされる学習の評価は、「目の前の具体的な子どもたち」の成長と向き合い、その子どもたちに対して責任をもって応答していくことが重要です。しかし、近年は子どもたちに対してではなく、行政評価や市民の「監査」に対するもの、さらに顔の見えない不特定多数の人々に対するものなどへの「説明責任」が頭をよぎることが多くなり、それを担保するための「客観性」や「公平性」に席巻されています。
第2の問題は、こうしたことを推し進めると、返って子ども一人一人に対して応えていく側面は捨象されていくことです。特に外国につながる子どもたちのような言葉のマイノリティの場合、これまでの評価が、基本的に「言葉」で可視化されたものでなされてきたために、その「言葉」が表出されなくなると、本来もっている可能性をあらゆる場面で評価してもらえない状況が生み出されかねません。それは本当の意味で「公平」とは呼べないでしょう。
こうしたことからも、カトウ先生の行った対応はとても重要です。ただ、「説明責任」の論理が渦巻く中、こうした取り組みを進めていくには、学校管理職や自治体の教育行政の理解が不可欠です。
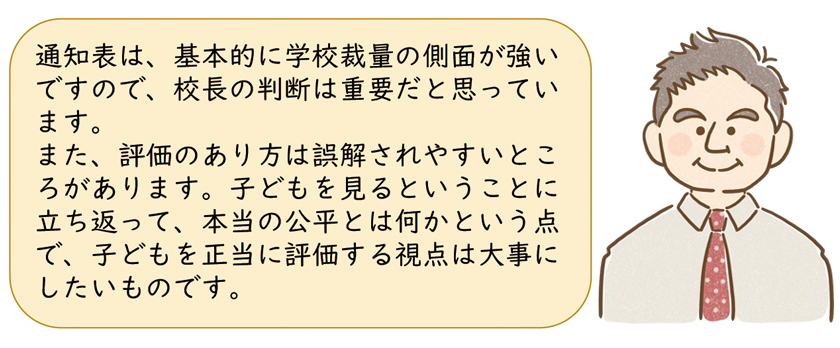
マイノリティの子どもたちの評価を考えるにあたっては、いまいちど「何のための評価なのか」というところに立ち返って、慣行的になされてきた評価の発想を捉え直していくことが欠かせません。教育課程において示された目的や目標を、その子どもがどのように学び取り、どのような成長の価値があるのかというところに立ち返って、その価値を検討していく必要があります。
先に、「評価」という言葉には多様な意味が含まれているといいましたが、学校現場、教育行政、教育学の研究、言語教育の研究の間では、それぞれが関係し合いながらも、異なる点を強調していることに注意する必要があります。
近年、学校現場では、評価というと「客観性、公平性、説明責任」という言葉で彩られることが多いといわれます。学年末に公文書として作成する指導要録よりも、学期末ごとに保護者や児童・生徒に渡す通知表のほうに焦点が当たることも多くあります。一方で、教育行政から求められているものは「観点別評価」や「指導と評価の一体化」というものです。これらは必ずしも「客観性、公平性、説明責任」によってなされるものというばかりではなさそうです。通知表のことかと思えば、指導要録の話であることも多く、学校現場が受け止め、慣行となっていることと、教育行政が示していること(場合によっては慣行の見直しを示すことも)の間にはズレが見られます。教育学の研究では、こうした現場と行政のズレを修正し、より深く両者が理解し合えるものにしていくための提案が中心になされています。
学校を取り巻く中でなされるこうした評価(以下、学習評価[あるいは教育評価])に対して、言語教育の研究からは、外国につながる子どもたちの「ことばの力」が、今どうなっているのかを可視化するアセスメントツールを指して、「評価」という言葉が用いられることが多く見受けられます(以下、言語評価)。例えば文部科学省から出されている「DLA」(外国人児童生徒のためのJSL対話型アセスメントDLA)や、早稲田大学の川上郁雄研究室が出している「JSLバンドスケール」などがよく用いられています。これらは、子どもたちの「ことばの力」を見るためのものであるため非常に重要なものである一方で、必ずしも上の学習評価そのものではありません。
こうした言語評価を学習評価として生かすには、単に「ことばの力が今どうなっているか」を測定するためのツールとして用いるだけではない発想が必要です。「つまずき思考」の根拠を与えることにつながることもあるからです。そうではなく、そうした「言葉が不十分なこと」という「つまずき思考」に隠れて見えにくくなっている子どもの成長や、学びの価値(のびしろ)を捉えていくためのツールとして使っていく必要があるでしょう。「DLA」であれば対話過程の中で、「JSLバンドスケール」であれば日々の子どもの姿の観察の中で、子どもが言葉の後ろ側で、自分の考えを表現しようとしているその姿を捉え、価値づけていく。それが見えたら、カトウ先生の言うような「言葉と内容を分けて考える」ことにも近づいていき、冒頭にあったような通知表の問題を解決していく手がかりにもなるはずです。
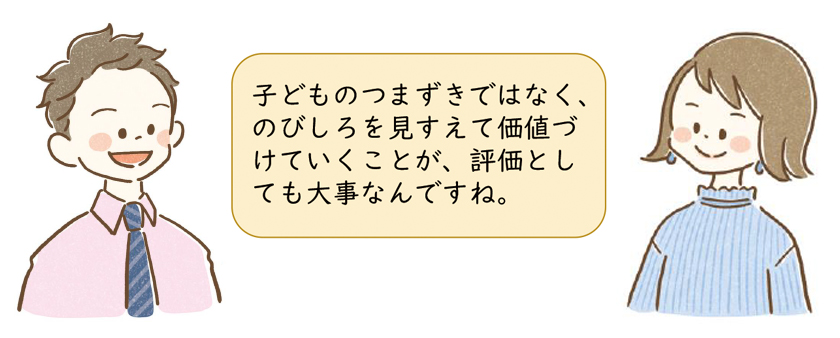
注:学校現場において「客観性、公平性、説明責任」が浸透していることについては、下記の文献に拠っています。高等学校向けとありますが、評価の考え方については小中学校でも同様の視点を得られるはずです。
参考文献:八田幸恵・渡邉久暢 著『深い理解のために 高等学校観点別評価入門』(学事出版 2023年)
【著者プロフィール】
言語的文化的に多様な子どもたちをめぐって、ことばと文化の共生の点から力のある授業と学校をデザインしていこうとする教師教育の仕事をしています。