#3 すがすがしい朝にする
香川大学教育学部准教授
【著者プロフィール】
東京都小学校、広島大学附属三原小学校等を経て現職。小・中学校の先生がたと社会科、総合的な学習の時間、生活科の授業づくりにともに取り組んでいる。
香川大学教育学部准教授
 |
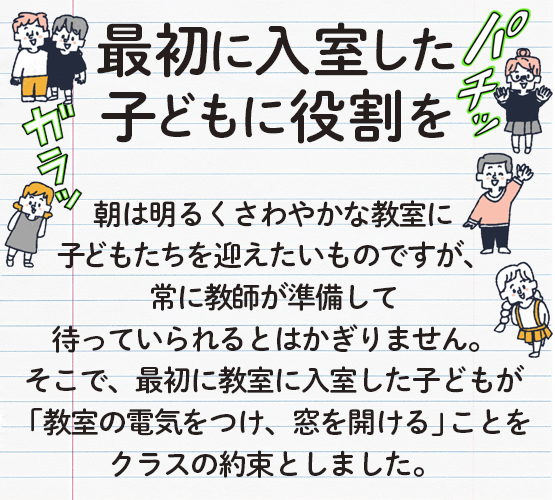 |
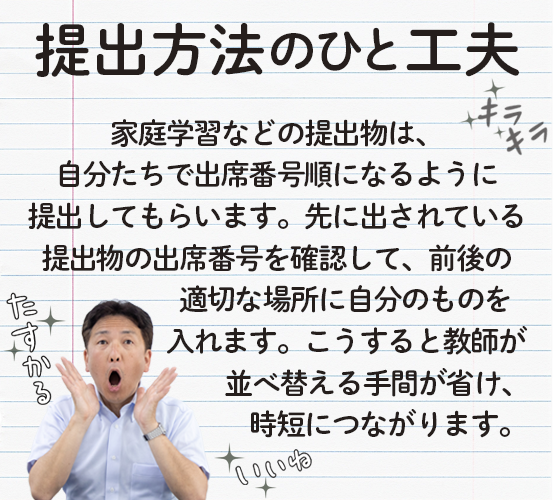 |
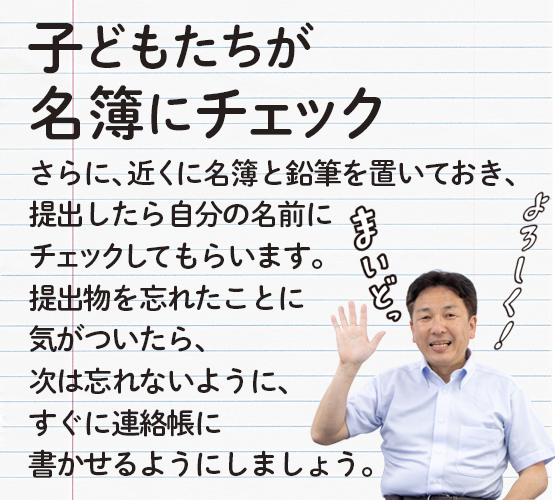 |
|
朝、廊下を歩いていると、教師が教室に入ってくるまで、ずっと電気がついておらず、暗いままになっているクラスが気になりました。そういったクラスは、晴れた日でも窓も開いていないことがあります。これでは朝から空気もどんよりして、子どもたちの気分も晴れません。 「電気をつける」「窓を開ける」ことを当番の仕事にしている学級が多いようです。しかし、その当番の子どもが始業ぎりぎりに登校した場合、当番ではない他の子どもたちは遠慮をしてしまいます。私のクラスでは、最初に入室した子どもが「電気をつけ、窓を開ける」という約束をしていました。これは、専科教室から戻ってきた際にも同様でした。ですから神野学級に「電気をつける」「窓を開ける」当番は、ありませんでした。 また、朝の時間には、提出物の確認や点検もあります。空き時間や放課後に名簿を見ながら提出確認をする時間を省くために、子どもたちに出席番号順に提出してもらい、そのチェックまで名簿にしてもらえば、作業の軽減につながります。提出忘れがあったら、その場で連絡帳に記入してもらい、再発を防ぐようにします。これは最初に教えてあげれば、小学生でもできるようになります。もちろん、集金袋や保健関係の提出書類等については金銭トラブル防止や個人情報保護の観点から、このような対応は行いません。 朝はすがすがしいスタートをきりたいものです。欠席する児童からの電話対応などのために、校内放送で呼ばれて職員室に戻るといったことは、DX化が進んだこともあり、以前よりは減ってきました。それでも教師にとって毎朝の時間は忙しいものです。 朝の時間帯での少しの工夫ですが、こういった業務改善を積み重ねることが、大きな時短につながっていきます。 |
【著者プロフィール】

東京都小学校、広島大学附属三原小学校等を経て現職。小・中学校の先生がたと社会科、総合的な学習の時間、生活科の授業づくりにともに取り組んでいる。
