#4 給食の配膳
香川大学教育学部准教授
【著者プロフィール】
東京都小学校、広島大学附属三原小学校等を経て現職。小・中学校の先生がたと社会科、総合的な学習の時間、生活科の授業づくりにともに取り組んでいる。
香川大学教育学部准教授
 |
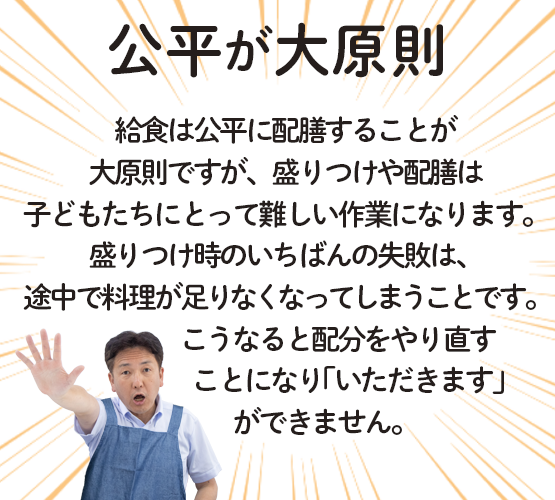 |
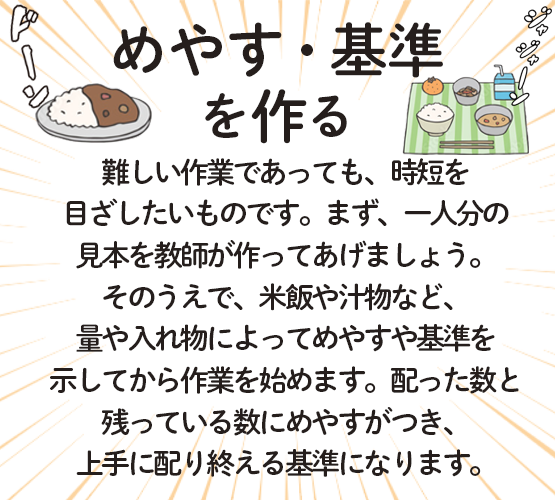 |
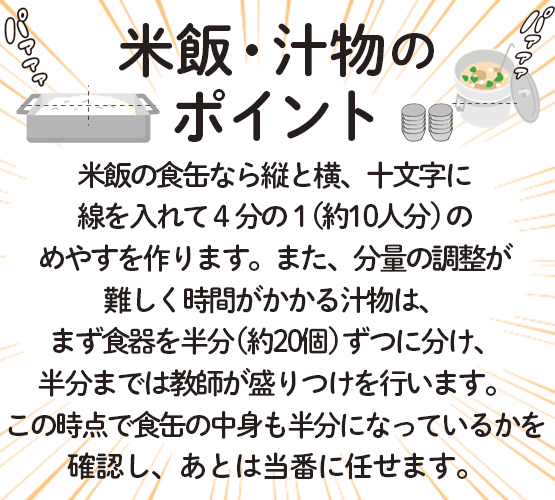 |
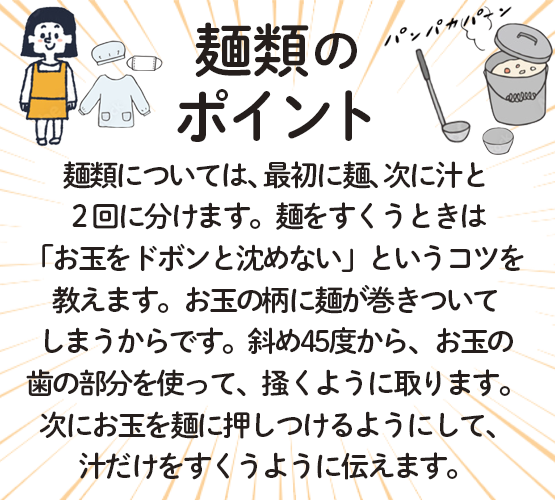 |
|
「食い物の恨みは怖い」ということわざがあるように、給食は公平に配膳することが大原則です。しかし、盛りつけや配膳は子どもたちにとっては難しい作業になります。盛りつけ時のいちばんの失敗は、途中で料理が足りなくなってしまうことです。こうなると配分をやり直すことになり「いただきます」ができません。給食の配膳や片づけが遅れてしまうと、掃除や昼休みにも時間がずれこんでしまい、給食室や給食委員会にも迷惑がかかってしまいます。 しかし難しい作業であっても、効率化・時短を目ざしたいものです。私は配膳時には給食当番に「いちばん困るのは途中で料理が足りなくなること」「少なくとも2名分は食缶に残すこと」を伝えていました。これはなんらかの問題が起きた際の保険です。分量が多少余った場合には、おかわり分に回します。 さらに補足すると、汁物では数回に1回、下に沈んでいる具材を混ぜて上に浮かせることが大切です。(ウズラの卵など)人数分以上あるものでも、最初は一人一個などの定量として配膳し、残りはおかわりで配ります。 また、米飯担当の子どもには、「欠席者分のおわんに、しゃもじを浸す水をくんでくる」などのきまりごとを共有させておくことも効率化につながります。配膳の時間を短縮できれば食事の時間が長くなり、楽しい給食の時間を過ごすことにつながっていきます。 |
【著者プロフィール】

東京都小学校、広島大学附属三原小学校等を経て現職。小・中学校の先生がたと社会科、総合的な学習の時間、生活科の授業づくりにともに取り組んでいる。
