#5 給食の「おかわり」
香川大学教育学部准教授
【著者プロフィール】
東京都小学校、広島大学附属三原小学校等を経て現職。小・中学校の先生がたと社会科、総合的な学習の時間、生活科の授業づくりにともに取り組んでいる。
香川大学教育学部准教授
 |
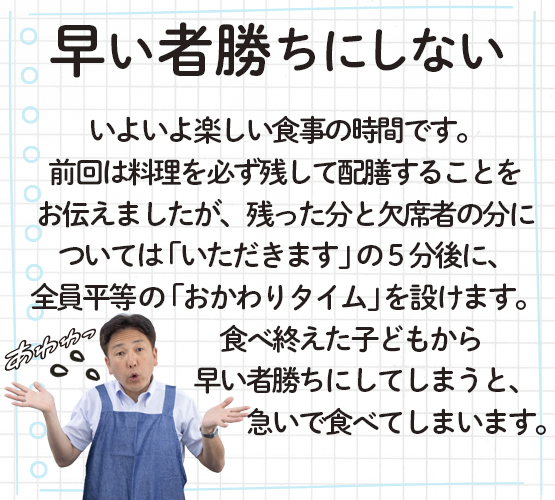 |
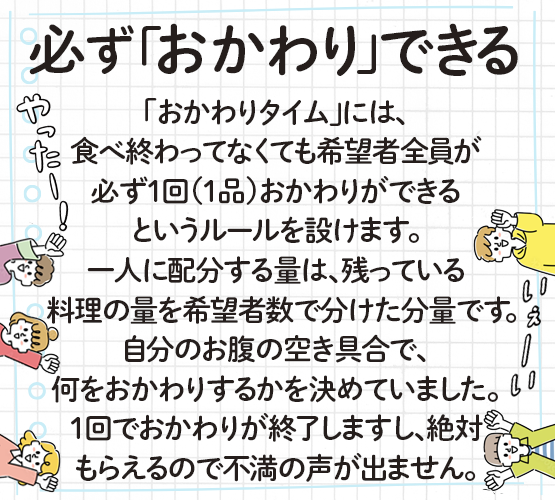 |
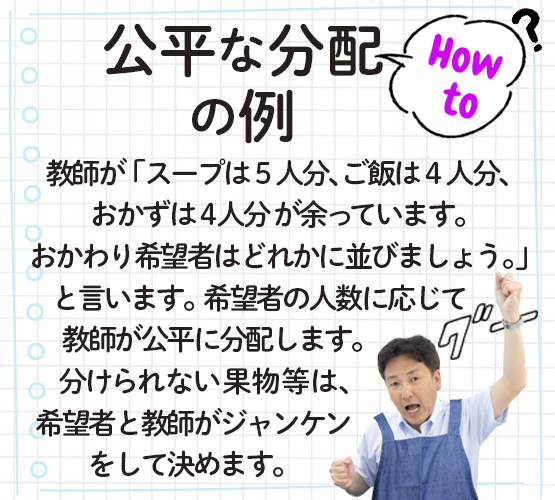 |
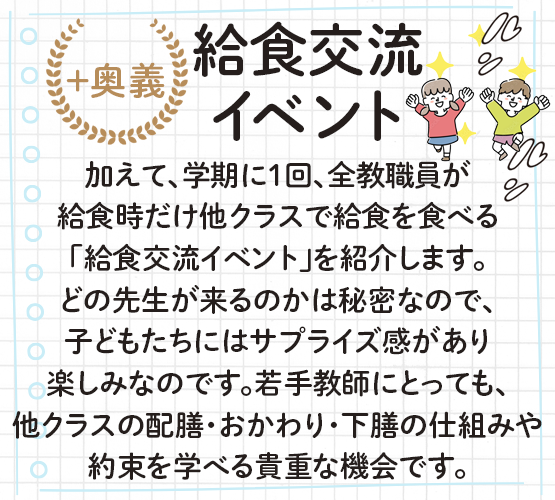 |
|
「おかわり」の大原則は「早い者勝ちにしない」「公平な分配」「教師がしきること」です。ちなみに、牛乳のおかわりは1本にとどめました。子どもたちが場の雰囲気に流され、調子に乗って、牛乳を2本も3本も飲むと、その後の掃除時間や昼休みにおう吐しがちだからです。 学期に1回実施した「給食交流イベント」の補足をします。当日は校長先生(教頭先生は職員室で電話対応)、専科の教師、学級担任だけが教室の移動をします。教室を訪問するのは配膳時からですが、教師は口を出さず、見守ります。実施にあたり、当日は4時間めの終了時間を守ることなどの共通理解を図ります。もちろん、食物アレルギー児童の情報共有や除去食の提供については、事前に確実な情報共有を行っておきます。 若手の教師にとっては、他学級の給食時の仕組みや約束を学べるだけでなく、一緒に食事をすると、そのクラスの雰囲気を感じ取ることができます。交流することで、学級の風通しがよくなり、複数の目で各学級の変化に気づけます。交流イベント当日は、「どの先生が来るのかな」「神野先生。どこへ行くかを内緒で教えて」などと朝から子どもたちは話題沸騰です。まずは、年間1回から始めてみてはいかがでしょうか。 また、学校栄養教諭・栄養士とのコラボも可能です。例えば小学校5年生社会科「農業の盛んな地域」で米離れ問題を学習した日に、米粉パンを出してもらいます。これは、1か月前の献立を決める時までの段階で、早めに栄養教諭に相談とお願いをしておきます。さらに、事前に放送委員にお願いし、当日のお昼の放送枠を少しだけもらうこともしました。子どもたちは、社会科の学びと関連づけながら、給食に米粉パンが提供された理由を誇らしげに語っていました。 |
【著者プロフィール】

東京都小学校、広島大学附属三原小学校等を経て現職。小・中学校の先生がたと社会科、総合的な学習の時間、生活科の授業づくりにともに取り組んでいる。
