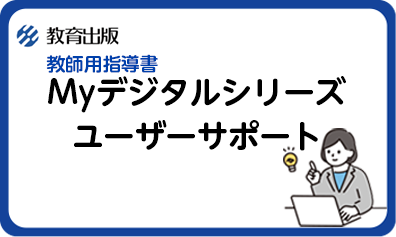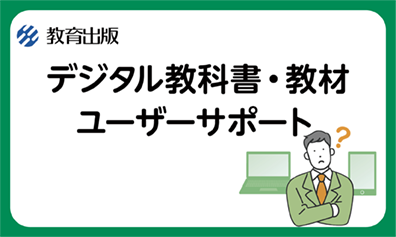霧笛
すやまたけし
ぼくの町には運河がある。モント川とオーデ川を結ぶその運河は,ぼくが生まれるずっと前に,マージによって作られた。マージはぼくの祖父の兄にあたる人で,昔は土木設計技師だった。あちこちに彼の作った用水路,池,港,ダムなどが残っている。しかし,マージにとってここの運河がもっとも愛着があったようだ。運河を見おろせる小高い丘の上の家に一人で住んでいた。マージは子供も孫もいなかったので,ぼくと弟をよくかわいがってくれた。ぼくたちはよく彼の家から運河を眺めたものだ。
運河が往来する船で栄えたのは遠い日のことだ。町は活気があり人々でにぎわった。ぼくは,それを知らない。
鉄道がこの町を通る計画がたてられた時には,町中が反対した。もちろんだ。町は運河によって成り立っていたのだから。鉄道なんて通ったら,仕事がなくなってしまう。
鉄道はこの町を避け,隣の町を通ることになった。
その後,当然のように輸送は船から鉄道に移っていった。時代の流れというものだ。そして,運河を通る船はなくなった。隣の町は栄え,この町は寂しくなった。
現在,運河は忘れられ,眠りつづける巨人のようにひっそりとたたずんでいる。
だから,今度,運河の一部を埋めてその上に高速道路を通すことになった時には,少数の者をのぞいて,反対する者はいなかった。
反対する人たちは言った。
「運河は過去に,この町をうるおしてくれた。船が消えた今も,運河の流れや河岸の緑は私たちの目を楽しませてくれている」
ぼくも同感だった。それになによりも運河はマージが一所懸命になって作り,今でも大切にしている。そして,丘の上から毎日,懐かしそうに暖かい目で見守っている。
しかし,マージは高速道路に反対ではなかった。彼は静かにぼくに話してくれた。決して負けおしみではなかった。
「うん,確かに運河を残したい人の気持ちもわかる。私だって運河はかわいい。私の若い日の情熱と思い出をそのままの姿でとどめているように見える。だが,私の作った運河は本当にみんなのためになったのだろうか。この運河のせいで鉄道が通らなかった。それに,この土地や自然は運河ができるのを本当に望んでいたのだろうか。運河を作る時に,森を切りはらい,丘を削りくずし,野原を無残に掘りかえしてしまった」
「運河が作られる前の自然は忘れられ,今では運河に郷愁を覚える。しかし,運河が埋められ,その上に高速道路が作られれば,やがて運河のことも忘れられるだろう。何十年かたち,高速道路が古くなり,それを壊さなければいけなくなる頃には,その高速道路に郷愁を感じる者が出てくるかもしれない。それに,高速道路を作る設計技師だって,私と同じように仕事に誇りを持っているだろうし,できた道路に愛着を感じるだろう」
マージが言うのを聞いて,ぼくもそのような気がしてきた。
結局,町のみんなの意見はそろって,高速道路を通すことになった。何年か後に運河のかわりに高速道路ができるだろう。その時にはまた,この町も変化しているだろう。
マージが冬を越せたのは,ある意味で奇跡と言えるかもしれない。すっかり弱っていて,現に何度か高熱を出し,あぶない時もあった。
ぼくたちもマージの容体を気にして,ぼくたちの家にくるように勧めたが,彼は丘の上の家をはなれようとはしなかった。マージは言った。
「ありがとう。みんなの気持ちはうれしいよ。でも,私はここに住んでいたいんだ。ここからは運河が見えるし,この風景が好きなんだ。あの運河か私のどちらかが消え去るまで,私はこの家にいるつもりだよ」
これにはぼくたちも無理に反論することはできなかった。そのかわり,みんなで交代で看病した。
その日はぼくがつきそっていた。春の夕暮れ,薄かったもやは次第に濃い霧に変わっていった。何日か前から,マージは具合が悪く食欲もなくなっていた。ぼくたちはとてもそれを心配していた。まどの外は少しずつ暮れていった。すっかりミルクのようになった霧が横に流れて,少し先の立木が,ぼんやりとした影になった。ぼくたち二人だけが白い闇のなかに取り残されていくような気がした。
その時,かすかに遠くのほうで霧笛の音がした。
「ねえ,マージ,聞こえた?今,霧笛が鳴った......ほら,やはり鳴っている」
「まさか......昔はこんな霧の深い日は,運河を行く船が霧笛を鳴らしたものだが。今は船も通らないし......うん?あれは?私にも聞こえた。遠いけれど」
ぼくたちは耳を澄ませた。厚い霧のベールを通して運河のほうから,しかも徐々に大きくなってくる。確かに霧笛の音が聞こえる。
「船だ。私の運河をモント川のほうから船がやってくる」
マージは目を輝かせて,ぼくに言った。その目は何かを思い出しているようだった。
ぼくはやはりやって良かったんだと思った。マージをだますことに初めはうしろめたさもあったが。ぼくはこの日のために町工場のカルノさんに頼んで霧笛を作ってもらった。
それを弟が運河の岸で鳴らしているのだ。
「ああ,懐かしいな。もうじきこのあたりを通る。霧が濃くて窓から見えないが。私の運河を船が通っている」
マージはうっとりと目を閉じて,群れからはぐれた象が鳴いているような哀しい霧笛の音を聞いている。その時,足音がしてドアが開いた。弟だった。ぼくはあわてて弟を外に押しもどすと,たしなめて言った
「しーっ,おい,せっかくの計画が台なしになるだろう」
弟は丘をかけあがってきたため,息をはずませながら言った。
「船が......ぼくが霧笛を鳴らしていたら......霧の中を......船が運河を通っているんだよ......。ほら,聞こえるでしょう?霧笛の音が......ぼくはここにいるのに」
半信半疑のぼくにも聞こえた。運河のほうで太い霧笛の音がする。
ぼくと弟は丘をかけおりていった。運河の岸は浅い緑でおおわれていた。運河は濃い霧につつまれていた。霧笛の音がゆっくりと近づいてくる。そして,霧の中に黄色いフォグランプをともした黒い船が浮かびあがってきた。霧笛が断続的に響く。ぼくたちはその幻影のような船を運河にそって追いかけた。
やがて船は運河からオーデ川にゆっくりと出ていった。その黒い影は霧に溶けこんでいく。霧笛の音も遠ざかっていく。
立ちつくしたままそれを見送るぼくは,マージのことを思った。あの船とともにマージも消えていくのじゃないか思った。そして,もうじきこの運河も......。
「さよなら,マージ,ぼくはマージのこと,忘れないよ。さよなら,ぼくはマージの運河のこと,いつまでも忘れないよ」
消えていく船に向かってつぶやくぼくの頬は,霧と涙でぐっしょりと濡れていた。
(『火星の砂時計』 株式会社サンリオ 1988年 現在は絶版)