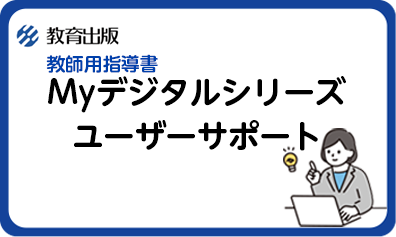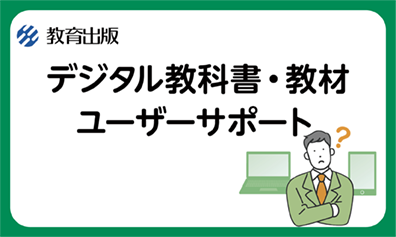仮面師の弟子
すやまたけし
仮面師ハルムの弟子のセイジは,まったく,とてつもない大きなことをやらかしたものだ。村人たちはみな,尊敬と驚嘆のいりまざった賛美の言葉をセイジに送っている。
セイジの岩山には,うわさを聞いた人々がその大きな成果を一目見ようと,遠くのほうからもやってくるようになった。やがて,その場所が巡礼地として賑わうようになるのではないかと地元の人々は話している。
おまけに,セイジときたら,それ一つだけに飽き足りないで,早くも次の岩山にとりかかっているそうだから,「セイジは本当に凄い奴だ」という評判はやがて,いっそう確かなものになるだろう。
このままいくと,セイジのやらかしたものは,あちこちに残るだろうし,きっと多くの人々によって,この物語はのちのちにまで語りつがれることになるだろう。
仮面師ハルムの作る仮面は,どれも感情ゆたかで素晴しいものだった。「冬の孤独」と題した年老いた男の仮面は,人生の哀愁と奥深さを感じさせたし,「白い微笑」と題した女の子の仮面は,無邪気さと若さの喜びをあふれるほどに表現していた。
ハルムの作る仮面はどれも,見る人に最大の感動と想像力をあたえた。しかも,その仮面の表情は見る人によって,微妙に変わったし,同じ人間が見ても,見る時によってまったく別の仮面のように感じられた。
その典型が「無の鏡」と題した仮面だった。この仮面は見る人によって,それぞれがみな違う感想を述べた。
ある人は,この「無の鏡」の仮面を見て,「これは,かしこそうな男の子が何かを考えている顔だ」と言った。また,別の人は,「この仮面は,年老いた上品な女性が故郷を懐かしがっている顔だ」と言った。この仮面は見る人によって,老若男女,喜怒哀楽,実にさまざまな異なる顔と表情を見せた。この仮面は,「無の鏡」という名前どおり,見る人の心をうつす鏡のようだった。
セイジが,仮面師ハルムの弟子になろうと決心したのも,彼がこの「無の鏡」の仮面に出会ったからだった。彼はこの仮面を見て,遠くのはるかな水平線を見つめている少年の顔を思い浮かべた。
仮面師ハルムは,弟子にしてくださいというセイジを簡単に受けいれてくれた。セイジは,あまりにあっけなくハルムが彼を弟子にしてくれたので,肩すかしをくったようだった。セイジは,ハルムの家のはなれに住むことになった。そして,彼はハルムの弟子として,毎日の雑用や仕事の手伝いをするようになった。
ハルムとともに暮らすようになって,セイジはいっそう彼に対する信頼と尊敬をましていった。ハルムの生活態度は質素でおごりのないものだったし,仕事は厳格でごまかしのないものだった。
ハルムは,一日のほとんどを仕事部屋で過ごした。仮面を彫っている時の彼の横顔は厳しく,セイジが言葉をかけるすきもなかった。しかし,日常に関しては,ハルムはセイジに対して寛大なところを見せた。セイジが不慣れから少しぐらい失敗しても,「今度から,気をつけなさい」と言うだけだった。
ところが,セイジが弟子になって随分たっても,ハルムは仮面を彫る技術を彼に一つとして教えてくれなかった。
ハルムはセイジに言った。
「時間があったら,私が仮面を彫っているところを見なさい」
だから,セイジはよくハルムの仕事を横で黙って見ていた。ハルムも,セイジがいようがいまいが,いつも黙々と仮面を彫りつづけていた。
ハルムは仮面の彫り方を直接,セイジに教えたりはしなかったが,時々,手があいた時に話しかけてくれた。その話は,仮面とは無関係な話も多かったが,セイジはどの言葉も心にきざみつけておこうと思った。
ある時,ハルムはまだノミを入れていない木のかたまりを前にしてセイジにきいた。
「この木を見て,何が見える?」
セイジはその木のかたまりを長い間じっと見つめていたが,あきらめて答えた。
「わかりません」
ハルムは,別の同じような木の素材をならべて言った。
「この木も,この木も,同じ木だし,形も大きさも似ている。しかし,私にはそれぞれ別の顔が隠れているのが見える。いいかい,私はこの木に埋もれている顔をそのままの形に彫り出してやるだけなのだ。私が仮面を作るのじゃない。この木の中にある顔を,私は彫り出すだけなのだ」
セイジはハルムが言おうとしていることが,何となくわかるような気がした。しかし,どれだけ見なおしても,木の中にひそんでいるという顔を見ることはできなかった。
ハルムはその木の一つを前に置くと,ノミとハンマーを持ち,彫りはじめた。大胆に粗削りをはじめると,仮面の輪郭がおぼろに浮かびあがってくる。そして,いくつかのノミに持ちかえながら彫りすすむと,木の中に埋もれていた顔が現われてくる。その仮面は幼い男の子の顔のように見えた。そして,その仮面を横に置くと,ハルムはもう一つの同じような木のかたまりにとりかかった。
ハルムの魔術師のような腕によって,木の中に眠っていた顔が目覚めはじめる。今度の木からは女性の顔が浮かびあがってきた。
セイジは言葉もなく,ハルムの不思議な手先をただぼうぜんと見つめるだけだった。
セイジは毎日,ハルムの作業を見て,その一つひとつを頭にたたきこんで,自分でも仮面を彫ってみようとした。しかし,セイジには木に埋もれているという顔も表情も見通せなかったし,ハルムのようにそれを彫り出してやることもできなかった。セイジの彫る仮面は,まだまだ未熟だった。
季節は流れ,時が過ぎていく。
セイジは仮面を幾つもいくつも彫りつづけたが,相変わらず,思いどおりの仮面を彫ることはできなかった。失敗作が山のように積み上げられていく。
ある日、セイジはいつものように森の中を歩いていた。ハルムが森の木を見ていると,その木の中に埋もれている顔が見える,と教えてくれたことを試しているのだ。しかし,セイジには森のどの木にも顔を見ることはできなかった。
セイジは一休みして,その岩山をぼんやりと眺めていた。ふと,彼の頭にひらめくものがあった。彼は,岩山を凝視した。
「やはり」セイジは背中に何かが走るのを感じた。大地に眠る偉大な神の啓示だろうか。セイジはふたたび,岩山を見た。
セイジは,確かに岩山に埋もれている顔を見たのだった。彼は急いでノミとハンマーを取ってくると,その日から岩山にとりかかった。そして,大変な苦労の末に,今,評判になっている岩山の巨大な顔を彫りあげることができたのだ。
もちろん,そのできばえは師匠の仮面師ハルムによって保証されているし,その素晴しい顔を拝みに遠くからも人がやってくるようになった。
そして,人々の絶賛と期待を浴びたセイジは,今は次の岩山に埋もれている顔を彫り出そうと,一生懸命になっているということだ。
(『火星の砂時計』株式会社サンリオ1988年現在は絶版)