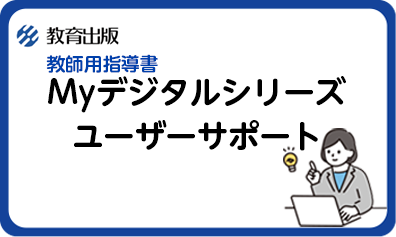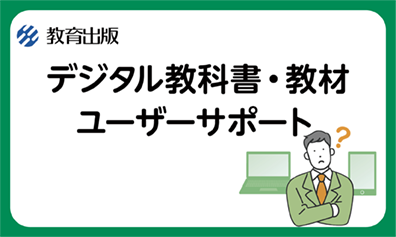一輪車の村
すやまたけし
ぼくは空色の自転車を走らせた。風と競争するように,過去から逃げるように。
初夏の陽差しは強く,ぼくはうっすらと額に汗をかいた。草原は陽に輝き,緑色に燃えていた。その中の一本道を,ぼくの自転車は走りつづけた。自転車のうしろには,大きな荷物が乗っている。ぼくは遠い遠い土地から,何日も何日も長い道のりを旅してきた。
なだらかな丘,一面の草原,空は晴れわたり,白い雲がぼくと同じように,あてもなく旅をつづけている。
丘を越え,自転車はゆるやかな坂道をすべるようにくだっていった。その先には川があり,やがてぼくは石でできた橋を渡った。
村の入口の標識を過ぎて少しいくと,右側に高い給水塔が見えてきた。給水塔のそばにはポンプ小屋があり,その先に小じんまりとした家が一軒,建っていた。
のどが乾いていたぼくは自転車をおり,その家のドアをたたいた。
ドアが開いて出てきたのは,年をとった男だった。ぼくが水を頼むと,彼はおだやかな笑顔で,疲れた顔のぼくを家の中へいれてくれた。彼はぼくに椅子をすすめ,冷たいミルクを持ってきてくれた。
ぼくは礼を言って,そのミルクを一気に飲みほした。乾ききったのどに,それはとても気持ちよく感じられた。
彼はオットーという名前で,村の水をすべてまかなう給水塔を管理していた。オットーはぼくに,自分の仕事や村のことを楽しそうに話してくれた。
ぼくは彼と話しているうちに,それまでの疲労もうすれ,安らぐことができた。
それに,彼がぼくの過去を根ほり葉ほり聞かないのも,ぼくにはうれしく感じられた。
オットーはぼくが行くあてもないのを知って,言った。
「きみさえ良ければ,ここにずっといてもいいんだよ」
ぼくはここで親切な彼の仕事の手伝いをしてもいいと思った。もし仕事が向いていなかったり,ここが自分の安住の地でないことがわかれば,ふたたび旅に出ればいいのだ。ぼくが,よろしくお願いしますと言うと,オットーは喜んだ。そして,彼はつけくわえて言った。
「ただしね,この村ではみんな,道を行くのに一輪車に乗らなければならないんだ」
「ぼくは一輪車になんか乗れないし,一輪車を買うお金も持っていませんが」
「それなら,心配いらない。きみなら,すぐに乗れるようになるから。それに,一輪車は,きみの乗ってきた自転車を,村の機械屋が作りなおしてくれるよ」
ぼくは,すべてをオットーにまかせる気になった。ぼくは自転車から荷物をおろし,彼に案内された部屋に運んだ。こぎれいにかたづけられたその部屋は,ぼくにとって気にいるものだった。
その日の夕方,村から少女が新鮮な野菜をカゴに一杯,とどけにきた。彼女はオットーのところへ,食料品や雑貨を運んでくるのが役割だった。もちろん,彼女は一輪車に乗っていた。
オットーは彼女にぼくを紹介して,帰りにぼくの自転車を機械屋のところへ持っていくように頼んだ。ぼくは,一輪車に乗って自転車を押しながら村のほうへ帰っていく彼女のうしろ姿を,感心して見送った。
数日後,機械屋が一輪車に乗って,荷車をひいてきた。荷車には給水塔のための何かの部品と,空色の一輪車が二台つんであった。
その日から,ぼくは一輪車に乗る練習をはじめた。オットーと食料品をとどけにくる少女が,その練習を手伝ってくれた。
一週間もすると,ぼくは自由に一輪車に乗れるようになった。
さっそく,ぼくは一輪車で村の方へ出かけてみた。村に近づくと,一輪車に乗った村人たちが,見なれないぼくを笑顔で受けいれてくれた。村中をぼくは走りまわった。
村の家々は色とりどりの屋根が美しく,村人たちもみんな快活だった。
その後,少女と二人で村の反対側のはずれまで行ったことがあった。村の入口と同じように川が流れていて,石の橋がかかっていた。その前までくると,彼女はぼくを止めて,村のしきたりを教えてくれた。ここから先へはぼくたちは行ってはいけないということだった。
「どうして」ときくと,彼女は,この村に長く住んでいればわかるとだけ答えた。
ぼくは毎日を充実して暮らした。オットーから,ポンプや発電機の保守,点検,修理,補助ポンプの動かしかた,定期的な給水タンクの清掃,ペンキの塗りかたなどを習った。森は紅葉し,秋も終りに近づく頃には,ぼくはオットーの仕事をひととおり,真似できるようになった。彼はぼくを信頼してくれた。
ぼくは自分の町から逃れて,この村に来たことを,少しも後悔していなかった。
オットーが給水塔から転落したのは村にちらほらと雪の降った頃だった。前夜に降った雪が,給水塔の鉄骨に凍りついていた。オットーは点検のために給水塔にあがり,足をすべらせたのだ。
オットーはひどく足を痛めた。医者の治療もむなしく,もとどおりにはならなかった。
オットーは寂しそうに言った。
「歩けるようにはなるだろうが,もう一輪車には乗れないようだ。そろそろ,私は次の村にいく時期がきたようだ。それが,この村のしきたりだ」
そして,オットーが次の村へ越す日がやってきた。寒い日だった。オットーは荷車に横たわり,そのまわりを一輪車に乗った村人たちが囲んだ。
オットーも,村人たちも,みんな口を閉ざしたままだった。ぼくもその行列に,黙ってついていった。横には少女がぼくをなぐさめるようにならんでいた。
荷車と一輪車の長い行列は,静かに冬空の下を進んだ。そして,村の反対側の橋のところまでやってきた。橋の向こう側にはぼくの知らない人々の一群が待っていた。彼らは誰も一輪車に乗っていなかった。
ぼくは少し前から,わかりはじめていた。
(こちら側は一輪車の村。そして,向こう側は一輪車に乗らない人たちの村だ。オットーは橋を渡り,新しい生活をはじめるのだ)
橋の手前の広場でオットーの荷車は止まり,ぐるりとそれを一輪車が囲んだ。ぼくは前に進み出て,彼と握手した。彼の目を見ると,彼は気まずさをかくすように口をひらいた。
「一輪車はすっかりうまくなったじゃないか。もう他の人たちと変わらない。給水塔もすべてきみにまかせられるし,きっと,うまくいくよ。それに彼女がいるしね」
オットーはぼくのとなりの少女のほうを見た。彼女は恥ずかしそうにうつむいた。
やがてオットーを乗せた荷車は,みんなの見守る中,橋を渡っていった。そして,真ん中で向こう側の人たちに渡された。ぼくはオットーとのこの別れをしっかりと心にきざみつけておこうと思った。それに,またここにくれば彼と会えるかもしれないと思った。川をはさんでではあるけれど。
灰色の空の下の荘厳な儀式は終り,人々の群れはとけはじめた。川の水はなにごともなかったように,ゆるゆると流れていた。
(『火星の砂時計』株式会社サンリオ1988年現在は絶版)