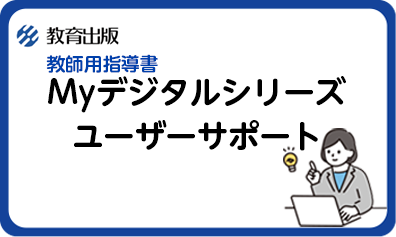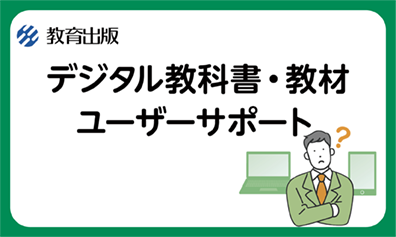ユラ山脈を救え!
すやまたけし
少年は畑を耕す手を休めて東の方角を見あげた。緑にあふれた農地と点在する森の向こうにユラ山脈が巨大な姿をゆったりと横たえている。山頂には白い雲がかかっていた。
ユラ山脈はユラ技師が造った人工山脈だった。少年も大人たちから,今では伝説になったそれが造られるまでの話を何度も聞かされていた。
少年が生まれるより遙かな昔,この地方は不毛の荒野がえんえんと広がっていた。地平線に囲まれたこの広い荒野は雨がほとんど降らず,乾ききった大地は何の役にも立たなかった。木も草も育たない荒野を西風が吹きすぎていくばかりだった。そのたびに乾燥した砂塵が舞い上がり,空は茶色く染まった。
ユラ技師はこの地方に吹きつづける強い西風を何とか利用できないものかと考えた。もし,東側に山脈があれば西風はその斜面にぶつかり上昇気流を生む。そして,山頂の付近で雨雲を生じさせるはずだった。
高さがおよそ八百メートル,長さは南北方向に三,四十キロメートルはあると思われるこの人工山脈を築きあげるまでのユラ技師の苦難と勇気の物語は,現在ではすっかり伝説化して伝えられている。
初めは,多くの者がユラのその無謀な計画を笑った。しかし,ユラは真剣だった。東奔西走し理解者をふやして,着実に自分の夢を実現していった。
ユラはまず山脈の骨組みに,巨大な支柱を二十本,等間隔に南北方向にならべて立てた。そして,それらの上端を特殊な索で順々につないだ。また,それぞれの支柱の上端から別の索を西側に向かって斜めにおろして,その二十本の索を地上に固定した。そして,テントの屋根を半分だけ張れるような形に,その斜めの索にそって巨大な膜を張った。そのようにして完成したのが,人工山脈のユラ山脈だった。
ユラが考えたとおり,この巨大な人工山脈に西風がぶつかると,斜めに張られた膜の面にそって上昇気流が山頂に向かって吹き上がり,上空の冷たい空気に冷やされ,少しずつ雲が成長した。そして,ついに雨が降りはじめた。この雨が降った時のユラの喜びようは多少オーバーに伝えられているが,思慮深く言葉少ない彼がこの時ばかりは大声で神に感謝したとしても不思議ではないだろう。
気圧,気温,湿度,西風などの具合によって雲のできかたも変化したが,この山脈のおかげでこの地方はそれ以来,雨に恵まれ,農業ができるようになった。そして村ができ,人々が定住するようになった。
ユラ山脈は,嵐や台風などで風が強い時には,その巨大な膜を斜めに張った索にそって降ろせるようになっていた。その時のユラ山脈の姿はちょっとした見ものだった。遠くからでもユラ山脈の偉容は眺められるのだが,その巨大な銀色の斜面の膜が少しずつ降りていく様子は壮観なものだった。そして,すべて膜が降ろされた後には,南北に二十本の支柱が巨人の国の電信柱のように点々と立ちつくしているのだった。
嵐が過ぎたあと,ふたたびユラ山脈に膜が張られる姿は,さらに誇らしく美しいものだった。地面から二十本の索にそって,巨大な膜が引き上げられていく。ある者はその姿を,巨大な帆船が帆を一杯に張る姿に例え,しかしまた,それよりもずっとずっと偉大で美しいと熱っぽく語った。
ユラ山脈の膜の上げ下げは,それぞれの索の根元に設置された動力によって行われた。そのための電力は山脈から少し離れた所に作られた風車の列から供給されていた。
このユラ山脈の操作をする技師は,村の中でもっとも信頼される男が代々つとめてきた。そして,村人たちから尊敬されてもいた。現在はモートという男がユラ山脈の操作技師として,ふもとの建物に一人で暮らし任務をはたしていた。
少年は伝説化した英雄ユラに憧れ,自分もユラのように夢を実現し,人々の役に立ちたいと思っていた。また現実的な将来の希望として,モートのように立派な技師になりたいとも思っていた。
少年は額の汗をぬぐうと,帽子をかぶりなおし,ふたたびユラ山脈の銀色に輝く山肌を眺めた。膜は風に揺れ,大きな波がその斜面を渡っていく。
明け方,少年は暴風雨の激しい音で目を覚ました。前夜,降りはじめた雨はしだいに激しくなり風も強くなった。夜中を過ぎるとひどい嵐になって,暴風雨が吹き荒れた。
少年はカーテンを開けてユラ山脈を見た。薄明の東の方向に雨の幕を通して,暗い雲のかかったユラ山脈の影が見えた。その姿のおかしいことに少年は気がついた。眠い目をこすりながら,もう一度しっかりと見つめなおした。やはり,変だ。こんな風の日はユラ山脈は膜を全部,降ろしているはずなのに,右から七本目あたりの索の上の方で膜が引っかかったままになっている。そのために,そこを頂点にしてその部分の膜が下がりきれずに,三角形の形に残っている。
少年は電話で村に知らせようと思い,受話器を取り上げた。しかし,何も音がしない。ダイヤルをまわしてみても駄目だった。おそらく,嵐で電話線が切れたのだろう。技師のモートのところへももちろん通じなかった。
少年はレインコートを着ると,風雨の中を出ていった。風は激しく,少年の顔に雨粒が叩きつけてきた。風に倒されそうになりながら,ユラ山脈のふもとにあるモート技師の建物をめざして進んだ。
モートの住む家は明かりがついていた。ドアを叩くと,モートが足をひきずりながら出てきた。
「どうしました,モートさん。ユラ山脈の膜が降りていませんよ」
「十四番支柱の索の膜が降りないんだ。操作盤を調べているのだが,動力が壊れたか,電線が切れたかで,膜を降ろすことができないんだ。少し前に,調べに外へ出たんだが,途中,凄い風で転んで左足を痛めてしまった。やっとのことで引きあげてきたところなんだ。電話は不通で誰にも連絡できないし,困っていたんだ。いいところに来てくれたよ」
「ぼくにできることがあれば教えてください」
「ああ,頼むとも。十四番の動力を調べてきてくれ。もし直せないようだったら......」
モートは倉庫室へ行き,小さい包みを持って帰ってきた。
「この爆薬を巻き取り索にしかけて,切断してきてくれ。早くしないと,逆風で,膜だけでなく,支柱まで被害を受けてしまう」
少年は爆薬を持って暴風雨の中を十四番の動力小屋に急いだ。
苦労してようやく動力小屋にたどりつき中にはいると,少年は機械のまわりを調べた。そして電動機と巻き取り機の間のギアが壊れているのを見つけた。少年の手にはおえないほどの壊れかただった。
少年はモートに言われたように,外に出て雨に濡れながら,巻き取り索に爆薬をしかけた。頭上のユラ山脈の膜は逆風にちぎれそうに,はためき暴れている。
少年は走って安全な場所まで離れると,爆薬のスイッチを押した。鈍い爆発音がして,頑丈な索がはじけとんで切れた。そして,上の方にひっかかっていた巨大な膜が解きはなたれ自由になると,東風にあおられて舞い上がった。少年は息をのんで地上にふせたまま,風にあおられて広がっていくユラ山脈の膜を見上げていた。やがて,その巨大な銀色の膜は少年の上にまでおおいかぶさってきた。
(『火星の砂時計』株式会社サンリオ1988年現在は絶版)