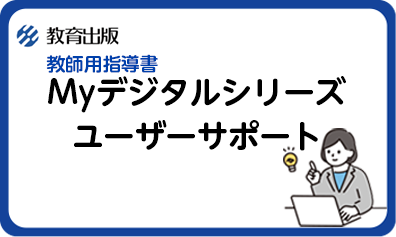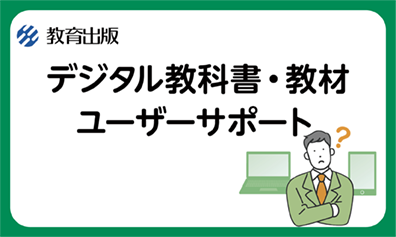火星の砂時計
すやまたけし
火星の赤い砂が,砂時計にもっとも適しているということは誰でも知っている。しかし,火星の砂時計を持っている人間は今のところ限られている。みんなが火星の砂時計を持つようになるには,まだ地球にある火星の砂の量はあまりにも少なすぎた。将来,定期的に貨物船が火星と地球の間を往復するようになれば,子供のお小遣いでも火星の砂時計を買えるようになるだろう。
少年の目の前にあるのは,正真正銘,本物の火星の砂時計だった。宇宙開発局に勤める少年の伯父が彼にくれた物だった。
少年は,赤い火星の砂が静かに流れ落ちるのを一人で見ているのが好きだった。自分の部屋で,机の上に置いた火星の砂時計を,じっと飽きることなく見つめた。
火星の赤い砂は粒子が細かく,一粒ひとつぶの形と大きさがそろっているために,非常に美しく精確に砂時計の中を流れ落ちた。砂時計の底に積もっていくその砂の山も,実に均整のとれた美しい形を見せた。
砂時計の砂は,目には見えない時間というものを,少年に実感として教えてくれた。少年はそれを見ていて,広大無辺の宇宙の広さと,悠々と流れつづける雄大な時間を思い浮かべることができた。
赤い砂はさらさらと柔らかく流れつづけ,砂時計の底にゆるやかな曲線の山を築いていく。そして,最後の赤い砂がガラス容器のくびれた部分をすべり落ちると,少年は再び砂時計をひっくり返した。
また,少年の目の前の時間が動きはじめる。
赤い砂が砂時計の底に積もっていく。じっとその砂の山を見つめているうちに,少年はその赤い砂の世界に引き込まれていくような気がした。
赤い砂が,さらさらと落ちてくる。風があるのだろうか,砂が横に流れていく。赤い砂丘,赤い砂の世界。少年の目の前に砂漠が広がっている。砂丘が美しい曲線を作り,その斜面を風が風紋を描きながら渡っていく。
少年は砂に足を取られながら歩いている。うしろを振り向くと,少年の足跡が点々とつづいている。やがて風と砂によって消えていくのだろう。
小高い砂丘を越えると,突然,目の前の砂漠に遺跡群が現われた。
装飾のついた石の柱が何本も立っている。ある物は傾き,ある物は途中で折れ,その全体から昔はそこに大きな神殿のような物があったことがうかがえる。
まわりにも,石を積み上げた壁や建物の跡が砂に埋もれるように広がっている。この廃墟は過去にかなり栄えた大きな都市の跡のようだ。そして,長い年月の末に風化し,砂におおわれたのだろう。
少年は遺跡に近づいていく。誰もいないと思っていたのに,石柱の影の石段に白い衣服の男が背中を見せて腰かけているのを見つける。その男の背後に少年が近づいていくと,男はゆっくりと振り返り少年に言った。
「よく来たね。待っていたよ。長い間」
「えっ,ぼくを? どういうことですか?」と少年は驚いて答えた。
「きみはここに来るべき人間で,私はそれを待ちつづけていたということだ」
「なぜ,ぼくをあなたが」
「きみは迷っていたはずだ。毎日のように火星の砂時計の流れる砂を見ながら,自分の将来について考えていた」
「そうです。ぼくは,いつも火星の砂時計を見ながら考えていました」
「そうだ。きみは迷っていた。きみは地球外文明の研究をしたいと考えていた。しかし,そんな非現実的な夢が果たしてかなえられるだろうかと思っていた」
「そうです。まわりの人たちはみな反対でした。ぼくも宇宙開発局の伯父の話を聞いて,まだ時代が早すぎると思うようになっていました」
「宇宙のどこかにある文明をさがして,きみが恒星間宇宙船に乗り込むとする。しかし,文明の可能性のある天体にたどりつくまでには何百年かかるかわからないし,乗員は,何十世代もの世代交代が必要だろう」
「ぼく自身はその文明に出会うことはできないのです。それに子孫にしたって,その可能性は非常に少ないのです」
「その考え方には,根本的に大きな間違いがある。きみたちは文明の可能性として,遠いとおい恒星系ばかりに目を向けていた。しかし,もしもっと近いところに文明の痕跡があったとしたらどうする?」
「えっ,それはどういうことですか?」
「つまり,もし太陽系内に文明があったとしたら」
「太陽系の,地球以外の惑星や衛星には知的な生命は過去にも未来にも存在しないでしょう」
「ところが,この遺跡を見てごらん」
「この遺跡? ここは一体どこなんですか? 地球の砂漠じゃないんですか?」
「ここは,火星なんだ」
「火星? 今までの調査ではこんな遺跡は見つかっていません」
「この遺跡は火星の砂漠の下に埋まっている。だから,まだ発見されていない。しかし,やがてきみがこの遺跡を発見することになる。将来の話だが」
「えっ,ぼくが?」
「そうだ。きみは火星に遺跡があることを信じて,将来,火星を調査する。そして,この遺跡を発掘することになるのだ」
「こんな大発見を,ぼくが?」
「きみが今の情熱と信念を持ちつづけたとしたらだが......。きみの故郷にはこんな話があるだろう。子供の時に,火山の噴火で滅びた古代都市があると聞いた男が,大きくなってもその話を忘れず,ついに灰に埋もれた都市を発掘することになる。誰もがその話を伝説に過ぎないと思い,本気になってさがそうとはしなかった。しかし,その話を信じた彼だけが栄光を勝ち取ることができた。情熱と信念を持ちつづけるということは素晴しいことじゃないだろうか」
「でも,本当に火星にはこんな文明が過去に栄えたのでしょうか?」
「それは,間違いない。私はここに住んでいたのだから」
「あなたは火星人ですか?」
「そうだ。そして,文明は滅び,町も私たちも砂に埋もれた。私たちの精神と意識は赤い砂に埋もれ,その砂の一粒ひとつぶにしみこんだ。私たちは滅びたが,私たちの精神はこの赤い砂の中に生きつづけている。それで,砂時計を見つめていたきみに私たちの思いが届いたのだ。どうだね,きみはそれを信じるだろうか」
「ぼくが火星で,砂の下に埋もれた古代の火星文明を発見する。もし,それが本当だったら,ぼくはどんな犠牲を払っても,そのための努力を惜しまないでしょう。その夢を実現するために」
「きみならばできる。信じつづければかなえられる。私はきみをここで待っている。再び,会える日まで」
男はそこまで話すと立ちあがり,少年にやさしく微笑んだ。
風が吹いてくる。赤い砂が舞う。その男は両手を広げ,風に身をまかせた。男はさらさらと砂になり崩れていく。身体が赤い砂になり,風に吹き飛ばされていく。少年はそれを声もなく見つめていた。
赤い砂がさらさらと流れていく。そして,最後の一粒が,砂時計を流れ落ちた。
少年は,火星の砂時計の三分間がいつのまにか過ぎたことを知った。
(『火星の砂時計』株式会社サンリオ1988年現在は絶版)