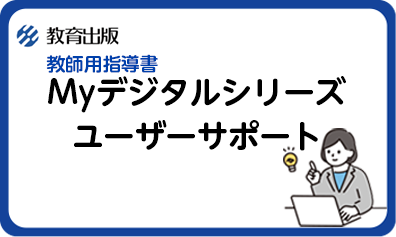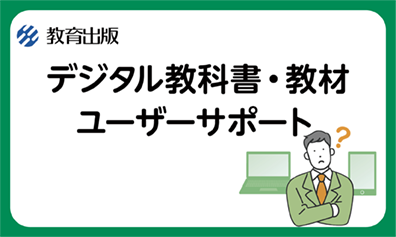一億年プール
すやまたけし
学校には,異次元の世界へつながっているのではないかと思われる場所がある。
誰もいない放課後の体育館,階段の踊り場,理科の実験室,そして夜のプールだ。
静まりかえった,ひとけのないそれらの場所に一人たちつくし,目を閉じて心を空にしてみる。すると,かすかな町の騒音や,風に運ばれてくる子供たちの声は,いつの間にか遠ざかり,時間や空間を超えた過去や未来のどこかの場所から,哀しい呼び声が聞こえてくるはずだ。
ある真夏の夜,ぼくと友人は冷房のない部屋でむせかえるほどの熱気にぐったりとしていた。数日前からつづく熱帯夜は,安心と幸福の船をひっくりかえし,ぼくたちを不眠と不快の渦の中にひきずりこんだ。開けはなたれた窓の外は,そよ風さえなく,濃密で暑い闇がねっとりといすわっていた。
「おい,ひと泳ぎしてこないか」
ぼくにも,現在の苦痛をいやす名案はそれ以外に思い浮かばなかったので,小さくうなずいた。
ぼくたちは,熱い夜の街に水着とタオルを持って飛び出した。
街は煮立った鍋の中のように,むせかえっていた。国道を走る車は,このやるせない熱い夜から脱出をこころみるかのように猛烈なスピードで飛ばしていた。ぼくたちも,気がおかしくならないうちにと,学校への道を急いだ。
国道の明るさと騒がしさとは対照的に,樹木に囲まれた学校は,闇と静寂の中にひっそりとその黒い影をそびえさせていた。
警備員に見つからないように,ぼくたちは校舎の裏側の,街灯の影になっている塀を乗り越えた。そして,西側のプールへ忍ぶようにまわった。
誰もいない真夜中のプールは,不気味なほどに静まりかえり,水面は鏡のように波も音もなく静止していた。
ぼくたちは,汗ばんだTシャツとジーパンを脱ぎ捨て水着にはきかえた。その時,友人が「あれっ」と小さな声をあげた。
「いけない。ポケットに入れてあった財布がない。塀のところで落としたらしい」
友人はポケットをさぐりながら小声でぼくに言った。
「ちょっと,見てくる」
友人が闇の中に消え,ぼくは一人プールサイドに取り残された。少しはなれたところにある水銀灯が,プールをうす明るく照らしだしている。裸になったぼくの肌を包む空気は,相変わらず蒸し暑かった。ぼくは友人が戻ってくるのを待ちきれず,先に一人で泳ぐことにした。
ひととおり,手足の体操をしてから,ぼくはプールの水面にゆっくりと足の先をいれていった。熱を持った足に,その冷たいプールの水はひんやりとして気持ちが良かった。
すっかり首まで水につかり,ぼくは軽くプールサイドをけって,そこからはなれた。
少しずつ,身体全体にこもっていた熱が水の中に溶けだしていくのがわかった。抜き手を切って,プールの真ん中の一番深いところまでくると,ぼくはあおむけになった。
身体の力を抜いて,ぼくはそのままの姿で水面に浮かんでいた。筋肉の緊張がほぐれるとともに,ぼくの心も解きほぐされていくようだった。
水面に漂いながら夜空を見上げると,校舎の上に満月がかかっていた。水につかった耳には,水中のいろいろな音が聞こえてくる。水が揺れるがままに,さまようように漂っていると,ふと,前にも同じようなことをしていたことがあるような気がした。
いつのことだろう,どこでだったか,記憶をたどってみても思い出せなかった。既視現象なのだろうか,それとも遺伝子や無意識の奥底にひそむ,潜在的な記憶であるのか,ぼくはしばらくの間,自分の意識の中をさまよっていた。
ぼくたちの祖先は,三十数億年前に海で生まれた。限りない絶滅や進化をくり返し,試行錯誤の末に,勇気あるものが陸上へはいあがってきた。
プールの中で,こうして孤独に浮かんでいると,太古の海の中での生命の記憶がよみがえってくるのかもしれない,と思った。
遙かな時間の流れをさかのぼり,原初の海の中でやがて明けてくる進化の朝をまちつづける原始生物。たとえようもなく不安で孤独でありながら,その反面,そこはもっとも安らかで平安な時と場所であるような気がした。母なる海という暖かい胎内で,静かにゆるやかに,柔らかい時が過ぎていくのを見守っているような......。
その時,西の方から進んできた黒い雲が満月を隠しはじめた。風が吹いている。そして,夜空は明るさを失った。
ぼくはあおむけになったまま,闇が世界をおおっていくのを見つめていた。
黒い絵の具で溶かしたような雲が流れさり,再び満月が現われた。雲が吹き払われたあとの澄みきった夜空には,数えきれないほどの星が現われた。
ぼくは波間に漂っていた。プールも校舎も木も水銀灯も消え去り,ぼくは海の中にいることを知った。ぼくの全身はぬめぬめとした灰色の皮膚でおおわれていた。不思議なことに,恐怖感や嫌悪感はわきおこっていなかった。自由に泳ぎまわれる新しい自分に,誇らしささえ覚えた。
潮の流れにしたがっていくと,陸地にたどりついた。陸上は熱帯を思わせる密林におおわれ,そのからみあった太い枝や大きな葉は岸辺から海の中にまであふれていた。
その深い闇の中で,突然木の枝がはじけ折れる音がした。葉ずれの音もしている。ぼくは注意深くその方角を見つめた。岸辺の木々の影に黒い大きな物の気配がする。ぼくはゆっくりと近づいていった。
ガサガサと動くその大きな影の正体がわかった。それは,恐竜だった。長い首を水辺にのばして,黙々と水草を食べているのだ。
巨大な身体の彼らは,やがて大隕石の落下がもたらした地球規模の気象異変によって,絶滅することになる。ぼくは,何も知らない彼の姿を見ているうちに,淋しくなってきた。しかし,これはどうしようもないことなのだ。恐竜は自分の未来に何の疑問も抱かないかのように,静かにゆうゆうと草をはんでいた。
きみたちはやがて滅び、ぼくたちが地上を支配することになる。しかし,ぼくたちにしたって,明日が見えないことには変わりがないのだ。ぼくは水の中に漂いながら,このままいつまでも海の中にいたほうが幸福なような気がした。
あおむけになり,星のきらめく夜空を見上げると,大きな流星が長い尾をひいて落ちていくのが見えた。そして,またひとつ......。
「おい,あった,あった。やっぱり飛びおりた時に落としたんだ」
いつの間に戻ったのだろう。友人が財布を振りふり,プールサイドからぼくに呼びかけている。なぜ,あんなにうれしそうな顔をしているのだろう。財布をなくそうが,見つけようが,それがぼくたちにとって,いったいどんな意味があるというのだろう。
ぼくは水面に横たわったまま,友人の笑顔を不思議な生き物を見るかのように見つめていた。
(『火星の砂時計』株式会社サンリオ1988年現在は絶版)