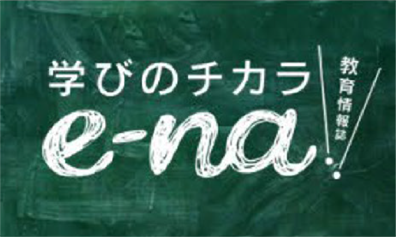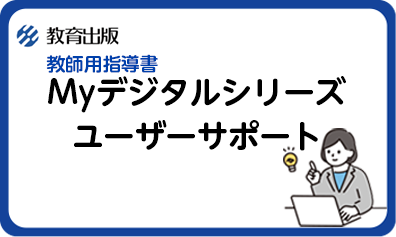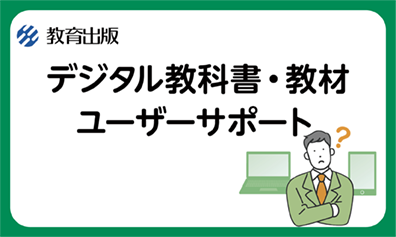井口時男が読む「教科書の俳句」
第1回 正岡子規①
● このページは,画面の幅が1024px以上の,パソコン・タブレット等のデバイスに最適化して作成しています。スマートフォン等ではご覧いただきにくい場合がありますので,あらかじめご了承ください。
| 柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺 正岡子規 | 季語:柿(秋) |
| 切れ字:なり |
なにしろ子規は柿が大好物だった。柿の句もいっぱい作った。明治30年(1897)には「我死にし後は」と前書して
柿喰ヒの俳句好みと伝ふべし
と詠んだほどである。
いわば生前の辞世の句だが、まだ心にゆとりがある。五年後の絶筆となった〈糸瓜咲て痰のつまりし仏かな〉などのようには切羽つまっていない。
そうした「柿喰ヒ」子規の数ある柿の句の中でも一番ポピュラーなのがこの〈柿くへば〉だ。というより、子規のすべての句の中で、それどころか近代に詠まれた無数の俳句の中で、一番ポピュラーな句がこれだろう。単純で、わかりやすくて、子供でもまねしたくなる。そこがよい。
この句の人気を支えているのは、子供も含めた大衆(俳句の専門家ではない一般人)なのだと思う。暗記しやすく口ずさみやすい俳句の場合、「人口に膾炙する」か否かはとても大事な評価ポイントなのである。
いきなり「柿くへば」。このストレートで無造作な俗語口調が俳句らしくて心地よい。そして、「柿くへば」の味覚・食感はただちに「鐘が鳴るなり」の聴覚に転じ、さらに「法隆寺」で斑鳩の秋の風景が眼前に広がる。しかもこの風景は歴史的連想の奥行まで含んでいるのだ。
赤い実をいっぱいつけた柿の木は日本(九州から東北まで)の秋の風景の代表だし、柿は奈良の名産でもある。そして奈良(大和)は古代日本の中心地、法隆寺は古代文化のシンボルだ。その二つを取り合わせて、しかも「柿くへば鐘が鳴る」のである。まるで柿の実にかぶりついたとたんに鐘が鳴ったようで、ちょっと劇的だ。
(もちろん動詞「くふ」の已然形に付いた接続助詞「ば」は、ここでは単純接続だが、読者の意識には原因理由のニュアンスも、つまりは柿を食ったことが引き金になって鐘が鳴ったかのようなニュアンスも、一瞬ちらつくだろう。言葉の効果とはそういうものだ。)
それにしても、法隆寺と柿。名所と名物の取り合わせ。典型的すぎやしないか。これじゃ富士山に茶畑や三保の松原を取り合わせるようなものではないか。
しかし、子規自身は「くだもの」というエッセイでこう書いている。
「柿などといふものは従来詩人にも歌よみにも見放されてをるもので、殊に奈良に柿を配合するといふ様な事は思ひもよらなかつた事である。余は
生涯厖大な「俳句分類」を続けた子規のいうことだ、まちがいはないだろう。つまり、柿は「雅」を尊ぶ詩人(漢詩人だろう)や歌人に見向きもされなかった「俗」なくだものだったのだ。そして、「雅」なる古都奈良に「俗」なる柿を配合した詩歌も俳諧も存在しなかったのだ。子規が初めてやったのである。子規は典型を模倣したのでなく、子規のこの句が典型を作り出したのである。
ところで、〈柿くへば〉は明治28年(1895)秋の作だった。この年5月、日清戦争従軍記者として渡った大陸からの帰途(戦争そのものは子規が日本で待機しているうちに休戦になっていた)、船中でひどく喀血して、神戸や須磨で療養し、故郷松山に帰って(漱石の下宿で起居を共にした)体力の回復を待った後、十月末、東京へ帰る途中で奈良を訪ねたときに詠んだのである。ちゃんと前書もついている。
法隆寺の茶店に憩ひて
柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺
そして、前に引用した「くだもの」の一節は、この奈良訪問の時の思い出をつづっているのである。
では、奈良と柿の取り合わせは前例がない、と自負する子規は「くだもの」でこの句のことを書いているか。書いていないのである。
彼が書いたのは別なエピソードだった。
奈良の宿で夕食を済ませた後、名物の御所柿を所望したら女中が大きな丼鉢に山盛りにして持ってきた。女中が皮をむいてくれたのを食っていると寺の鐘が鳴った。どこの鐘かと聞くと東大寺の大釣鐘だと答えて外を見せてくれた。「成程東大寺は自分の頭の上に当つてゐる位である」というのである。
きっとこれが事実だったのだ。それなら〈柿くへば鐘が鳴るなり東大寺〉である。前書も法隆寺も虚構なのだ。実際、子規の句稿「寒山落木」の明治28年には、〈柿くへば〉の他に「法隆寺二句」として〈行く秋をしぐれかけたり法隆寺〉と〈行く秋を雨に汽車待つ野茶屋哉〉がある。たぶんこちらの二句の方が法隆寺の実景に近かったのだろう。
子規は夜を昼に変え、東大寺を法隆寺に変え、宿を茶店に変えたのである。つまり子規は、事実をそのまま句に詠んだのでなく「虚構化」したのである。体験的事実を踏まえながらも、事実を離れて句を「構成」したのである。
たしかに子規は「写生」を主張した。「写生」の基本は見たままありのままを描くことだ。だが、たった十七音で風景を「写生」する困難は誰にもわかる。長大な散文ですらありのままに「写生」するのは難しい。まして短小な俳句においてをや。
いっそ極論すれば、俳句ほど「写生」に向かない詩形はないのである。だから、短すぎる俳句は、多様な風景の中から対象を極度に限定し、他の一切は捨ててそれだけを抽出し、抽出したものを小さい定型の枠の中で組み合わせる、というやり方をとるしかない。つまり事実そのままを離れて、言語秩序としての作品世界を「虚構」し「構成」するしかない。それが、事実(現実)と異なる位相に作り出される「詩的真実」というものだ。
たとえば『病床六尺』によれば、虚子と並んで子規門の高弟だった碧梧桐は〈柿くへば〉の句を評して、「『柿食ふて居れば鐘鳴る法隆寺』とは何故いはれなかつたであらう」と疑問を呈したという。「これは
おそらく碧梧桐は、「柿くへば鐘が鳴る」がちょっと劇的すぎる、つまりちょっと嘘(虚構)くさい、と感じたのだろう。後に、ありのままに拘泥して「無中心」論を唱え、その結果俳句の散文化を推し進めてしまう(次にはその反省として、「詩」を回復するために過激な「前衛」志向を強めていく)碧梧桐らしい感想だ。対して、子規は事実そのままより「句法」の強さ、すなわち詩的効果というものの方を重視しているのである。
ここで、世間の「常識」に対して強調しておきたいことがある。
子規が「写生」を主張したのは、あくまで、和歌俳諧の手垢に染みた出来合いの自然イメージを打破して、新たな「発見」をするための手段としてだった。現実べったりの「写生」が彼の俳句の目的(理想)だったわけではない。
現に、明治二十八年、奈良を巡って帰京した後に書き出した『俳諧大要』では、俳句学習を三段階に分けて、最終三段階目にこう書いている。
「空想と写実と合同して一種非空非実の大文学を製出せざるべからず。空想に
ここではまだ「写実」という言葉を用いているが、「非空非実の大文学」、すなわち、ただの空想でもただの写実でもなく、両者の総合・止揚としての言語世界を作り出すこと、それこそが「至る者」(俳句を極めた者)の表現の理想だ、と言っているのである。
それにしても、なぜ子規は東大寺を捨てて法隆寺を選んだのか。東大寺(トーダイジ)という寺名の響きも大仏殿や「鎮護国家」の連想を誘うイメージも、法隆寺(ホーリュージ)に比べて少し重すぎる、というのが私の感じだが、こういう感じを理詰めで説明するのはとても難しい。子規も理詰めで判断したわけではなかっただろう。子規の直感、鋭敏な俳句的感性の勝利だというしかない。
とはいえ、事は人それぞれに異なって論理化しにくい感性の問題なので、俳句の評価というものは実に厄介だ。実際、この句は発表された時もとくに話題にならなかったそうだし、虚子と碧梧桐共選になる子規の俳句選集にも収められなかったそうだ。子規没後の俳句界を担った高弟二人はこの句をちっとも評価していなかったのである。
では、法隆寺を選んだ子規の感性に「勝利」をもたらしたのは、俳句の専門家ではなく、やっぱり後世の大衆の支持だったのである。
最後に、この場を借りて拙句を二句。
十有九士この柿手向けん俗の柿 (句集『天來の獨樂』)
会津若松の白虎隊の墓を訪れたときの句。この「俗の柿」は、大義に殉じて聖化された若き死者たちに、俗世間を生きながらえている現代の旅人が手向ける柿である。
虚無僧になりたし柿の花こぼれゐる (「2019年版俳誌要覧」東京四季出版)
こちらは柿の実ではなく散りこぼれた柿の花。柿の実は色あざやかに目を引くが、柿の花は小さくて色合いも地味で、若葉に隠れて目立たない。まさに「花ともあらぬ柿の花」(三好達治「青くつめたき」)だ。
*2019年11月11日、本文一部加筆修正しました。