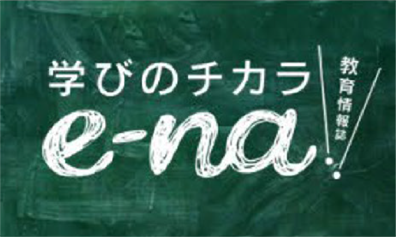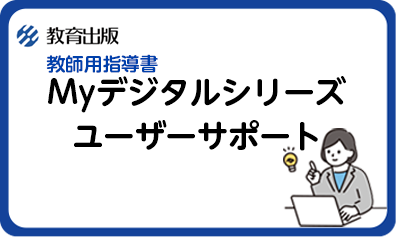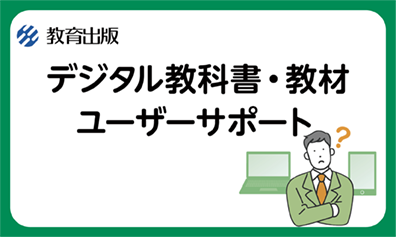数学問はず語り 第2回
日本人の図形的感性(その2)
岡本光司(元静岡大学教授)
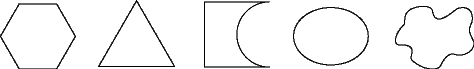
図形(左からA,B,C,D,E)
先日,300人近い60歳以上の高齢者を対象とした会で講演をする機会があった。その折り,参会者に日仏比較研究で使った次のような5つの図形を見せ,どの図形にもっとも落ち着きを感じるかと質問したところ,9割を超える方々がD(楕円)を選んだ。E(曲線図形)を選んだ方はただ一人であった。
私も前者の仲間であるが,日本人は,単純でまろやかなもの,端正で均整のとれたものに対して,ある種の憧憬とか親しみを感じる感性をもっているのだと改めて思った。こうした感性傾向は,小学生や中学生においてもみられることを前回述べたが,高齢者になるとさらにその度合いが強まるようである。
このことを教育という視点に立って考えた場合,どんなことがいえるのだろうか。個性とか創造性といったこととかかわるのではあるまいか。
P.バロンの研究(1962)によれば,画家や博士候補のような創造に従事する人達は,単純で対称的な図形を嫌い,複雑で非対称的な図形を好むパーソナリティーをもつという。こうした知見からは,「創造」という点で,日本の子ども達は決して有利とはいえないようである。
目下,日本の算数・数学教育では,個性を重視し,創造性の育成をめざしている。それは,今後,国際的にも活躍していける人材を育てていくためには欠かせないことなのである。しかし,日本の子ども達が,論理とか理性以前の感性において,上記のような負の要因と考えられるものを抱えているだけに,そうした目標の達成は決して容易ではなさそうである。
しかし,私は日本人の感性傾向をそれほど悲観的にはとらえていない。そこには欧米人のそれとは異質なすばらしさがあると思うからである。それは,今なお,能や茶道や俳諧など様々な日本の伝統的芸術においてみられるものであるが,ほとんど変化や起伏のない微妙さの中に豊かな違いを見出せるという感性であり,単調な一本の線にすら無限を感じることができるという感性である。
グローバル化の進む時代にあってなお,単に欧米に追い着け,追い越せといった発想に終始せず,そうした日本人の感性を生かす形での個性教育,創造性教育の開発ということを考えていけないものだろうか。